「仮定法」と聞くと、多くの人が「If I were a bird…」のような仮定法過去や、「If I had studied harder…」のような仮定法過去完了を思い浮かべるかもしれませんね。「でも、仮定法って現在形もあるの?」そんな疑問を持ったことがある方もいるのではないでしょうか。実は、英語には「仮定法現在」と呼ばれる形も存在するんです。ただ、これは私たちが学校で習う「もし現在~なら」というような、いわゆる「現在の事実に反する仮定」とは少し毛色が違う、ちょっと特殊な仮定法なんです。英語学習を始めたばかりの方や、中学生、高校生、そして大学受験やTOEICでより正確な文法知識を目指す皆さんにとって、この仮定法現在は、少し馴染みが薄いかもしれませんが、知っておくと「なるほど!」と納得できる表現の一つですよ。
「仮定法現在って、一体どんな時に使うの?」「普通の現在形と何が違うの?」そんな皆さんの疑問に答えるために、この記事では、仮定法現在の基本的な考え方から、特によく使われる「要求・提案・必要などを表す動詞や形容詞の後の that節で、動詞の原形(または should + 原形)が使われる」という重要な用法について、具体的な例文をたくさん見ながら、一つひとつ丁寧に解説していきます。この記事を読み終わる頃には、きっと仮定法現在の謎が解け、英文読解や英作文で役立つ知識が身についているはずです!

仮定法に現在形もあるなんて知らなかった!これでスッキリわかるかな?
仮定法現在の基本 – 「あるべき姿」や「願望」を表す形
まずは、仮定法現在とは一体どのようなもので、どんなニュアンスを持つのか、基本的なところから見ていきましょう。これは、事実を述べる「直接法」とは異なる、「心の中の姿」を表す表現方法の一つなんです。
仮定法現在とは? – 動詞の原形が使われる特別な形
仮定法現在とは、現在の事実や状態とは関係なく、話し手の願望、要求、提案、必要性、祈りなどを表す際に、動詞の原形(または should + 動詞の原形)を用いる表現方法のことです。ポイントは、主語が三人称単数 (he, she, it など) であっても、動詞の原形が使われる、という点です。つまり、三単現の -s がつかないんですね。
例えば、
- God save the Queen! (神よ、女王を守りたまえ!)
→ この “save” は、主語が三人称単数 (God) であるにもかかわらず、saves とならずに原形のままです。これは「~でありますように」という祈りや願望を表す仮定法現在の一例です。
- It is necessary that he be present at the meeting. (彼がその会議に出席することが必要だ。)
→ この “be” も、主語が he であるにもかかわらず is ではなく原形の be が使われています。これは「~であるべきだ」という必要性を表す仮定法現在です。
このように、仮定法現在は、事実をそのまま述べるのではなく、「こうあるべきだ」「こうなってほしい」という話し手の心の中の考えや判断を表現するときに使われます。そのため、時制の一致のルールなども適用されず、常に動詞の原形(または should + 原形)が使われるのが特徴です。
現代英語では、特にアメリカ英語で、この仮定法現在の「動詞の原形」の形がよく使われます。イギリス英語では、「should + 動詞の原形」の形の方が好まれる傾向があります。どちらの形も同じ意味を表します。
仮定法現在の主な使われ方 – 祈願文と要求・提案・必要の that節
仮定法現在は、大きく分けて主に以下の二つの場面で使われます。
- 祈願文 (きがんぶん): 「~でありますように」「~あれ!」というように、神への祈りや強い願望を表す文。
例: Long live the King! (王様万歳! / 王よ、長く生き給え!)
例: Heaven forbid that such a thing should happen! (そんなことが起こるなんて、とんでもない! / 神様、そんなことが起こりませんように!)
- 要求・提案・必要・重要などを表す動詞・形容詞・名詞の後の that節: これが現代英語で最もよく使われる仮定法現在の形で、今回の記事のメインテーマです。
「(主語)が~するべきである」というニュアンスで、that節の中の動詞が原形(または should + 原形)になります。
例: The doctor suggested that she (should) take a rest. (医者は彼女に休息をとるべきだと提案した。)
祈願文は、やや古風な響きを持つものや、決まった言い回しで使われることが多いです。一方、2番目の that節の用法は、日常的なコミュニケーション(特にフォーマルな場面や書き言葉)でも頻繁に使われるため、英語学習者にとっては非常に重要です。
仮定法現在と直接法現在の違い – 事実 vs. あるべき姿
仮定法現在と、通常の「現在形」(直接法現在)との違いを理解しておくことが大切です。
- 直接法現在: 現在の事実や習慣的な状態をありのままに述べる。
例: He is present at the meeting. (彼は会議に出席している。) ← 事実
- 仮定法現在: 事実かどうかは問題にせず、「そうあるべきだ」「そうなることが望ましい」という話し手の判断や要求を表す。
例: It is important that he be present at the meeting. (彼が会議に出席することが重要だ。) ← 「出席しているべきだ」という当為・要求
つまり、仮定法現在は、現実がどうであるかよりも、「どうあるべきか」「どうなってほしいか」という理想や規範、要求に焦点が当たっている表現だと言えますね。
「彼が会議に出席する」って、普通の現在形でも言えそうなのに、わざわざ仮定法現在を使うのはなぜですか?
いい質問ですね! もし “It is important that he is present at the meeting.” と直接法現在を使うと、「彼が出席しているという事実が重要だ」という意味合いになります。一方、仮定法現在で “It is important that he be present…” と言うと、「彼が出席しているかどうかはまだわからない(あるいは出席していないかもしれない)が、とにかく彼が出席するという状況が重要だ・そうあるべきだ」という、より強い要求や当為のニュアンスが出るんです。「まだ実現していないけど、そうなるべきだ」という気持ちが込められているんですね。

へぇ~、仮定法現在って、動詞が原形になるんだ!「~べきだ」って感じなんだね。God save the Queen! って、あれも仮定法だったんだ!
要求・提案・必要・重要などを表す that節での仮定法現在
ここからは、現代英語で最も重要となる、特定の動詞・形容詞・名詞の後に続く that節の中で使われる仮定法現在について、詳しく見ていきましょう。これがマスターできれば、あなたの英語表現は格段に洗練されますよ!
「Sが~すべきだ」というニュアンス – 動詞の原形 or should + 原形
この用法では、that節の中で「(主語)が~するべきである」「(主語)が~するように」という、一種の命令や強い推奨に近いニュアンスが込められます。そのため、that節の動詞は、主語の人称や数に関わらず、常に動詞の原形になるか、あるいはshould + 動詞の原形の形をとります。
基本の形:
[要求・提案・必要・重要などを表す動詞/形容詞/名詞] + that + 主語 + (should) + 動詞の原形 …
例:
- The teacher demanded that the student apologize. (先生はその生徒が謝罪するよう要求した。)
(または … that the student should apologize.)
- It is essential that everyone understand the rules. (全員がルールを理解することが不可欠だ。)
(または … that everyone should understand …)
- My suggestion is that we postpone the meeting. (私の提案は、会議を延期すべきだということです。)
(または … that we should postpone …)
アメリカ英語では動詞の原形が、イギリス英語では should + 動詞の原形が好まれる傾向がありますが、どちらを使っても文法的に正しく、意味もほぼ同じです。TOEICなどの試験では、どちらの形も出題される可能性があります。
否定形にする場合は、動詞の原形の前に not を置くか、should not + 動詞の原形 とします。
- He insisted that she (should) not go there alone. (彼は彼女が一人でそこへ行くべきではないと主張した。)
仮定法現在を導く主な動詞 (suggest, demand, require, insistなど)
that節に仮定法現在(動詞の原形 / should + 原形)を導く代表的な動詞には、以下のようなものがあります。これらは「~するように要求する」「~するように提案する」といった意味合いを持つものが多いです。
主な動詞のリスト:
- suggest (提案する)
例: I suggested that he (should) see a doctor. (私は彼に医者に診てもらうよう提案した。)
- propose (提案する)
例: She proposed that a new committee (should) be formed. (彼女は新しい委員会が作られるべきだと提案した。)
- recommend (推薦する、勧告する)
例: The report recommends that the company (should) invest more in R&D. (その報告書は会社が研究開発にもっと投資すべきだと勧告している。)
- demand (要求する)
例: They demanded that the government (should) take immediate action. (彼らは政府が即座に行動を起こすよう要求した。)
- require (要求する、必要とする)
例: The law requires that all drivers (should) have a license. (その法律は全ての運転手が免許を持つことを要求している。)
- request (要請する、頼む)
例: He requested that his name (should) not be mentioned. (彼は自分の名前を出さないよう要請した。)
- insist (主張する、強く要求する)
例: She insisted that he (should) tell the truth. (彼女は彼が真実を語るべきだと主張した。)
- order (命令する)
例: The captain ordered that the soldiers (should) advance. (隊長は兵士たちに前進するよう命令した。)
- urge (強く促す、説得する)
例: They urged that the plan (should) be reconsidered. (彼らはその計画が再考されるべきだと強く促した。)
- ask (頼む、要求する) ※「尋ねる」ではなく「要求する」の意味の場合
例: I ask that you (should) be quiet. (静かにしていただくようお願いします。)
- move (動議を出す、提案する) ※会議などで
例: I move that the meeting (should) be adjourned. (会議を閉会することを動議します。)
- decree (布告する、命令する)
例: The king decreed that a new tax (should) be imposed. (王は新しい税が課されるべきだと布告した。)
これらの動詞は、that節の内容が「まだ実現していないが、そうなるべきだ」という話し手の強い意向を表しています。そのため、that節の中は未来志向の「原形」または「should + 原形」になる、と考えると理解しやすいですね。
注意点: “insist” は、「(事実として)~だと主張する」という意味の場合は、that節の中は直接法(普通の時制)になります。仮定法現在になるのは、「(~すべきだと)強く要求する」という意味の場合です。
- He insisted that he was innocent. (彼は自分が無実だと主張した。) ← 事実の主張なので直接法
- He insisted that he be given another chance. (彼はもう一度チャンスを与えられるべきだと主張した。) ← 要求なので仮定法現在
仮定法現在を導く主な形容詞 (necessary, important, essentialなど)
It is … that ~ の構文で、… の部分に「必要だ」「重要だ」「不可欠だ」といった意味の形容詞が来る場合、that節の中は仮定法現在(動詞の原形 / should + 原形)になることが多いです。
主な形容詞のリスト:
- necessary (必要な)
例: It is necessary that you (should) finish this by tomorrow. (明日までにこれを終えることが必要だ。)
- important (重要な)
例: It is important that we (should) respect each other. (私たちがお互いを尊重することが重要だ。)
- essential (不可欠な、極めて重要な)
例: It is essential that she (should) be informed immediately. (彼女がすぐに知らされることが不可欠だ。)
- vital (極めて重要な、不可欠な)
例: It is vital that the project (should) start on time. (そのプロジェクトが時間通りに始まることが極めて重要だ。)
- imperative (必須の、緊急の)
例: It is imperative that action (should) be taken to solve the problem. (その問題を解決するため行動が取られることが必須だ。)
- crucial (決定的な、極めて重要な)
例: It is crucial that they (should) understand the risks involved. (彼らが関連するリスクを理解することが極めて重要だ。)
- advisable (賢明な、勧められる)
例: It is advisable that he (should) consult a lawyer. (彼が弁護士に相談するのが賢明だ。)
- desirable (望ましい)
例: It is desirable that everyone (should) participate in the discussion. (全員が議論に参加することが望ましい。)
- urgent (緊急の)
例: It is urgent that we (should) find a solution. (私たちが解決策を見つけることが緊急だ。)
- fitting / proper (適切な、ふさわしい)
例: It is fitting that she (should) receive the award. (彼女がその賞を受けるのがふさわしい。)
これらの形容詞も、that節の内容が「そうあるべきだ」「そうなることが望ましい」という話し手の判断や評価を表しているため、仮定法現在が使われます。
仮定法現在を導く主な名詞 (suggestion, demand, proposalなど)
「提案」「要求」「命令」といった意味を持つ名詞が、”The suggestion is that…” や “My demand is that…” のように、that節を伴ってその内容を説明する場合、that節の中は仮定法現在(動詞の原形 / should + 原形)になることがあります。
主な名詞のリスト:
- suggestion (提案)
例: Her suggestion was that the meeting (should) be postponed. (彼女の提案は会議を延期すべきだというものだった。)
- proposal (提案)
例: The proposal that a new park (should) be built was accepted. (新しい公園が建設されるべきだという提案は受け入れられた。)
- recommendation (勧告、推薦)
例: It is my recommendation that you (should) apply for the scholarship. (あなたがその奨学金に応募すべきだというのが私の推薦です。)
- demand (要求)
例: Their demand is that the working hours (should) be reduced. (彼らの要求は労働時間が短縮されるべきだということだ。)
- request (要請)
例: We received a request that the deadline (should) be extended. (私たちは締め切りが延長されるべきだという要請を受けた。)
- insistence (主張、強い要求)
例: His insistence that he (should) be treated fairly was understandable. (彼が公正に扱われるべきだという彼の主張は理解できるものだった。)
- order (命令)
例: The general gave an order that the troops (should) attack at dawn. (将軍は部隊が夜明けに攻撃すべきだという命令を下した。)
- requirement (要求、必要条件)
例: One of the requirements for this job is that applicants (should) have a driver’s license. (この仕事の必要条件の一つは、応募者が運転免許を持っているべきだということだ。)
これらの名詞も、動詞や形容詞の場合と同様に、that節の内容が「まだ実現していないが、そうなるべきだ」という当為のニュアンスを持つため、仮定法現在が使われます。
これらの動詞・形容詞・名詞は、TOEICの文法問題でも「that節の中の動詞の形」を問う形でよく出題されます。「要求・提案・必要・重要」系の言葉の後の that節は「原形 or should + 原形」と覚えておくと、かなり役立ちますよ!
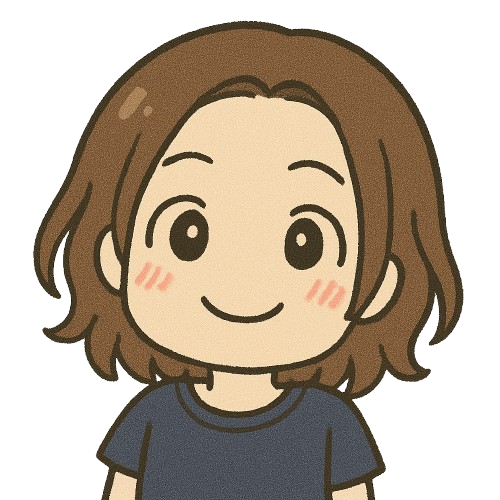
suggest とか important の後の that節は原形!これはテストに出そう!should を入れてもいいんだね。
仮定法現在の使い方と注意点 – より自然な英語のために
仮定法現在のルールが理解できたら、次はそれを実際にどのように使い、どんな点に注意すればよいかを見ていきましょう。ちょっとしたニュアンスの違いや、他の表現との比較も大切です。
アメリカ英語とイギリス英語での傾向の違い (原形 vs. should)
すでにも触れましたが、要求・提案などを表す that節での仮定法現在の形は、アメリカ英語とイギリス英語で使われ方に傾向があります。
- アメリカ英語 (AE): 動詞の原形 を使うのが一般的。
例: The boss insisted that Mary finish the report by Friday. (AE)
- イギリス英語 (BE): should + 動詞の原形 を使うのがより一般的。should を省略して動詞の原形だけを使うこともありますが、should を入れる方が好まれます。
例: The boss insisted that Mary should finish the report by Friday. (BE)
どちらの形も文法的に正しく、意味も同じですが、地域や個人の好みによって使われ方が異なります。国際的なビジネスシーンや、TOEICのような試験では、どちらの形にも対応できるようにしておくのが良いでしょう。
ちなみに、否定の場合は、
- The doctor recommended that he not smoke. (AE)
- The doctor recommended that he should not smoke. (BE)
となります。原形の場合は not を動詞の原形の直前に置きます。
仮定法現在と直接法の使い分け – 「べき論」か「事実」か
要求・提案などを表す動詞の後の that節でも、常に仮定法現在が使われるわけではありません。that節の内容が「事実」や「話し手が事実だと考えていること」を述べている場合は、直接法(通常の時制)が使われます。
仮定法現在 (~すべきだ、~するように):
- She insisted that her son (should) clean his room. (彼女は息子が部屋を掃除するよう主張した。)
→ 息子が実際に掃除したかどうかは不明。掃除「すべきだ」という要求。
直接法 (~という事実を):
- She insisted that her son cleaned his room. (彼女は息子が部屋を掃除したと主張した。)
→ 息子が実際に掃除した、という事実を主張している。
- She insisted that her son had cleaned his room. (彼女は息子が部屋を掃除し終えていたと主張した。)
→ 過去の時点で掃除が完了していたという事実を主張。
このように、同じ動詞 (insist) であっても、that節の内容が「当為(~べきだ)」なのか「事実」なのかによって、使われる動詞の形が変わってきます。文脈をよく読んで、どちらの意味で使われているのかを判断することが大切です。
特に “suggest” や “insist” は、この使い分けが重要になる動詞です。「提案する/要求する」なら仮定法現在、「示唆する/(事実を)主張する」なら直接法、と覚えておきましょう。
仮定法現在の that節の主語が it の場合 – It be …
仮定法現在の that節の主語が三人称単数の場合、動詞が原形になるため、例えば主語が it で動詞が be動詞なら “that it be …” という形になります。これは、普段あまり見慣れない形なので、少し奇妙に感じるかもしれませんね。
- It is necessary that it be done immediately. (それが直ちに行われることが必要だ。)
(It is necessary that it should be done immediately. とも言える。)
- The proposal is that it be put to a vote. (その提案は、それが投票にかけられるべきだというものだ。)
このように、受動態 (be + 過去分詞) の場合でも、be動詞は原形の be になります。”that it is done” ではない点に注意しましょう。
仮定法現在の省略 – should の省略はいつ可能?
要求・提案の that節で使われる仮定法現在では、”should + 動詞の原形” の should は省略して、動詞の原形だけにすることができます。では、この should はいつ省略しても良いのでしょうか?
基本的には、アメリカ英語では should を省略して動詞の原形を使うのが一般的で、イギリス英語では should を入れる方が好まれます。
しかし、どちらの英語においても、should を省略できるのは、文脈から「~すべきだ」という当為のニュアンスが明確に伝わる場合です。もし should を省略することで意味が曖昧になったり、直接法と誤解されたりする可能性がある場合は、should を入れた方が無難です。
特に、
- 主節の動詞が過去形の場合 (例: He suggested that I go.) は、go が過去形なのか原形なのか紛らわしいため、He suggested that I should go. とした方が明確な場合があります。(ただし、文脈で判断できることも多い)
- that節の主語と主節の主語が同じで、かつ主節の動詞が suggest や propose のような場合、should を省略すると、不定詞を使った方が自然に聞こえることもあります。
例: I suggest that I (should) go. よりも I suggest going. や I suggest that we (should) go. の方が一般的。
現代英語では、特に書き言葉やフォーマルな場面では、意味の明確さを期して should を入れることも少なくありません。どちらの形も理解できるようにしておき、自分で使う際には、より明確で自然に聞こえる方を選ぶのが良いでしょう。
TOEICの文法問題などでは、選択肢に「原形」と「should + 原形」の両方がある場合、どちらも正解になり得ることがあります。その場合は、他の選択肢が明らかに間違っていることを確認するのが定石ですね。
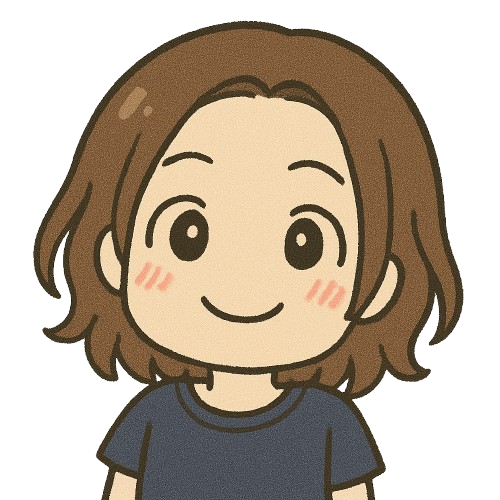
アメリカ英語とイギリス英語で違うんだ!should を入れるかどうか、迷ったらどうしよう…。でも、どっちもOKなのは安心ですね!
まとめ – 仮定法現在を理解して、より正確で洗練された英語へ!
今回は、少し特殊な仮定法である「仮定法現在」について、その基本的な考え方から、特に重要な「要求・提案・必要・重要などを表す that節での用法」を中心に、詳しく見てきました。これで、今まで「なんだかよくわからない…」と思っていた仮定法現在の正体が、少しでもクリアになったのではないでしょうか。
最後に、この記事で学んだ仮定法現在の重要なポイントをまとめておきましょう。
- 仮定法現在とは:
- 現在の事実とは関係なく、話し手の願望、要求、提案、必要性などを表す際に、動詞の原形(または should + 動詞の原形)を用いる表現。
- 「こうあるべきだ」「こうなってほしい」という当為・規範のニュアンスが強い。
- 主な使われ方:
- 祈願文 (例: God save the Queen!)
- 要求・提案・必要・重要などを表す動詞・形容詞・名詞の後の that節
例: I suggest that he (should) go.
例: It is important that she (should) be there.
- that節でのポイント:
- that節内の動詞は、主語の人称や数に関わらず原形、または should + 原形。
- アメリカ英語では原形、イギリス英語では should + 原形が好まれる傾向。
- 否定は not + 原形、または should not + 原形。
- that節の内容が「事実」の場合は直接法(通常の時制)になる。
- 仮定法現在を導く主な言葉:
- 動詞: suggest, demand, require, insist, recommend, propose, order, ask など。
- 形容詞: necessary, important, essential, vital, imperative, advisable など (It is … that ~ の形で)。
- 名詞: suggestion, demand, proposal, recommendation, order など (The suggestion is that ~ の形で)。
仮定法現在は、特にフォーマルな場面や書き言葉で、話し手の強い意向や、あるべき姿を明確に伝えるために使われる重要な表現です。この構文を正しく理解し、使いこなせるようになれば、あなたの英語はより正確で、より洗練されたものになるでしょう。
最初は、動詞が原形になるという点に少し戸惑うかもしれません。でも、「~べきだ」という未来志向のニュアンスを意識しながら、たくさんの例文に触れていくうちに、必ず自然な感覚が身についてきます。TOEICや英検などの試験でも頻出の項目なので、しっかりとマスターしておきましょう。
この記事が、皆さんの英語学習の旅において、仮定法現在という少し手ごわい文法項目を乗り越えるための一助となれば、これ以上嬉しいことはありません。頑張ってくださいね!

仮定法現在、スッキリ理解できた!「べき論」って感じなんだね!これで試験も怖くないかも!

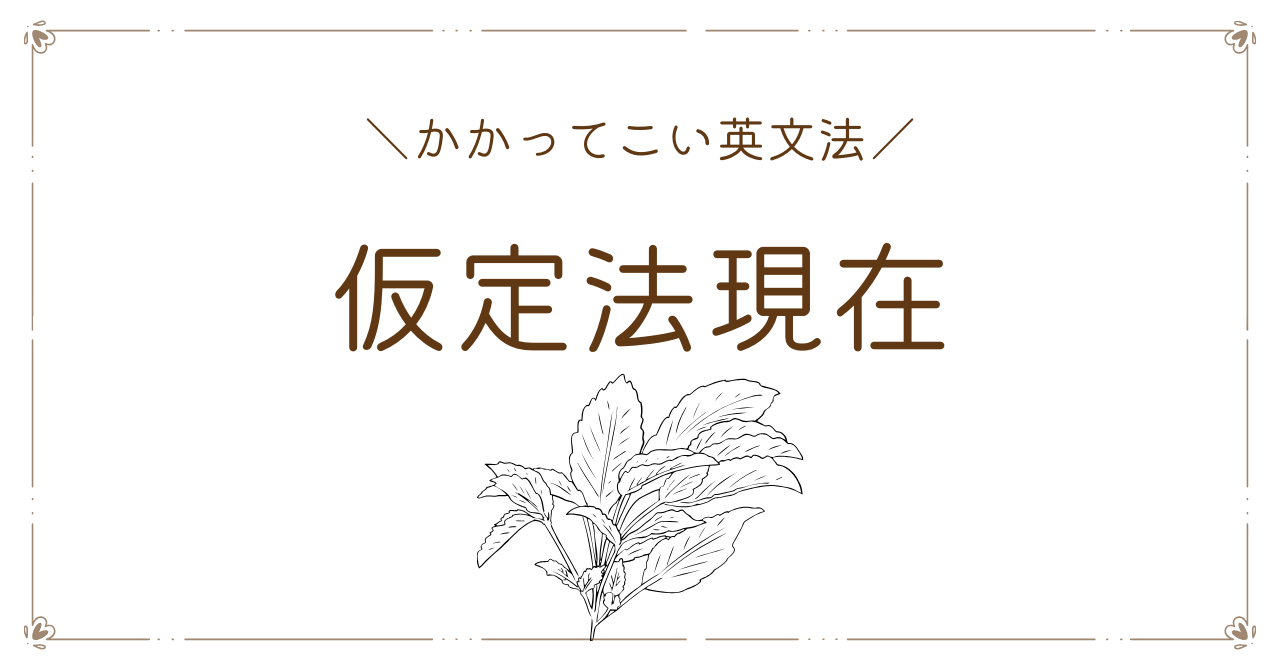
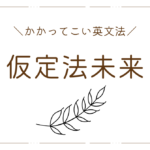

コメント