「もし万が一~なら…」「ひょっとしたら~かもしれないけど…」みたいに、未来のことについて、実現する可能性が低いことや、現実にはまず起こらないだろうなと思うことを仮定して話したいとき、英語でどう表現すればいいか迷ったこと、ありませんか? 普通の if を使った未来の文 (If it rains tomorrow, I will stay home.) とは、なんだかニュアンスが違う気がする…。英語学習を始めたばかりの方や、中学生、高校生、そして大学受験やTOEICでより細やかな表現力を目指す皆さんにとって、この「仮定法未来」と呼ばれるものは、少しとっつきにくい分野かもしれませんね。
「仮定法って、過去形とか過去完了形とか、ただでさえややこしいのに、未来まであるの!?」そう思った方もいるかもしれません。でも大丈夫!仮定法未来には、ちゃんと使い分けのポイントと、覚えておくと便利な形があるんです。この記事では、そんな皆さんのために、仮定法未来の基本的な考え方から、代表的な形である “If S should …” と “If S were to …” の使い方、それぞれのニュアンスの違い、そして訳し方のコツまで、具体的な例文をたっぷり使いながら、一つひとつ丁寧に解説していきます。この記事を読み終わる頃には、きっと仮定法未来のモヤモヤがスッキリ晴れ、自信を持って使いこなせるようになっているはずですよ!

仮定法未来って、なんだか難しそうだけど、これでスッキリわかるかな?
仮定法未来の基本 – 「万が一」や「ありえない未来」をどう表す?
まずは、仮定法未来とは一体何なのか、そしてどんなときに使われるのか、基本的なところから見ていきましょう。「普通の未来の仮定」と「仮定法未来」では、話し手の気持ちが大きく違うんです。
仮定法未来とは? – 実現可能性が低い未来の仮定
仮定法未来とは、未来に起こる可能性が非常に低いこと、または現実にはまず起こり得ないだろうと話し手が考えていることについて、「もし(万が一・ひょっとしたら)~ならば…」と仮定して述べる表現方法のことです。
通常の if を使った未来の条件文(「もし明日雨が降ったら、~するだろう」のような、起こる可能性があることについての仮定)とは区別され、話し手の「まあ、実際には起こらないと思うけどね…」という気持ちが含まれているのが特徴です。
例えば、
- 通常の未来の条件文: If it rains tomorrow, I will stay home. (もし明日雨が降ったら、家にいます。)
→ 明日雨が降ることは、十分にあり得ることとして話しています。
- 仮定法未来: If the sun should rise in the west tomorrow, I would believe you. (もし明日太陽が西から昇るようなことがあれば、君を信じるよ。)
→ 太陽が西から昇るなんて、まずあり得ないですよね。そういった非現実的な仮定をするのが仮定法未来です。
このように、仮定法未来は、単に未来のことを述べるのではなく、話し手の主観的な判断(「これはまずないだろうな」という気持ち)を伴うのがポイントです。
仮定法未来が使われる場面 – 丁寧な依頼や提案、非現実的な仮定
仮定法未来は、主に以下のような場面で使われます。
- 実現可能性が極めて低い未来の出来事を仮定するとき:
例: If I were to live my life over again, I would choose a different career. (もし人生をもう一度やり直せるなら、違う職業を選ぶだろう。)
→ 人生をやり直すのは現実的には不可能ですよね。
- 丁寧な依頼や提案をするとき:
「万が一~していただけるようなことがあれば」というニュアンスで、相手に控えめに依頼したり、提案したりする際に使われます。相手にプレッシャーを与えない、丁寧な言い方になります。
例: If you should change your mind, please let me know. (もし万が一お気持ちが変わるようなことがあれば、お知らせください。)
- 強い疑いや、起こってほしくないことを仮定するとき:
「まさか~ないとは思うが、もし万が一~なら」という気持ちを表します。
例: What would you do if you should fail the exam? (万が一試験に落ちたら、どうしますか?)
仮定法未来は、直接的な表現を避け、より婉曲的で丁寧なコミュニケーションを図りたいときにも役立つ表現なんですね。
仮定法未来の主な2つの形 – “If S should…” と “If S were to…”
仮定法未来を表す代表的な形は、主に以下の2つです。
- If + 主語 + should + 動詞の原形 … , 主語 + 助動詞の原形/過去形 + 動詞の原形 …
- If + 主語 + were to + 動詞の原形 … , 主語 + 助動詞の過去形 + 動詞の原形 …
どちらの形も「もし(万が一)~ならば」という意味合いを持ちますが、ニュアンスや使える場面に少し違いがあります。また、帰結節(主節、カンマの後ろの文)で使われる助動詞も、仮定の内容や話し手の気持ちによって使い分けられます。
この2つの形について、これから詳しく見ていきましょう。

へぇ~、仮定法って未来にもあるんだ!「万が一」って感じなんだね。「should」と「were to」がポイントなのかな?
“If + 主語 + should + 動詞の原形” の仮定法未来
まずは、仮定法未来の代表的な形の一つである “If S should + 動詞の原形” の使い方とニュアンスを詳しく見ていきましょう。「should」が使われるのが特徴です。
形と意味 – 「もし万が一~するようなことがあれば」
この形の仮定法未来は、未来に起こる可能性が低いと話し手が考えていること、または、起こってほしくないが万が一起こった場合を想定して、「もし(万が一・ひょっとしたら)~するようなことがあれば」と述べるのに使われます。
基本の形:
If + 主語 + should + 動詞の原形 …, 主語 + 助動詞の原形/過去形 + 動詞の原形 …
帰結節(主節)で使われる助動詞:
- 未来形 (will, shall など): if節の出来事が実際に起こった場合の、未来の行動や結果を表す。
例: If it should rain tomorrow, the picnic will be cancelled. (もし万が一明日雨が降るようなら、ピクニックは中止になるでしょう。)
- 過去形 (would, should, could, might など): if節の出来事が実際に起こった場合の、推量や仮定的な結果を表す。より丁寧なニュアンスや、実現可能性の低さを強調することが多い。
例: If you should need my help, I would be happy to assist you. (もし万が一私の助けが必要なようでしたら、喜んでお手伝いいたします。)
- 命令文: if節の出来事が起こった場合に、相手にしてほしいことを伝える。
例: If you should see him, tell him to call me. (もし万が一彼に会うようなことがあれば、私に電話するように伝えてください。)
“If S should…” の “should” は、「~すべきだ」という意味の助動詞の should とは異なり、ここでは「万が一」という仮定のニュアンスを出すための特別な働きをしています。なので、「~すべきなら」と訳さないように注意しましょう。
実現可能性の度合い – 普通の if より低いが、ゼロではない
“If S should…” の形で表される仮定は、話し手が「まあ、まず起こらないだろうけど、絶対にないとは言い切れないし、万が一そんなことがあったら…」と考えているような状況で使われます。
つまり、
- 通常の未来の条件文 (If S + 現在形…): 起こる可能性が十分にある。
- 仮定法未来 (If S should…): 起こる可能性は低いが、ゼロではない。「万が一の可能性」を念頭に置いている。
- 仮定法未来 (If S were to…): 起こる可能性がさらに低い、またはほぼあり得ない(後述)。
というような、実現可能性のグラデーションがあります。
例:
- If I win the lottery, I will buy a new house. (もし宝くじに当たったら、新しい家を買うつもりだ。) ← 当たるかも、と思っている。
- If I should win the lottery, I would donate half of it to charity. (もし万が一宝くじに当たるようなことがあれば、半分は慈善団体に寄付するだろう。) ← まあ当たらないと思うけど、もし当たったら…という感じ。
“If S should…” は、「ありえない!」とまでは思っていないけれど、かなり低い確率だと感じている、そんなニュアンスです。
丁寧な依頼や提案で使われる “If you should…”
仮定法未来 “If S should…” は、特に丁寧な依頼や提案、あるいは相手に何かを促す際に、控えめで婉曲的な表現として非常によく使われます。 「万が一~のようなことがおありでしたら」というニュアンスで、相手にプレッシャーを与えずに、こちらの意向を伝えることができます。
- If you should have any questions, please do not hesitate to contact us.
(もし万が一ご質問がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。)
→ 企業からの案内などでよく見かける丁寧な表現ですね。
- If you should change your mind, feel free to let me know.
(もし万が一お考えが変わるようなことがあれば、どうぞお気軽にお知らせください。)
- Should you require further assistance, our staff will be happy to help.
(万が一さらに援助が必要な場合は、当社のスタッフが喜んでお手伝いいたします。)
→ これは、後述する「if の省略による倒置」の形です。よりフォーマルな響きになります。
このように、ビジネスシーンやフォーマルな場面で、相手への配慮を示したいときに非常に役立つ表現です。
If の省略による倒置 – “Should S + 動詞の原形…”
“If S should + 動詞の原形…” の文では、if を省略して、should を文頭に出し、主語と should の語順を入れ替える(倒置する)ことができます。 これにより、さらに文語的でフォーマルな、あるいは少し硬い印象の文になります。
形: Should + 主語 + 動詞の原形 …
- Should it rain tomorrow, the event will be postponed.
(= If it should rain tomorrow, the event will be postponed.)
(万が一明日雨が降るようなら、イベントは延期されます。)
- Should you need any help, please call this number.
(= If you should need any help, please call this number.)
(万が一助けが必要な場合は、この番号にお電話ください。)
- Should anyone ask for me, tell them I’ll be back in an hour.
(= If anyone should ask for me, tell them I’ll be back in an hour.)
(万が一誰かが私を訪ねてきたら、1時間で戻ると伝えてください。)
この if の省略による倒置は、書き言葉でよく見られます。文頭がいきなり Should で始まっていたら、「あ、これは仮定法未来の倒置かも!」と気づけるようにしておきましょう。TOEICの文法問題でも頻出ですよ!
帰結節が命令文の場合、If S should… の形が特に好まれます。「万が一~なら、~しなさい」という指示を、やや控えめに伝えることができるからですね。

“If you should have any questions…” って、よく見るフレーズだ!あれも仮定法未来だったんだね。倒置もカッコイイ!
“If + 主語 + were to + 動詞の原形” の仮定法未来
次に、もう一つの代表的な仮定法未来の形、”If S were to + 動詞の原形” について詳しく見ていきましょう。こちらは “should” を使う形よりも、さらに非現実的な仮定を表す傾向があります。
形と意味 – 「もし仮に~するようなことがあったとしたら (まずないだろうが)」
この形の仮定法未来は、未来に起こる可能性が極めて低い、あるいは現実にはまずあり得ないと話し手が強く考えていることについて、「もし仮に(万が一にも)~するようなことがあったとしたら」と、非常に低い可能性や非現実的な状況を仮定して述べるのに使われます。
基本の形:
If + 主語 + were to + 動詞の原形 …, 主語 + 助動詞の過去形 (would, could, might) + 動詞の原形 …
帰結節(主節)で使われる助動詞:
- “If S should…” の場合とは異なり、帰結節では主に助動詞の過去形 (would, could, might) が使われます。 will のような未来形は通常使われません。これは、仮定している内容がより非現実的であるため、帰結も現実離れした、あるいは仮定的なものになることが多いからです。
例:
- If the sun were to rise in the west, I would change my mind.
(もし太陽が西から昇るようなことがあったとしたら、私は考えを変えるだろう。)
→ 太陽が西から昇ることはあり得ないので、非常に非現実的な仮定です。
- If I were to be born again, I would want to be a bird.
(もし私が生まれ変わるようなことがあったとしたら、鳥になりたいと思うだろう。)
- What would you do if you were to win a million dollars?
(もし仮に100万ドル当たるようなことがあったとしたら、あなたはどうしますか?)
“were to” の “were” は、仮定法過去で使われる be動詞の過去形と同じ形ですね。主語が単数 (I, he, she, it) であっても、原則として was ではなく were を使います。 (口語では was to が使われることもありますが、フォーマルな場面や書き言葉では were to が標準です。)
実現可能性の度合い – “If S should…” よりもさらに低い、ほぼゼロ
“If S were to…” で表される仮定は、”If S should…” よりもさらに実現可能性が低い、あるいは話し手が「そんなことはまずあり得ない」「想像上の話だけど」と強く感じている状況で使われます。
実現可能性の比較:
- 通常の未来の条件文 (If S + 現在形…): 実現の可能性がある。
- 仮定法未来 (If S should…): 実現の可能性は低いが、ゼロではない。「万が一」
- 仮定法未来 (If S were to…): 実現の可能性は極めて低い、またはほぼゼロに近い。「まずありえないが、仮に」
例:
- If he comes, I will talk to him. (もし彼が来たら、彼と話すつもりだ。) ← 来る可能性がある。
- If he should come, I would be surprised. (もし万が一彼が来るようなら、私は驚くだろう。) ← 来る可能性は低いと思っている。
- If he were to come now, it would be a miracle. (もし仮に彼が今来るようなことがあったとしたら、それは奇跡だろう。) ← 来ることはまずあり得ないと思っている。
このように、使う形によって、話し手の「未来の出来事に対する確信度」が表現されるわけですね。
主語の意志とは無関係な出来事を仮定することが多い
“If S were to…” の構文は、主語の意志や努力ではどうにもならないような、偶然起こるかもしれない(しかし実際にはまず起こらないだろう)出来事を仮定する場合によく使われる傾向があります。
- If a major earthquake were to hit Tokyo, what would happen?
(もし仮に大地震が東京を襲うようなことがあったとしたら、何が起こるだろうか?)
- If war were to break out between the two countries, it would be a disaster.
(もし仮にその二国間で戦争が勃発するようなことがあったとしたら、それは惨事になるだろう。)
一方、”If S should…” は、主語の意志が関わる行動(例: If you should change your mind)についても使うことができます。
“were to” は、実現性が極めて低いことや、想像上のシナリオを描写するのに適しているので、小説や物語などで、非現実的な設定を導入する際にも使われたりしますよ。
If の省略による倒置 – “Were S to + 動詞の原形…”
“If S should…” の場合と同様に、”If S were to + 動詞の原形…” の文でも、if を省略して、were を文頭に出し、主語と were の語順を入れ替える(倒置する)ことができます。 これも、より文語的でフォーマルな響きになります。
形: Were + 主語 + to + 動詞の原形 …
- Were the earth to stop spinning, all life would disappear.
(= If the earth were to stop spinning, all life would disappear.)
(もし仮に地球が自転を止めるようなことがあったとしたら、全ての生命は消滅するだろう。)
- Were I to have another chance, I would do things differently.
(= If I were to have another chance, I would do things differently.)
(もし仮に私にもう一度チャンスがあるようなら、私は違うやり方をするだろう。)
- Were he to propose to her, she would surely accept.
(= If he were to propose to her, she would surely accept.)
(もし仮に彼が彼女にプロポーズするようなことがあったとしたら、彼女はきっと受け入れるだろう。)
文頭がいきなり Were で始まり、その後に “主語 + to不定詞” が続いていたら、仮定法未来の倒置の可能性が高いです。これもTOEICの文法問題などで見かけることがあるので、形に慣れておきましょう。
“If S were to…” の帰結節は、いつも would とか could とかの過去形なんですか?
はい、その通りです! “If S were to…” で仮定する内容は、非常に非現実的、あるいは純粋な想像に基づいていることが多いので、その結果として起こることも、現実から離れた仮定的なものになります。そのため、帰結節では will のような直接的な未来を表す助動詞ではなく、would, could, might といった仮定のニュアンスを持つ助動詞の過去形が使われるのが一般的です。
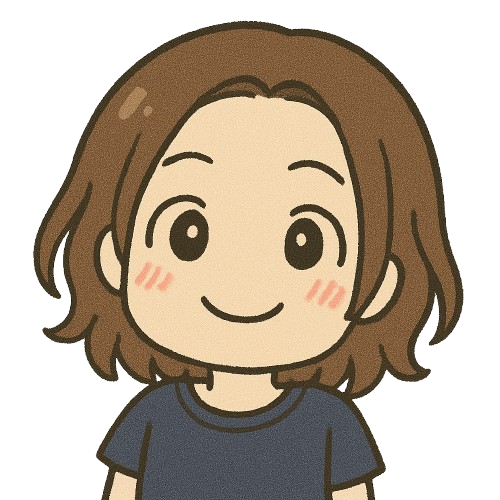
“were to” は、”should” よりもっとありえない感じなんだね!太陽が西から昇るとか!倒置の形も、慣れるまで練習が必要そうだなぁ。
仮定法未来を使いこなすためのポイントと注意点
仮定法未来 “If S should…” と “If S were to…” の基本的な形とニュアンスが理解できたところで、これらをより効果的に使いこなし、また誤解を避けるためのポイントや注意点を見ていきましょう。
“should” と “were to” のニュアンスの違いを意識する
すでにお話ししてきた通り、仮定法未来の “should” と “were to” は、どちらも実現可能性の低い未来を仮定しますが、その度合いやニュアンスには違いがあります。
おさらい:
| If S should + 原形 | If S were to + 原形 | |
|---|---|---|
| 実現可能性 | 低いが、ゼロではない。「万が一」 | 極めて低い、ほぼゼロ。「まずありえないが、仮に」 |
| 話し手の気持ち | 「起こらないとは思うが、もしものために」「ひょっとしたら」 | 「まずありえないだろうけど、想像してみると」「もしそんな非現実的なことが起きたら」 |
| 帰結節の助動詞 | 未来形 (willなど)、過去形 (wouldなど)、命令文 | 主に過去形 (would, could, might) |
| 主語の意志 | 関わることもあり得る (例: If you should change your mind) | 関わらないことが多い (例: If war were to break out) |
どちらを使うべきか迷ったら、自分がその未来の出来事に対して、どれくらいの実現可能性を感じているか、どんな気持ちで仮定しているかを考えてみると良いでしょう。「絶対ないとは言えないけど、まあ万が一だよね」くらいなら “should”、「いやいや、それはさすがにないでしょ、あくまで仮の話だけど」という感じなら “were to” を選ぶ、というような使い分けです。
ただし、実際の会話では、この区別がそれほど厳密でないこともあります。特に “should” は、比較的広い範囲の「万が一」を表すのに便利に使われます。
帰結節 (主節) の助動詞の選び方 – 現実味で判断
仮定法未来の if節に対する帰結節(主節)で使われる助動詞は、仮定している内容の現実味や、話し手が伝えたいニュアンスによって変わってきます。
“If S should…” の場合:
- will / shall + 原形: もし万が一~が起きたら、実際に~するだろう/~になるだろう (比較的現実的な結果)
例: If it should rain heavily, the river will flood. (もし万が一雨がひどく降れば、川は氾濫するだろう。)
- would / should / could / might + 原形: もし万が一~が起きたら、~するだろう/~できるだろう/~かもしれない (より仮定的な、あるいは丁寧な結果・推量)
例: If you should need assistance, I could help you. (もし万が一援助が必要でしたら、お手伝いできますが。)
- 命令文: もし万が一~が起きたら、~しなさい (指示・依頼)
例: If anything should happen to me, call the police. (もし万が一私の身に何かあったら、警察を呼んでください。)
“If S were to…” の場合:
- would / could / might + 原形: もし仮に~が起きたとしたら、~するだろう/~できるだろう/~かもしれない (非現実的な仮定に対する、仮定的な結果・推量)
例: If I were to meet an alien, I would try to communicate with it. (もし仮に宇宙人に会うようなことがあったら、それとコミュニケーションを取ろうとするだろう。)
will は通常使われません。 なぜなら、if節の仮定が極めて非現実的なので、その結果も現実のものとして断定的に述べるのは不自然だからです。
帰結節の助動詞の選び方は、仮定法過去 (If S + 過去形, S + would/could/might + 原形) のルールと似ていますね。仮定の度合いが強ければ強いほど、帰結節も仮定的な助動詞(過去形)が使われやすくなる、と覚えておきましょう。
仮定法未来と通常の未来の条件文 (If S + 現在形) との違いを再確認
仮定法未来を正しく使うためには、それが「通常の未来の条件文」とどう違うのかを常に意識しておくことが大切です。
ポイントの再確認:
- 通常の未来の条件文 (If S + 現在形…, S + will/can/may… + 原形):
- 未来に起こる可能性が十分にあると話し手が考えていることを仮定する。
- 「もし~ならば、~だろう」という、比較的ストレートな条件と結果の関係。
- 例: If I have time tomorrow, I will visit you. (もし明日時間があれば、あなたを訪ねます。)
- 仮定法未来 (If S should/were to + 原形…, S + 助動詞(原形/過去形) + 原形):
- 未来に起こる可能性が低い、またはほぼあり得ないと話し手が考えていることを仮定する。
- 「万が一~ならば」「もし仮に~としたら」という、話し手の主観的な判断や気持ちが含まれる。
- 例: If I should have time tomorrow (which is unlikely), I would visit you. (もし万が一明日時間があるようなら(まあないと思うけど)、あなたを訪ねるのですが。)
- 例: If pigs were to fly, I would believe his story. (もし豚が空を飛ぶようなことがあったら、彼のお話を信じるでしょうに。)
「これは実現可能なことかな? それとも、まずないだろうな、という気持ちで言っているのかな?」と、話し手の心の状態を想像することが、使い分けの鍵になります。
否定の仮定法未来 – “If S should not…” / “If S were not to…”
仮定法未来も、もちろん否定の形で使うことができます。「もし万が一~しないならば」「もし仮に~しないとしたら」というように、起こらないことを仮定するわけですね。
- If it should not rain tomorrow, we will have a barbecue.
(もし万が一明日雨が降らないようなら、私たちはバーベキューをするでしょう。)
- If he were not to come to the party, she would be disappointed.
(もし仮に彼がパーティーに来ないとしたら、彼女はがっかりするだろう。)
if の省略による倒置の形では、not は主語の後ろに置かれます。
- Should it not rain tomorrow, …
- Were he not to come to the party, …
ただし、否定の仮定法未来は、肯定の形に比べて使われる頻度はやや低いかもしれません。多くの場合、「もし~なら」と肯定的に仮定し、帰結節で否定的な結果を述べる方が自然なことが多いからです。
仮定法は、現在・過去・未来と、時制の組み合わせが複雑に見えますが、それぞれの形が持つ「現実との距離感」や「話し手の気持ち」を掴むことができれば、決して難しいものではありません。一つひとつ丁寧に理解していきましょう!
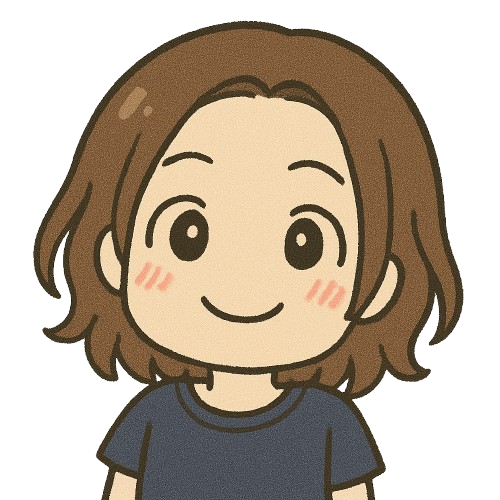
should と were to の違い、やっと整理できた気がする!帰結節の助動詞も大事なんだね。普通の if との違いも、もう一度復習しなきゃ!
まとめ – 仮定法未来を使いこなし、よりニュアンス豊かな英語表現へ!
今回は、「万が一」や「まずありえない未来」を仮定する「仮定法未来」について、その代表的な形である “If S should…” と “If S were to…” を中心に、基本的な考え方から使い方、ニュアンスの違い、そして注意点まで、詳しく見てきました。これで、今まで少し遠い存在に感じていた仮定法未来が、グッと身近なものになったのではないでしょうか。
最後に、この記事で学んだ仮定法未来の重要なポイントをまとめておきましょう。
- 仮定法未来とは:
- 未来に起こる可能性が低い、またはほぼあり得ないと話し手が考えることを仮定する表現。
- 話し手の主観的な判断や気持ち(「万が一」「まずないだろうが」)が含まれる。
- 主な形とニュアンス:
- If + 主語 + should + 動詞の原形 …:
- 「もし万が一~するようなことがあれば」
- 実現可能性は低いがゼロではない。
- 帰結節は、will, would, 命令文など様々。
- 丁寧な依頼・提案 (If you should…) でよく使われる。
- If省略で Should + S + 原形… の倒置形あり。
- If + 主語 + were to + 動詞の原形 …:
- 「もし仮に~するようなことがあったとしたら(まずないだろうが)」
- 実現可能性は極めて低い、ほぼゼロ。
- 帰結節は、主に would, could, might などの助動詞の過去形。
- 主語の意志と無関係な出来事を仮定することが多い。
- If省略で Were + S + to + 原形… の倒置形あり。
- If + 主語 + should + 動詞の原形 …:
- 通常の未来の条件文との違い:
- 通常の条件文 (If S + 現在形…) は、実現可能な未来を仮定する。
- 仮定法未来は、実現可能性が低い未来を仮定し、話し手の気持ちが込められる。
仮定法未来は、単に未来の出来事を述べるのではなく、そこに話し手の「現実との距離感」や「丁寧さ」「控えめな気持ち」といったニュアンスを乗せることができる、非常に洗練された表現方法です。これを使いこなせるようになれば、あなたの英語はより細やかで、より相手に配慮した、深みのあるものになるでしょう。
最初は、”should” と “were to” の使い分けや、帰結節の助動詞の選び方に戸惑うかもしれません。でも、それぞれの形が持つ「話し手の気持ち」を想像しながら、たくさんの例文に触れ、そして自分でも使ってみることで、必ずその感覚が掴めてきます。特に、if が省略された倒置の形は、書き言葉やフォーマルなスピーチなどで見かけると「おっ」と思わせる、知的な印象を与える表現ですよ。
この記事が、皆さんの英語学習の旅において、仮定法未来という新たな扉を開くための一助となれば、これ以上嬉しいことはありません。楽しみながら、英語の奥深さを味わっていってくださいね!

仮定法未来、なんだか使えるとかっこいいかも!should と were to の使い分け、練習してみます!

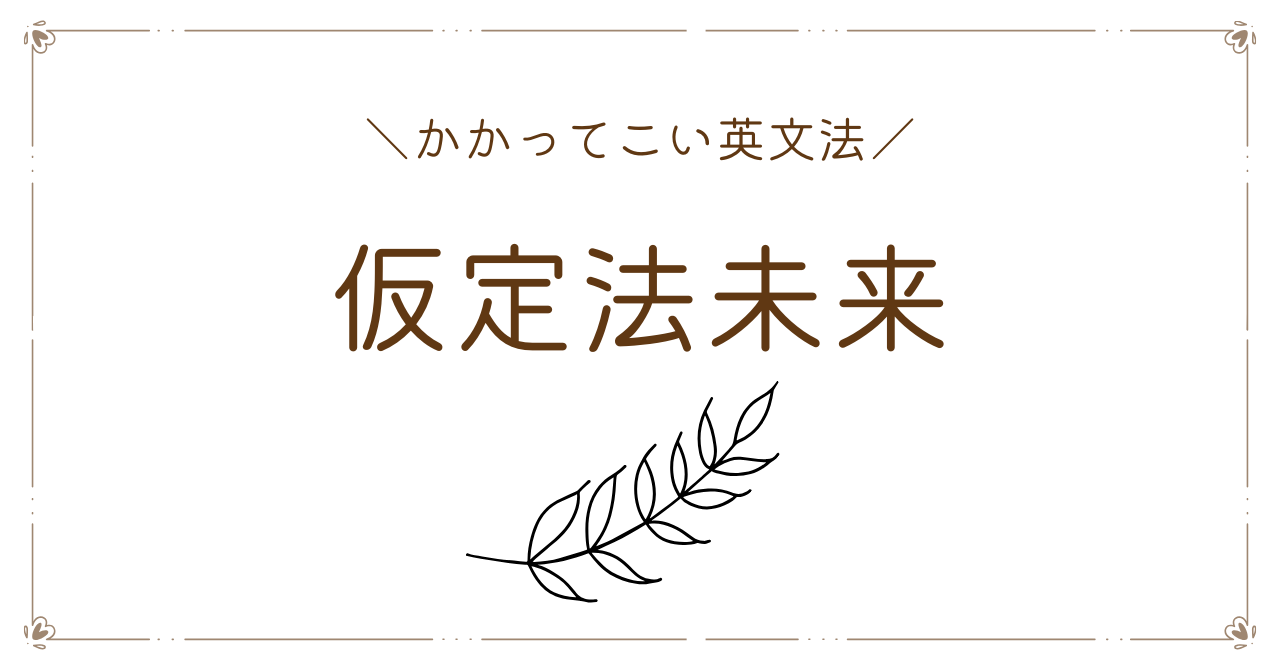
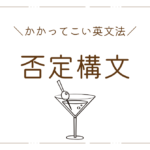
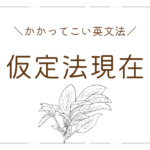
コメント