英語の文章を読んでいると、「and」や「or」、「but」といった接続詞で結ばれた部分で、なんだか言葉が省略されているように感じること、ありませんか?「前の部分と同じだから言わなくてもわかるでしょ?」と言わんばかりに、主語や動詞、目的語などが繰り返されずにスッキリしている…。これらは英語の「共通構文」と呼ばれるテクニックが使われているサインかもしれません。英語学習を始めたばかりの方や、中学生、高校生、そして大学受験やTOEICでより自然で効率的な英文読解・作成を目指す皆さんにとって、この共通構文を理解することは、文の構造を正確に把握し、スマートな英語表現を身につける上でとても大切なんです。
「共通構文って何?」「何がどう省略されるの?」「自分で使うときのルールは?」そんな疑問や不安を感じている方もいるかもしれませんね。でも大丈夫!この記事では、そんな皆さんのために、共通構文がどんな仕組みで成り立っているのか、どんな言葉が共通で省略されやすいのか、そして共通構文を見抜き、使いこなすためのポイントを、具体的な例文をたくさん見ながら、一つひとつ丁寧に解説していきます。この記事を読み終わる頃には、きっと共通構文の魅力に気づき、英語の理解力も表現力もワンランクアップしているはずですよ!

共通構文って、なんだか賢そう!これでスッキリわかるかな?
共通構文の基本 – なぜ言葉を「共通化」して省略するの?
まずは、共通構文とは一体何なのか、そしてなぜ言葉を共通化して省略するのか、その基本的な考え方から見ていきましょう。「繰り返しを避けてスッキリさせる」というのが大きな目的です。
共通構文とは? – 接続詞で結ばれた文の共通部分を省略するルール
共通構文(きょうつうこうぶん、Shared construction / Ellipsis in coordination)とは、主に等位接続詞(and, or, but など)で結ばれた二つ以上の文(または句や節)において、それらに共通する語句(主語、動詞、目的語、修飾語など)の繰り返しを避け、後の文(または句や節)でその共通部分を省略する表現方法のことです。
簡単に言うと、「同じことは二度言わないよ!」という、英語の効率的なコミュニケーション術の一つですね。省略されることで、文が簡潔になり、リズムも良くなります。
例えば、
- Tom likes apples, and Mary likes apples too. (トムはリンゴが好きで、メアリーもリンゴが好きだ。)
→ この文の “likes apples” は共通していますね。これを共通構文にすると…
- Tom likes apples, and Mary does too. (トムはリンゴが好きで、メアリーもそうだ。)
→ “likes apples” が代動詞 “does” で置き換えられ、さらに省略も可能です。
または、主語が共通なら…
- He can play the guitar, and (he can) play the piano. (彼はギターが弾けるし、ピアノも弾ける。)
→ “He can” が共通なので、後の部分で省略できます。結果として “He can play the guitar and the piano.” のようになります。
このように、共通する部分をうまく省略することで、文が引き締まり、より自然で洗練された印象になるんです。
共通化・省略の目的 – 文の簡潔化とリズム感の向上
共通構文が使われる主な目的は、以下の通りです。
- 文の簡潔化・効率化: 同じ言葉の繰り返しを避けることで、文が不必要に長くなるのを防ぎ、情報をより簡潔に伝えることができます。
- リズム感とテンポの向上: 特に会話において、冗長な繰り返しをなくすことで、話のテンポが良くなり、聞き手も理解しやすくなります。
- 強調効果: 共通でない部分、つまり対比されたり新しく付け加えられたりする情報が、かえって際立つことがあります。
- 自然な英語表現: ネイティブスピーカーは、無意識のうちに共通構文を多用しています。これを理解し使えるようになると、より自然な英語に近づけます。
共通構文は、単なる省略テクニックではなく、英語の「経済性の原則」(できるだけ少ない言葉で効果的に伝える)を反映した、賢い表現方法と言えるでしょう。
共通で省略されやすい要素 – 主語、動詞、目的語、修飾語など
では、具体的にどんな言葉が共通部分として省略されやすいのでしょうか? 文の様々な要素が対象となります。
- 共通の主語:
例: She sings and (she) dances very well. → She sings and dances very well.
- 共通の動詞 (または助動詞 + 動詞):
例: Some people like summer, and others (like) winter. → Some people like summer, and others winter.
- 共通の目的語:
例: He bought a book, and I borrowed (a book / it). → He bought a book, and I borrowed it. (代名詞で受ける)
- 共通の補語:
例: The weather was fine, and the sky (was) blue. → The weather was fine, and the sky blue.
- 共通の修飾語 (副詞句など):
例: We went to the park in the morning, and (we went) to the museum in the afternoon.
→ We went to the park in the morning and to the museum in the afternoon.
- 共通の前置詞:
例: He is interested in and good at sports. (彼はスポーツに興味があり、得意だ。)→ “is interested in sports and is good at sports” の共通部分を整理した形。これは少し高度な例です。
共通構文では、省略された部分を補って理解することが大切です。最初は少し難しく感じるかもしれませんが、パズルのように考えると面白いですよ!

へぇ~、同じことは繰り返さないって、英語も効率的なんだね!色々なものが省略できるんだなぁ。
共通構文の主なパターンと作り方・見抜き方
それでは、実際にどのような形で共通構文が使われるのか、主なパターンと、それらの作り方や見抜き方のポイントを詳しく見ていきましょう。等位接続詞 (and, or, but) が鍵になります。
等位接続詞 (and, or, but) で結ばれる文の共通要素の省略
共通構文の最も基本的な形は、等位接続詞 (and, or, but) で二つ以上の文や句が結ばれるときに、共通する要素を省略するものです。
1. 共通の主語の省略
二つ(以上)の述語動詞が同じ主語を持つ場合、後の述語動詞の主語は通常省略されます。つまり、S + V1 and V2 (and V3…) の形になります。
- She got up early and (she) prepared breakfast.
→ She got up early and prepared breakfast. (彼女は早起きして朝食の準備をした。)
- He studied hard, (he) passed the exam, and (he) entered the university.
→ He studied hard, passed the exam, and entered the university. (彼は一生懸命勉強し、試験に合格し、大学に入学した。)
- You can stay here or (you can) go home.
→ You can stay here or go home. (ここにいてもいいし、家に帰ってもいいですよ。)
作り方・見抜き方:
- 複数の動詞(句)が等位接続詞で結ばれていて、それらの動作主が同じであれば、最初の動詞の前に主語を置き、後は動詞(句)だけを続けます。
- 動詞が並んでいるのを見たら、「これらの動詞の主語は何かな?」と最初の動詞の主語を探してみましょう。
2. 共通の動詞(句)の省略
主語が異なるが、述語動詞(句)が共通している場合、後の文の動詞(句)が省略されることがあります。その際、代動詞 (do, does, did) や助動詞が残ることが多いです。
- My sister likes pop music, and I do, too.
(私の姉はポップミュージックが好きで、私も好きです。)
(= … and I like pop music, too.)
- John can speak French, but Mary can’t.
(ジョンはフランス語を話せるが、メアリーは話せない。)
(= … but Mary can’t speak French.)
- Some people prefer tea, and others (prefer) coffee.
(お茶を好む人もいれば、コーヒーを好む人もいる。)
→ このように、代動詞すら省略されることもあります。特に、対比が明確な場合。
作り方・見抜き方:
- 共通の動詞(句)を繰り返さず、代動詞や助動詞で受けるか、文脈で明らかならそれすら省略します。
- “S1 + V …, and S2 (do/aux.), too.” や “S1 + V …, but S2 (don’t/aux. not).” のような形を見たら、省略を疑いましょう。
3. 共通の目的語・補語の省略
目的語や補語が共通している場合も、後の文では省略されたり、代名詞で置き換えられたりします。
- He wrote a letter, and she read it.
(彼は手紙を書き、彼女はそれを読んだ。)
(= … and she read the letter.) ← a letter を it で受けています。完全な省略ではありませんが、共通の対象を指しています。
- The teacher praised John, and (the teacher praised) Mary as well.
→ The teacher praised John, and Mary as well. (先生はジョンを褒め、メアリーも同様に褒めた。)
→ この場合、”praised” という動詞と、間接的に「褒めるという行為の対象」という点が共通しています。
- The soup is hot, and the bread (is) fresh.
(スープは熱く、パンは新鮮だ。)
→ 共通のbe動詞が省略されています。
作り方・見抜き方:
- 共通の目的語や補語は、代名詞で受けるか、文脈上明らかであれば省略します。
- “S1 + V1 + O, and S2 + V2 (it/them).” や “S1 is C1, and S2 (is) C2.” のような形に注意しましょう。
等位接続詞で結ばれる共通構文は、文をスッキリさせるための基本的なテクニックです。特に、主語や動詞の省略は頻繁に使われますよ。
比較構文における共通要素の省略
比較の文(AはBより~だ、AはBと同じくらい~だ、など)では、比較される二者の間で共通している部分は、後の部分で省略されるのが一般的です。これは、共通構文の一種と考えることができます。
- She is taller than her sister (is tall).
→ She is taller than her sister. (彼女は姉より背が高い。)
- My car is not as expensive as yours (is expensive).
→ My car is not as expensive as yours. (私の車はあなたのほど高くない。)
- He works harder than I (work hard / do).
→ He works harder than I. / He works harder than I do. (彼は私より熱心に働く。)
- This computer is better than that one (is good).
→ This computer is better than that one. (このコンピュータはあれより良い。)
作り方・見抜き方:
- 比較の対象となる二つの事柄で、共通する述語部分は省略します。
- “than S” や “as S” の後に、動詞や補語が省略されている可能性を常に考えましょう。省略されている部分を補って考えると、文の構造が理解しやすくなります。
比較構文の省略は、特に “than” の後でよく起こります。省略された形に慣れていないと、文末が代名詞だけで終わっているように見えて戸惑うことがあるので注意しましょう。
to不定詞の共通要素の省略 (toの代不定詞)
複数の to不定詞が等位接続詞で結ばれる場合や、文脈から明らかな場合、to不定詞の後の動詞の原形 (およびそれに続く目的語など) が共通であれば、後の to不定詞では to だけを残して他を省略することがあります。これを「代不定詞」と呼び、共通構文の一例です。
- I want to sing and (I want to) dance.
→ I want to sing and dance. (私は歌って踊りたい。)
→ この場合、”I want” も共通なので、”to sing and to dance” の to も一つにまとめられることが多いです。
- She decided to go to the party, but her friend decided not to.
(彼女はパーティーに行くことにしたが、彼女の友達は行かないことにした。)
(= … but her friend decided not to go to the party.)
- A: Are you going to study abroad? (留学するつもりですか?)
B: I hope to. (そうしたいと思っています。)
(= I hope to study abroad.)
- You can use my pen if you want to. (もし使いたければ、私のペンを使っていいですよ。)
作り方・見抜き方:
- 共通する動詞の原形以下を省略し、to だけを残します。
- 文末や接続詞の後に to だけがポツンと置かれていたら、代不定詞の可能性が高いです。前に出てきた to不定詞の内容を補って考えましょう。
関係詞節における共通要素の省略 (先行詞の共通)
一つの先行詞に対して、複数の関係詞節が等位接続詞で結ばれて修飾する場合、後の関係詞節では、共通の先行詞を指す関係代名詞 (と場合によってはbe動詞) が省略されることがあります。
- This is the book that I bought yesterday and (that/which) I found very interesting.
→ This is the book that I bought yesterday and found very interesting.
(これは私が昨日買って、とても面白いと思った本です。)
→ 二つの関係詞節 (that I bought yesterday と that/which I found very interesting) が共通の先行詞 the book を修飾しています。後の関係詞節では、関係代名詞 that/which と主語 I が共通でないため、この場合は関係代名詞は省略できませんが、動詞句が続く場合は主語が省略されることもあります。より正確には、この例では動詞が並列されていると捉える方が自然かもしれません。
より典型的な例は以下のようなものです。
- The man who lives next door and (who) works at the bank is Mr. Smith.
→ The man who lives next door and works at the bank is Mr. Smith.
(隣に住んでいて銀行で働いている男性はスミスさんです。)
→ who lives next door と who works at the bank が the man を修飾。後の who が省略されています。
作り方・見抜き方:
- 共通の先行詞を修飾する複数の関係詞節を and などで繋ぐ場合、後の関係詞節の冒頭の関係代名詞 (や主語) を省略できることがあります。
- 名詞の後に、関係詞節と、さらに and などで繋がれた動詞句が続いている場合、共通の先行詞と関係代名詞の省略を疑ってみましょう。
共通構文は、文の構造をスッキリ見せるためのテクニックですが、省略されている部分を正確に補えないと、意味を取り違える可能性もあります。慣れるまでは、丁寧に文の要素を分析することが大切ですね。

and とか or で繋がってるとき、同じ言葉は言わないんだね!to不定詞の to だけ残るやつ、よく見るかも!
共通構文を読み解き、使いこなすためのコツと注意点
共通構文は、英語をより自然で簡潔にするための強力なツールですが、正しく理解し、使いこなすためにはいくつかのコツと注意点があります。これらを意識することで、あなたの英語力はさらに向上するでしょう。
省略されている部分を正確に補って理解する
共通構文に出会ったときに最も重要なのは、「何が省略されているのか」を正確に特定し、それを補って文全体の意味を理解することです。省略されている部分が曖昧なまま読み進めてしまうと、誤解が生じたり、文の論理的なつながりが見えなくなったりすることがあります。
練習方法:
- 共通構文と思われる箇所を見つけたら、まずは接続詞 (and, or, but など) や比較の表現 (than, as … as など) に注目する。
- 接続詞の前後の文(または句)で、形や意味が対応している部分を探す。
- 後の文(または句)で省略されていそうな共通要素(主語、動詞、目的語など)を、前の部分から見つけ出し、補ってみる。
- 補った状態で文全体の意味が自然に通じるか確認する。
例えば、”He can play tennis and she soccer.” という文を見たら、
1. and に注目。
2. 前は “He can play tennis”、後ろは “she soccer”。
3. 後ろの文で動詞が省略されていそう。”soccer” は目的語なので、前の文の動詞 “can play” が共通で省略されたと推測できる。
4. 補うと “He can play tennis, and she can play soccer.” となり、意味が通じる。
と、こんな風に段階的に考えていくと、複雑な共通構文も怖くありません。
共通構文を作る際の注意点 – 曖昧さを避ける
自分で共通構文を使って文を作るときには、省略した結果、文の意味が曖昧になったり、誤解を招いたりしないように注意する必要があります。
- 省略しても意味が明確に伝わるか:
省略する共通要素は、文脈から容易に推測できるものでなければなりません。聞き手や読み手が補えないような重要な情報を省略してしまうと、コミュニケーションが成り立ちません。
- 文法的に正しい省略か:
共通構文の省略には、ある程度のパターンやルールがあります。何でもかんでも省略していいわけではありません。例えば、主語と動詞の種類が異なるのに無理やり共通化しようとすると、非文法的な文になってしまいます。
例: × I like apples and she oranges. (私はリンゴが好きで、彼女はオレンジ。)
→ この場合、動詞が共通でないので、”I like apples, and she likes oranges.” とするか、”I like apples and she (likes) oranges, too.” のように、動詞を残すか代動詞を使う必要があります。
- 並列される要素の形を揃える (平行構造/パラレリズム):
等位接続詞で結ばれる要素は、文法的に同じ形(名詞と名詞、動詞句と動詞句、節と節など)であることが望ましいです。これを平行構造(パラレリズム)と言います。共通構文を作る際も、この平行構造を意識すると、より自然で分かりやすい文になります。
例: She enjoys reading books and watching movies. (動名詞句の並列)
(× She enjoys reading books and to watch movies. ← 形が不揃い)
共通構文は文を簡潔にしますが、分かりやすさを犠牲にしてはいけません。迷ったら、無理に省略せずに、丁寧に書く(話す)ことを心がけましょう。
共通構文と他の省略・倒置との関連性
共通構文は、英語における様々な「省略」のテクニックの一つであり、場合によっては「倒置」とも関連してくることがあります。
- 一般的な省略との違い:
共通構文は、主に等位接続詞で結ばれた複数の要素間で、共通する部分を省略するものです。一方、接続詞の後の「主語+be動詞」の省略や、関係詞の省略などは、また別のルールに基づいています。(詳しくは「省略構文」の記事を参照してくださいね!)
- 倒置との関連:
例えば、”Not only did he study hard, but he also exercised every day.” (彼は一生懸命勉強しただけでなく、毎日運動もした。) のように、Not only が文頭に来て倒置が起こり、かつ but also 以下で共通の主語 he が省略される(正確には he が繰り返される)というように、倒置と共通構文が組み合わさることもあります。
これらの文法現象は、それぞれ独立しているわけではなく、英語をより効果的に、そして表現豊かにするための道具として、互いに関連し合っていると考えると、理解が深まるでしょう。
TOEICや英検などの試験における共通構文のポイント
TOEIC L&Rテストや英検などの英語資格試験では、共通構文は以下のような点で重要になります。
- 長文読解:
- 共通構文によって省略されている部分を正しく補って理解できるかが、速読力と精読力に繋がります。特に、長い修飾語句がついている場合や、複数の要素が並列されている場合に、文の骨格を見抜く力が試されます。
- and, or, but の前後で、何と何が対応しているのか(何が共通で何が対比されているのか)を正確に把握することが、文全体の論理関係を理解する鍵となります。
- 文法問題 (Part 5など):
- 代動詞 (do/does/did) や助動詞の正しい形を選ぶ問題。
- to不定詞の後の動詞の省略 (toの代不定詞) を理解しているかを問う問題。
- 平行構造(パラレリズム)が保たれているか、接続詞の使い方が適切かなどを判断させる問題。
- 比較構文での省略に関連する問題。
- リスニング:
- 会話では、共通部分の省略が頻繁に起こります。省略された形に慣れていないと、話の展開についていけなくなることがあります。特に、短い応答 (“Yes, I do.” “Me, too.” “Neither do I.” など) は共通構文の宝庫です。
試験対策としては、普段から共通構文が使われている英文に多く触れ、省略されている部分を意識しながら読む練習をすることが効果的です。また、基本的な文型や品詞の働きをしっかり理解しておくことが、共通構文攻略の土台となりますよ。
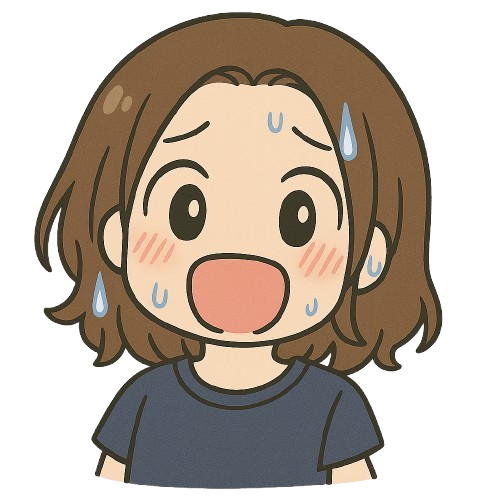
曖昧にならないように気をつけるの、大事だね…。試験でも読解で役立ちそう!
まとめ – 共通構文をマスターして、英語の達人への道を切り開こう!
今回は、英語の文をスッキリと、そして効率的に繋ぐ「共通構文」について、その基本的な考え方から具体的なパターン、見抜き方、そして使いこなすためのコツまで、詳しく見てきました。これで、今まで「なんだかよくわからない…」と感じていた共通構文が、グッと身近なものになったのではないでしょうか。
最後に、この記事で学んだ共通構文の重要なポイントをまとめておきましょう。
- 共通構文とは:
- 主に等位接続詞 (and, or, but) で結ばれた文や句において、共通する語句の繰り返しを避け、後の部分で省略する表現方法。
- 目的は、文の簡潔化、リズム感の向上、強調効果など。
- 主な省略パターン:
- 共通の主語の省略 (例: She sings and dances.)
- 共通の動詞(句)の省略 (例: I like tea, and he does, too.)
- 共通の目的語・補語の省略 (または代名詞化)
- 比較構文での共通部分の省略 (例: taller than I am.)
- to不定詞の後の動詞の原形の省略 (例: I want to.)
- 関係詞節における共通の先行詞や関係代名詞の省略 (例: the man who … and works …)
- 理解と活用のコツ:
- 省略されている部分を正確に補って理解する練習をする。
- 自分で使うときは、曖昧さを避け、平行構造を意識する。
- たくさんの英文に触れて、共通構文の使われ方に慣れる。
共通構文は、英語の「言わなくてもわかることは繰り返さない」という合理的な精神を反映した、非常に洗練された表現テクニックです。この構文を理解し、自分でも使いこなせるようになれば、あなたの英語はよりネイティブスピーカーのそれに近づき、コミュニケーションの効率も格段に上がるでしょう。
最初は、省略された部分を見つけるのに苦労するかもしれません。でも、諦めずに、一つひとつの文と丁寧に向き合っていけば、必ずそのパターンが見えてきます。 そして、共通構文の便利さ、美しさに気づくはずです。英語学習の旅は長いですが、このような発見を積み重ねていくことが、上達への何よりの近道ですよ。
この記事が、皆さんの英語力向上の一助となれば、これ以上嬉しいことはありません。頑張ってくださいね!

共通構文、スッキリ理解できた!これで英文読むのも書くのも、もっと楽しくなりそう!

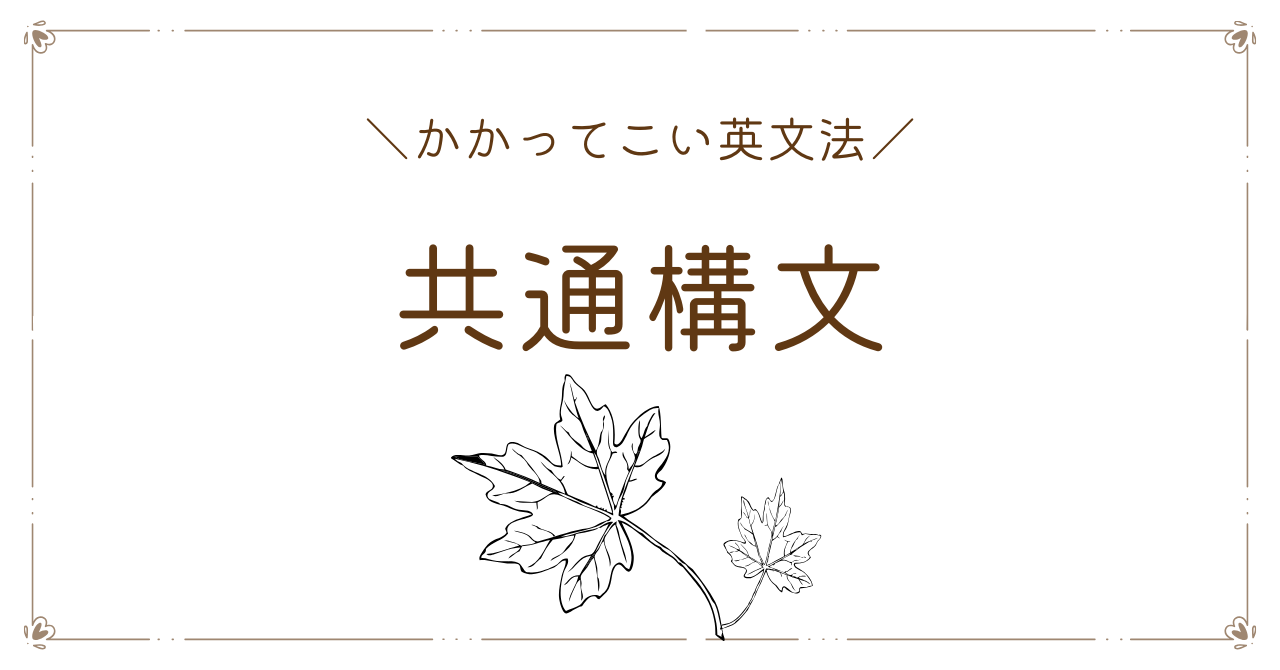
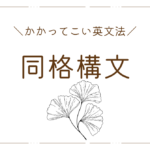
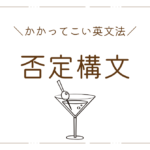
コメント