「時制の一致」って、なんだか聞くだけで難しそう…って感じちゃいますよね。「彼が言ったのは過去だから、彼が言った内容も全部過去形にしなきゃいけないの?」とか、「え、でもこれって今も本当のことなのに、過去形にしちゃっていいの?」なんて、疑問がたくさん出てくる英語学習のつまずきポイントの一つかもしれません。
でも大丈夫!この記事を読めば、そんな時制の一致のモヤモヤがスッキリ晴れますよ。今回は、英語の「時制の一致」というルールについて、基本的な考え方から、どんな時に動詞の形を変えるのか、そして「え、この場合は変えなくていいの?」という例外パターンまで、たくさんの例文を交えながら、とことん分かりやすく解説していきます。これをマスターすれば、英会話や英文読解がもっとスムーズになること間違いなしです!
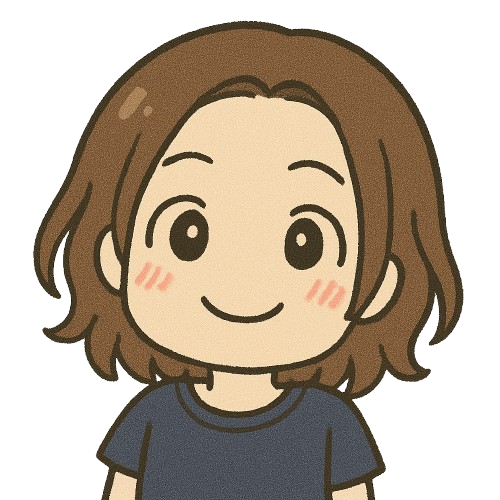
時制の一致、本当に苦手なんです…この記事で克服できるといいな!
時制の一致とは?まずは基本ルールをしっかり押さえよう!
英語を話したり書いたりするとき、時間を正しく表現するのはとっても大切ですよね。その中でも「時制の一致」は、特に間接話法(誰かが言ったことや思ったことを伝える言い方)で重要になってくるルールなんです。まずは、このルールがどうして必要なのか、そして基本的な形はどうなっているのかを、じっくり見ていきましょう。
なぜ「時制の一致」が必要なの?その理由と目的を理解しよう
そもそも、なぜ「時制の一致」なんていうルールがあるんでしょうか?それは、話の「基準となる時」をはっきりさせて、聞き手や読み手が時間の流れをスムーズに理解できるようにするためなんです。
例えば、「彼が昨日言ったこと」を誰かに伝える場面を想像してみてください。彼が言った「内容」は、彼が言った「時点」での話ですよね。もし、彼が言った内容をそのまま現在の時制で伝えてしまうと、聞き手は「あれ?それって今の話?それとも彼が言った時の話?」と混乱してしまうかもしれません。
そこで、主となる文(主節と言います)の動詞が過去形(例:彼が言った)のとき、それに続く内容を表す文(従属節と言います)の動詞も、主節の過去の時点に合わせて形を変える、というのが「時制の一致」の基本的な考え方なんです。これによって、「ああ、これは過去のある時点でそうだった話なんだな」と、時間の基準が明確になるんですね。
簡単に言うと、主節の動詞が過去形だったら、従属節の動詞もそれに合わせて過去っぽくする、ということです。ただし、何でもかんでも過去形にすればいいわけではないので、そこが少しややこしいところでもあります。
主節と従属節って何?時制の一致が起こる条件を確認!
「時制の一致」を理解する上で欠かせないのが、「主節(しゅせつ)」と「従属節(じゅうぞくせつ)」という言葉です。ちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、大丈夫ですよ!
- 主節:文のメインとなる部分。「SがVする」という骨組みです。
- 従属節:主節の内容を詳しく説明したり、補足したりする部分。主節にくっついているイメージです。特に “that” で導かれる名詞節(~ということ、という内容を表す節)で時制の一致がよく起こります。
例: He said that he was tired.
(彼は疲れていると言った。)
この文では、
- “He said” (彼は言った) が主節です。
- “that he was tired” (彼が疲れているということ) が従属節(that節)です。
そして、時制の一致が起こる主な条件は、主節の動詞が「過去形」のときです。主節の動詞が現在形や未来形の場合は、基本的に従属節の動詞は内容に合わせて自由に時制を選べます。ここ、とっても大事なポイントですよ!
例:
- He says that he is busy. (彼は忙しいと言っている。 主節が現在形 → 従属節も現在形)
- He says that he was busy yesterday. (彼は昨日忙しかったと言っている。 主節が現在形 → 従属節は内容に合わせて過去形)
- He will say that he is busy. (彼は忙しいと言うだろう。 主節が未来形 → 従属節は現在形)
このように、主節が現在形や未来形の場合は、従属節の時制は比較的自由です。問題は、主節が過去形の場合なんですね。
基本パターン1:主節が過去形 → 従属節も「過去形」にシフト!
これが時制の一致の最も基本的なパターンです。主節の動詞が過去形で、従属節の内容が主節の時と同じか、それより後の未来を表す場合(ただし過去から見た未来)、従属節の動詞は過去形になります。
直接話法(” ” を使ったセリフ)と間接話法(that節で伝える形)で比べてみると分かりやすいですよ。
<直接話法と間接話法の時制変化の例>
| 直接話法 (Direct Speech) | 間接話法 (Indirect Speech) – 時制の一致後 | 日本語訳(間接話法) |
|---|---|---|
| He said, “I am busy.” | He said that he was busy. | 彼は忙しいと言った。 |
| She said, “I study English every day.” | She said that she studied English every day. | 彼女は毎日英語を勉強すると言った。 |
| They said, “We will go to the park.” | They said that they would go to the park. | 彼らは公園へ行くだろうと言った。 |
上の表を見てください。直接話法で現在形 (am, study) だったものは、間接話法では過去形 (was, studied) に変わっていますね。また、未来を表す “will go” は “would go” になっています。これが時制の一致の基本です。
要注意! ここで言う「過去形」は、動詞の形が過去になるという意味で、必ずしも「過去の出来事」だけを指すわけではありません。例えば、”will” が “would” になるのは、過去から見た未来を表すためです。
基本パターン2:主節が過去形 → 従属節は「過去完了形」にシフト!(主節より前の時)
次に、従属節の内容が、主節の動詞が表す時よりも「さらに過去」である場合です。このときは、従属節の動詞は過去完了形 (had + 過去分詞) になります。
これも直接話法と間接話法で比べてみましょう。
<直接話法と間接話法の時制変化の例(従属節がより過去の場合)>
| 直接話法 (Direct Speech) | 間接話法 (Indirect Speech) – 時制の一致後 | 日本語訳(間接話法) |
|---|---|---|
| He said, “I saw her yesterday.” | He said that he had seen her the day before. | 彼はその前の日に彼女に会ったと言った。 |
| She said, “I have finished my homework.” | She said that she had finished her homework. | 彼女は宿題を終えてしまっていたと言った。 |
| They said, “We had already eaten lunch.” | They said that they had already eaten lunch. | 彼らは既に昼食を食べてしまっていたと言った。 (元々過去完了形ならそのまま過去完了形) |
直接話法で過去形 (saw) や現在完了形 (have finished) だったものが、間接話法では過去完了形 (had seen, had finished) になっていますね。これは、「彼が言った」時点よりも「彼女に会った」や「宿題を終えた」ことの方が時間的に前だからです。
基本パターン3:主節が過去形 → 従属節の「助動詞」も過去形にシフト!
従属節に助動詞 (will, can, may など) が含まれる場合、主節の動詞が過去形なら、これらの助動詞も過去形に変わります。これはパターン1の延長線上にあると考えられますね。
代表的な助動詞の変化は以下の通りです。
- will → would
- can → could
- may → might
- must → had to (「~しなければならなかった」という意味の場合。推量の場合は must のままのことも)
- shall → should (現代英語では shall の使用頻度が減っているので、will → would の方が一般的)
例文を見てみましょう。
- He said, “I will help you.” → He said that he would help me.
(彼は私を手伝うと言った。) - She said, “I can swim.” → She said that she could swim.
(彼女は泳げると言った。) - They said, “We may be late.” → They said that they might be late.
(彼らは遅れるかもしれないと言った。) - I thought, “He must study hard.” → I thought that he had to study hard. (義務)
(私は彼が一生懸命勉強しなければならないと思った。) - I thought, “He must be tired.” → I thought that he must be tired. (推量)
(私は彼が疲れているに違いないと思った。)※この場合は must のままも可能。
助動詞の中でも、should, ought to, had better, used to など、元々過去形のような形をしているものや、意味合いから変化しないものは、時制の一致を受けても形が変わりません。
ここまでが、時制の一致の基本的な3つのパターンです。まずはこの骨組みをしっかり頭に入れましょう!

なるほど、主節が過去だと、従属節も影響を受けるんですね。助動詞も変わるのか…!
時制の一致の例外!これを知ればもっとスッキリ、もう怖くない!
さて、基本ルールを学んだところで、「じゃあ、主節が過去形だったら、従属節は絶対に過去形か過去完了形にしなきゃいけないの?」と思うかもしれません。実は、そうではない場合もあるんです! これが「時制の一致の例外」と呼ばれるもので、これを知っていると、より自然で正確な英語表現ができるようになりますよ。
「例外」というと難しく感じるかもしれませんが、「わざわざ過去形にしなくても、意味が通じる、あるいはその方が自然な場合」と考えてみましょう。
例外1:不変の真理や一般的な事実・習慣は時制の一致を受けない!
これは最も代表的な例外の一つです。「太陽は東から昇る」とか「水は100度で沸騰する」といった、いつの時代でも変わらない普遍的な事実や科学的な真理は、主節の動詞が過去形であっても、従属節は現在形のままなんです。
例文:
- Our teacher taught us that the earth goes around the sun.
(先生は私たちに、地球は太陽の周りを回っていると教えた。)
→ “went” にすると、「昔は回っていたけど今は違う」みたいに聞こえかねませんよね。 - He said that honesty is the best policy.
(彼は正直が最善の策だと言った。)
→ ことわざや格言も、普遍的な内容なので現在形のままです。 - She told me that she usually gets up at seven.
(彼女は普段7時に起きると私に言った。)
→ これは彼女の現在の習慣を表しています。もし「彼女が言った当時」の習慣を強調したいなら “got up” とすることもありますが、今も変わらない習慣なら現在形でOKです。
「不変の真理」や「一般的な事実」は、話している時点でも変わらず真実なので、わざわざ過去形にする必要がない、と考えると分かりやすいですね。
例外2:歴史上の事実は時制の一致を受けず、過去形のまま!
歴史上の出来事も、それが起こったのは明確に過去ですが、その事実自体は変わりませんよね。そのため、主節の動詞が過去形でも、歴史上の事実を述べる従属節は過去形のまま(過去完了形にしない)のが一般的です。
例文:
- We learned that Columbus discovered America in 1492.
(私たちはコロンブスが1492年にアメリカを発見したと学んだ。)
→ “had discovered” と過去完了形にしなくても、1492年という明確な過去の時点があるので、過去形で十分です。 - The history teacher said that World War II ended in 1945.
(歴史の先生は第二次世界大戦が1945年に終わったと言った。)
→これも “had ended” にする必要はありません。
歴史上の事実は、それが「いつ起こったか」という情報が重要であり、主節の過去の時点から見てさらに過去であることを強調する必要があまりないため、過去形のままが多いです。
例外3:主節の動詞が過去形でも、従属節の内容が「現在も変わらない事実」である場合
これが少し判断が難しいケースですが、主節の動詞が過去形でも、従属節で述べている内容が、話している「現在」においても真実である、あるいは変わらない状態である場合、従属節の動詞を現在形のままにすることがあります。
例文:
- Tom told me yesterday that his brother is a doctor.
(トムは昨日、彼の兄〔弟〕は医者だと私に言った。)
→ トムが言ったのは昨日ですが、彼のお兄さん(弟さん)が今も医者である可能性が高い場合、”is” のままにします。もし “was” にすると、「昔は医者だったけど、今は違う」というニュアンスを含むことがあります。 - I knew that she likes dogs.
(私は彼女が犬が好きだと知っていた。)
→ 私が知ったのは過去ですが、彼女が今も犬が好きであると話者が考えているなら “likes” のままです。 - He said that Tokyo is the capital of Japan.
(彼は東京が日本の首都だと言った。)
→ これは不変の真理にも近いですが、彼が言った時点でも、そして今も変わらない事実ですね。
このパターンの判断は、文脈や話者が何を伝えたいかによります。「彼が言った時点ではそうだったけど、今はどうか分からない」ということを明確にしたい場合は、時制の一致をさせて過去形 (was, liked など) を使います。どちらを使うかでニュアンスが変わってくるのが面白いところですね。
じゃあ、どっちを使えばいいか迷ったらどうすればいいの?
良い質問ですね!迷ったときは、原則通り時制の一致をさせて過去形(または過去完了形)にしておくのが無難ではあります。特に書き言葉やフォーマルな場面では、時制の一致をきっちり行う方が好まれる傾向があります。ただ、会話では、現在も変わらない事実を強調するために、あえて現在形を使うこともよくあります。文脈と伝えたいニュアンスを考えて使い分けるのが理想ですね。
例外4:仮定法が使われている従属節は時制の一致を受けない!
仮定法(「もし~だったら、~だろうに」のような現実とは異なることを述べる表現)は、それ自体が特別な時制のルールを持っています。そのため、仮定法が使われている従属節は、主節の時制の影響を受けず、仮定法独自の動詞の形を保ちます。
例文:
- She said, “If I were rich, I would travel around the world.” (直接話法:仮定法過去)
→ She said that if she were rich, she would travel around the world. (間接話法:were, would のまま)
(もしお金持ちだったら世界中を旅するのに、と彼女は言った。) - He said, “I wish I had studied harder.” (直接話法:I wish + 仮定法過去完了)
→ He said that he wished he had studied harder. (間接話法:had studied のまま)
(もっと一生懸命勉強していたらなあ、と彼は言った。)
仮定法の “were” や “would + 動詞の原形”、”had + 過去分詞” といった形は、時制の一致によって変化しない、と覚えておきましょう。これは仮定法自体のルールが優先されるからです。
[補足] must, need, should, ought to などの助動詞の扱い
基本パターン3で助動詞の変化を見ましたが、いくつかの助動詞は時制の一致に関して少し注意が必要です。
- must:
- 「~しなければならない」(義務)の意味なら had to に変わることが多いです。
例:He said, “I must go home.” → He said that he had to go home. - 「~に違いない」(強い推量)の意味なら must のままが多いです。
例:She said, “He must be tired.” → She said that he must be tired.
- 「~しなければならない」(義務)の意味なら had to に変わることが多いです。
- need not (~する必要はない): didn’t have to や wouldn’t have to になることが多いです。
例:He said, “You need not hurry.” → He said that I didn’t have to hurry. - should / ought to (~すべきだ): 基本的に形は変わりません。
例:The doctor said, “You should rest.” → The doctor said that I should rest.
これらの助動詞の扱いは、意味合いによって変わることがあるので、文脈で判断することが大切です。
ここまで、時制の一致の例外パターンを見てきました。「なんだ、意外と単純じゃないか!」と思えた部分もあれば、「うーん、やっぱりここは難しいな」と感じた部分もあるかもしれません。でも、これらのルールを知っているだけで、英語の理解度がぐっと深まりますよ。

例外って聞くと身構えちゃうけど、理由を知ると納得できるものも多いですね!「現在も変わらない事実」の判断は練習が必要そう…。
まとめ:時制の一致をマスターして、正確な英語表現を目指そう!
今回は、英語学習者にとって少し厄介な「時制の一致」について、基本ルールから例外まで、詳しく見てきました。最後に、今日学んだ大切なポイントをもう一度整理しておきましょう。
- 時制の一致とは?
主節の動詞が過去形のとき、従属節(特にthat節)の動詞も、主節の過去の時点に合わせて形を変えるルール。話の時間の基準を明確にするため。 - 基本パターン:
- 主節が過去形 → 従属節も過去形に (主節と同じか、それより後の時を表す場合)
- 主節が過去形 → 従属節は過去完了形 (had + 過去分詞) に (主節より前の時を表す場合)
- 主節が過去形 → 従属節の助動詞 (will, can, mayなど) も過去形 (would, could, mightなど) に
- 時制の一致の例外(従属節の時制が変わらない、または現在形になる場合):
- 不変の真理や一般的な事実・習慣 → 現在形のまま
- 歴史上の事実 → 過去形のまま(過去完了にしない)
- 従属節の内容が現在も変わらない事実 → 現在形のままにすることがある(話者の判断による)
- 仮定法が使われている従属節 → 仮定法独自の時制を保ち、変化しない
- 注意点:
- 主節の動詞が現在形や未来形の場合は、基本的に時制の一致は起こらない。
- 助動詞 must は意味によって変化の仕方が異なる。
- 迷ったら原則通り時制の一致をさせるのが無難な場合もあるが、ニュアンスを考えて使い分けるのが理想。
時制の一致は、最初はルールが多くて混乱するかもしれませんが、一つ一つのパターンを例文と一緒に丁寧に確認していくことで、必ず理解できるようになります。そして、実際に自分で英文を作ったり、会話で使ってみたりすることで、だんだんと自然に使いこなせるようになっていきますよ。
このルールをしっかり身につければ、あなたの英語はより正確で、相手にも誤解なく伝わるものになるはずです。映画のセリフや洋書の中で、登場人物が誰かの言葉を伝える場面に注目してみるのも、良い練習になりますね。ぜひ、楽しみながら時制の一致をマスターしていってください!

時制の一致、だいぶスッキリしました!これからは自信を持って使えそうです!ありがとうございました!


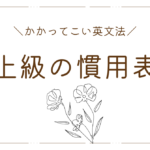
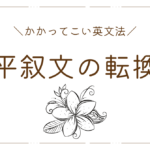
コメント