英語の助動詞「could」、皆さんはどんなイメージを持っていますか? 「canの過去形でしょ?」と思っている方も多いかもしれませんね。もちろんそれも正解なんですが、実はcouldにはもっとたくさんの顔があるんです! 丁寧にお願いする時、可能性を控えめに伝えたい時、そして「もし~だったらなぁ」と想像する仮定法…。couldを使いこなせると、英語の表現力がぐんと豊かになりますよ。
この記事では、そんな奥深い助動詞couldの様々な用法を、英語学習初心者の方や、改めて基礎を確認したい中高生、大学生、TOEIC受験者の方にもわかりやすく、徹底的に解説していきます。例文もたくさん用意したので、読み終わる頃には「なるほど、couldってこう使えばいいんだ!」とスッキリ理解できているはずです。一緒にcouldマスターを目指しましょう!

couldって意外と使い道が多いんですね! 楽しみです!
couldの基本:canの過去形としての使い方
まずは、皆さんが一番よく知っているであろう「canの過去形」としてのcouldから見ていきましょう。これはcouldの基本的な意味の一つで、主に「過去にできたこと(能力・可能性)」を表します。
過去にできたこと(能力・可能性)を表すcould
「子供の頃は自転車に乗れた」「若い頃は速く走れた」のように、過去に持っていた能力や、過去のある状況下で可能だったことを表現する時にcouldを使います。
例文を見てみましょう。
- When I was young, I could run very fast.
(若い頃は、とても速く走ることができた。) - She could speak French fluently when she lived in Paris.
(彼女がパリに住んでいた時、フランス語を流暢に話すことができた。) - He tried very hard, but he couldn’t open the jar.
(彼は一生懸命試したが、その瓶を開けることができなかった。)※否定形 couldn’t = could not
これらの例文では、過去の一時期において持っていた一般的な能力や、特定の状況下で可能だったことを示していますね。
ここで一つ注意点です。過去の「特定の場面で実際に何かをすることができた」という事実を述べたい場合は、couldよりもwas/were able toを使う方が自然なことが多いんです。
例えば、「火事の中からなんとか赤ちゃんを助け出すことができた」のような、一回限りの具体的な行動の成功を表す場合です。
・The firefighters were able to rescue the baby from the fire. (消防士たちは火事の中から赤ちゃんを救い出すことができた。)
もしこれを could を使って The firefighters could rescue the baby… と言うと、「救い出す能力はあった(けど、実際に救い出せたかどうかは別)」というニュアンスに聞こえる可能性があります。否定文や、see, hear, feel, understand, remember のような知覚・思考動詞の場合は、could を使っても「実際にできた」意味を表すことが多いんですけどね。
| 表現 | 主なニュアンス | 例文 |
|---|---|---|
| could | 過去の一般的な能力・可能性 (実際にやったかどうかは別) | He could swim across the river when he was a boy. (彼は少年の頃、その川を泳いで渡ることができた=能力があった) |
| was/were able to | 過去の特定の状況で実際に何かをすることができた | He swam hard and was able to reach the other side. (彼は一生懸命泳いで、対岸にたどり着くことができた=実際にできた) |
この違い、少しややこしいかもしれませんが、使い分けられるとより正確な表現ができますよ!
過去の状況における可能性・推量を表すcould
もう一つ、canの過去形としてのcouldには、「過去のある時点で可能だったこと」や「~する可能性があった(けど、実際にはしなかった/起こらなかった)」というニュアンスを表す使い方もあります。
例文です。
- It was a dangerous situation. We could have been injured.
(危険な状況だった。私たちは怪我をしていた可能性があった。)→ 実際には怪我をしなかった - You were lucky. You could have fallen off the ladder.
(君は運が良かったね。はしごから落ちていた可能性があったよ。)→ 実際には落ちなかった - Why didn’t you tell me? I could have helped you.
(どうして言ってくれなかったの? 手伝ってあげられたのに。)→ 実際には手伝えなかった
この用法では、could have + 過去分詞 の形がよく使われます。過去の事実とは違う状況を想定して、「~できたかもしれないのに(実際は違った)」という気持ちを表すんですね。これは後で説明する仮定法にも繋がってくる考え方です。

なるほど! could have + 過去分詞で「できたのに(しなかった)」って言えるんですね!
現在の可能性・推量を表すcouldの使い方
さて、ここからはcouldが「canの過去形」という枠を超えて使われるパターンを見ていきましょう。couldは現在の事柄について、可能性や推量を表すためにもよく使われるんです。
canよりも控えめな可能性・推量を示すcould
現在の可能性や推量を表す場合、couldはcanよりも控えめで、確信度が低いニュアンスを持ちます。「~かもしれない」「~ということもあり得る」といった感じです。mayやmightと似たような意味合いで使われることも多いんですよ。
例文で比較してみましょう。
- Where is John?
– He can be in his office. (オフィスにいるはずだ / いる可能性がある)→ 比較的確信度が高い or 一般的な可能性
– He could be in his office. (オフィスにいるかもしれない)→ 確信度は低め、控えめな推量
– He may be in his office. (オフィスにいるかもしれない)→ couldとほぼ同じか、少しだけ確信度が高い場合も
– He might be in his office. (オフィスにいるかもしれない)→ couldやmayよりさらに確信度が低い
このように、助動詞によって話し手の「確からしさ」の度合いが変わってくるんですね。couldを使うと、断定を避けた、より丁寧で柔らかい印象を与えることができます。
他の例文も見てみましょう。
- This plan could be risky.
(この計画はリスクがあるかもしれない。) - It could rain later, so you should take an umbrella.
(後で雨が降るかもしれないから、傘を持っていった方がいいよ。) - Don’t worry, it could be worse.
(心配しないで、もっと悪くなる可能性だってあったんだから。→ これで済んでよかった)
これらのcouldは、あくまで「可能性の一つ」として述べている感じで、断定的な響きはありません。
「canは『できる』って意味じゃないの?」と思った方もいるかもしれませんね。確かにcanには「能力」の意味がありますが、実は「可能性・推量」の意味もあるんです。「It can be cold in winter.(冬は寒くなることがある)」のように、一般的な可能性を表す時によく使われます。一方、couldはより具体的で、不確かな状況での可能性・推量を示すことが多い、と覚えておくと良いでしょう。
否定形couldn’t:「~のはずがない」という強い否定の推量
面白いことに、否定形のcouldn’tは、肯定形のcouldが持つ「控えめな推量」とは少し違った意味合いを持つことがあります。特に、現在の事柄について「~のはずがない」という強い否定の推量を表すことがあるんです。
これは、否定の推量を表す`can’t`(~のはずがない)と似たような意味で使われます。
- A: Someone is knocking on the door. (誰かがドアをノックしているよ。)
B: It can’t be Mary. She’s in Japan now. (メアリーのはずがないよ。彼女は今日本にいるんだ。) - A: Look! Is that Mr. Tanaka over there? (見て! あそこにいるの、田中さんじゃない?)
B: It couldn’t be him. He’s on a business trip this week. (彼のはずがないよ。今週は出張中だもの。)
`can’t` と `couldn’t` のどちらを使うかは、文脈や話し手の気持ちにもよりますが、一般的に `can’t` の方がより直接的で強い否定、`couldn’t` は少しだけ婉曲的というか、「(常識的に考えて)ありえない」というニュアンスが含まれることがあります。ただ、多くの場合、意味は非常に近いです。
過去の事柄に対する否定の推量として「~だったはずがない」と言いたい場合は、couldn’t have + 過去分詞 の形を使います。
- He couldn’t have known about the surprise party. We kept it a secret.
(彼がサプライズパーティーのことを知っていたはずがない。私たちは秘密にしていたんだから。)
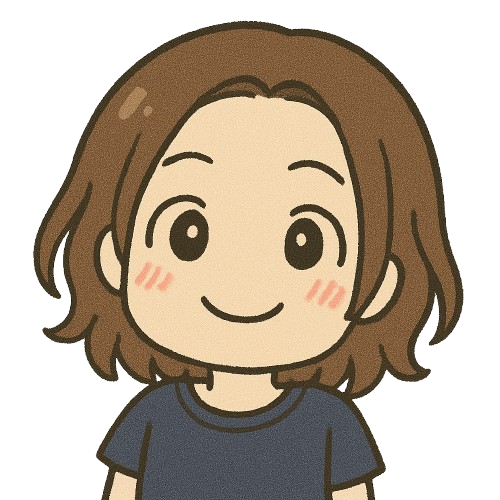
couldn’t が「〜のはずがない」って強い意味になるのは意外でした! can’t と似てるんですね。
丁寧な依頼・許可・提案を表すcouldの使い方
couldのもう一つの重要な役割が、丁寧さを表現することです。特に、人にお願い事をしたり、許可を求めたり、提案したりする場面で大活躍します。canよりも一段階丁寧で、控えめな印象を与えることができるんです。
Could you…? / Could I…?:丁寧な依頼・許可
誰かに何かをお願いしたい時、「Could you…?」という形を使うと、非常に丁寧な依頼になります。「~していただけませんか?」というニュアンスですね。
- Could you please pass me the salt?
(お塩を取っていただけませんか?) - Could you possibly lend me your pen?
(もしよろしければ、ペンをお借りできませんでしょうか?) ← possiblyを入れるとさらに丁寧 - Could you tell me the way to the station?
(駅への道を教えていただけますか?)
もちろん `Can you…?` でも依頼はできますが、`Could you…?` の方がよりフォーマルな場面や、相手に配慮を示したい時に適しています。
同様に、自分が何かをしても良いか許可を求める場合も、「Could I…?」を使うと丁寧になります。「~してもよろしいでしょうか?」という意味合いです。
- Could I use your phone for a moment?
(少しの間、お電話をお借りしてもよろしいでしょうか?) - Could I ask you a question?
(一つ質問してもよろしいでしょうか?) - Could I possibly leave a little early today?
(もし可能でしたら、今日少し早めに退社してもよろしいでしょうか?)
`Can I…?` よりも控えめで、相手の許可を丁寧に伺う姿勢が示せます。
Couldを使った依頼や許可は、現在のことを尋ねているのであって、過去形ではありません。canを過去形にすることで距離感が生まれ、それが丁寧さにつながっている、とイメージすると分かりやすいかもしれませんね。日本語でも「~していただけますでしょうか」のように、少し遠回しな言い方をすることで丁寧さを出すのと似ています。
We could…:控えめな提案
「~するのはどうかな?」「~することもできるね」のように、控えめに提案する時にもcouldが使えます。特に「We could…」の形でよく使われます。
- A: What should we do this weekend? (今週末、何をしようか?)
B: Well, we could go to the movies. (うーん、映画に行くのはどうかな。) - We could have dinner together sometime next week.
(来週あたり、一緒に夕食でもどうかな。) - If you’re free, we could grab a coffee later.
(もし時間があれば、後でコーヒーでもどうかな。)
`We can…` と言うと、「~できるよ!(能力・可能性)」というニュアンスが強くなりますが、`We could…` は「~という選択肢もあるね」といった感じで、相手に判断を委ねるような、より柔らかい提案になります。
Couldを用いたその他の丁寧表現
他にも、couldを使った丁寧な表現があります。
- I could help you with your bags if you like.
(もしよろしければ、お荷物を持つのをお手伝いしましょうか?)
→ 押し付けがましくなく、相手の意向を尊重する申し出になります。 - Could this be the right address?
(こちらが正しい住所でしょうか?)
→ `Is this…?` よりも自信なさげに、あるいは丁寧に確認するニュアンス。
このように、couldは様々な場面で丁寧さを加える便利な助動詞なんです。

Could you…? はよく使うけど、We could… で提案もできるんですね! 使ってみます!
仮定法におけるcouldの使い方
最後に、couldの重要な用法として「仮定法」での使い方を見ていきましょう。仮定法は「もし~だったら、…なのに/…だったのに」のように、現在の事実と違うことや、過去の事実と違うことを仮定して話す表現です。couldは、この仮定の結果(帰結節)を表す部分でよく使われます。
仮定法過去:現在の事実に反する仮定の帰結
仮定法過去は、「もし(今)~なら、…できるのに」のように、現在の事実に反することを仮定し、その結果どうなるかを述べる表現です。形は If + S + 過去形 …, S + could + 動詞の原形 となります。
例文を見てみましょう。
- If I had more time, I could travel around the world.
(もしもっと時間があれば、世界中を旅行できるのに。)
→ 事実:今は時間がないので、世界中を旅行できない。 - If he were here, he could help us.
(もし彼がここにいれば、私たちを手伝ってくれるのに。)
→ 事実:彼はここにいないので、手伝ってくれない。
(仮定法では、be動詞は主語に関わらず were を使うのが伝統的ですが、口語では was が使われることもあります。) - If I could speak Spanish, I could talk to her directly.
(もし私がスペイン語を話せたら、彼女と直接話せるのに。)
→ 事実:スペイン語を話せないので、直接話せない。(If節の中でも能力を表すためにcouldが使われることもあります)
ここでのcouldは「~できるだろうに」という、仮定の状況下での能力や可能性を表しています。
仮定法過去という名前ですが、話している内容は現在の事実に反する仮定です。動詞の形が過去形になるので「仮定法過去」と呼ばれますが、時間軸は現在だという点に注意してくださいね!
仮定法過去完了:過去の事実に反する仮定の帰結
仮定法過去完了は、「もし(あの時)~だったら、…できただろうに」のように、過去の事実に反することを仮定し、その結果どうなっていたかを述べる表現です。形は If + S + had + 過去分詞 …, S + could + have + 過去分詞 となります。
例文です。
- If I had studied harder, I could have passed the exam.
(もしもっと一生懸命勉強していたら、試験に合格できただろうに。)
→ 事実:一生懸命勉強しなかったので、試験に合格できなかった。 - If you had told me earlier, I could have helped you.
(もしもっと早く言ってくれていたら、手伝ってあげられたのに。)
→ 事実:早く言ってくれなかったので、手伝えなかった。 - If we hadn’t missed the train, we could have arrived on time.
(もし電車に乗り遅れていなかったら、時間通りに到着できただろうに。)
→ 事実:電車に乗り遅れたので、時間通りに到着できなかった。
ここでの `could have + 過去分詞` は、「~できたはずなのに(実際はできなかった)」という、過去の事実とは異なる状況下での可能性を表しています。先ほど「canの過去形としての使い方」で触れた `could have + 過去分詞` と形は同じですが、仮定法の場合は「もし~だったら」という条件が伴っている点が異なります。
仮定法現在の帰結節でのcould
少し応用的な使い方として、条件節は過去の事実と反する(仮定法過去完了)けれど、帰結節は現在の状況について述べる、というパターンもあります。
- If I had taken that job offer, I could be rich now.
(もしあの仕事のオファーを受けていたら、今頃お金持ちだったかもしれないのに。)
→ If節:過去の事実(オファーを受けなかった)
→ 帰結節:現在の状況(お金持ちではない)
また、逆に、条件節は現在の事実と反する(仮定法過去)けれど、帰結節は過去にできたであろうことについて述べるパターンもあります。
- If I were younger, I could have joined the marathon last week.
(もしもっと若かったら、先週のマラソンに参加できただろうに。)
→ If節:現在の事実(若くない)
→ 帰結節:過去の可能性(参加できなかった)
仮定法は少し複雑に感じるかもしれませんが、基本的な形と意味をしっかり押さえれば大丈夫です。couldが仮定の世界で「~できるのに」「~できただろうに」という可能性を表す重要な役割を担っていることを理解しておきましょう。

仮定法、苦手意識があったけど、could の役割がわかると少し理解が深まった気がします…!
まとめ
今回は、助動詞「could」の様々な用法について詳しく見てきました。いかがでしたか? canの過去形というだけではない、couldの多様な顔が見えてきたのではないでしょうか。
最後に、この記事のポイントをまとめます。
- canの過去形としてのcould
- 過去の一般的な能力・可能性:「若い頃は速く走れた (I could run fast)」
- 過去の特定の状況で実際にできたこと(否定文や知覚・思考動詞でよく使う、肯定文では was/were able to が自然な場合も):「ドアが開けられなかった (I couldn’t open the door)」
- 過去の可能性(実際はそうならなかった):「事故に遭っていたかもしれない (We could have been injured)」
- 現在の可能性・推量としてのcould
- canより控えめな可能性・推量:「雨が降るかもしれない (It could rain)」
- 否定形couldn’tは強い否定の推量:「彼のはずがない (It couldn’t be him)」
- 丁寧な依頼・許可・提案としてのcould
- 丁寧な依頼:「塩を取っていただけませんか? (Could you pass me the salt?)」
- 丁寧な許可:「電話をお借りしても? (Could I use your phone?)」
- 控えめな提案:「映画に行くのはどうかな? (We could go to the movies)」
- 仮定法におけるcould
- 仮定法過去(現在の事実に反する):「もし時間があれば、旅行できるのに (If I had time, I could travel)」
- 仮定法過去完了(過去の事実に反する):「もし勉強していたら、合格できただろうに (If I had studied, I could have passed)」
couldは一つの単語でありながら、文脈によって意味合いが大きく変わる、非常に表現力豊かな助動詞です。最初は少し戸惑うかもしれませんが、それぞれの用法が持つ核となるイメージ(過去、可能性、丁寧さ、仮定)を意識しながら、たくさんの例文に触れていくことが大切です。
ぜひ、今回学んだことを意識して、実際の英会話やライティングでcouldを使ってみてくださいね。きっと、あなたの英語表現の幅がぐっと広がるはずですよ!

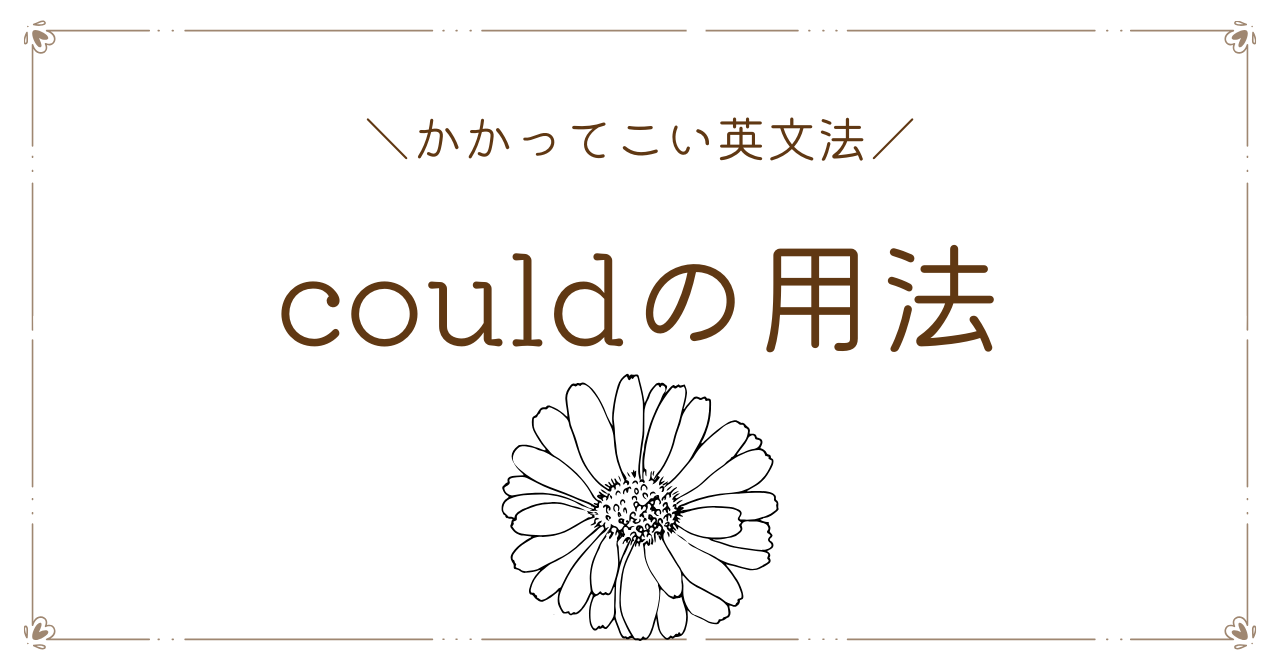

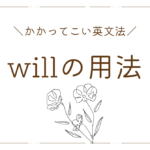
コメント