英語の長文を読んでいると、文の途中にコンマ「,」で挟まれたフレーズや、カッコ ( ) でくくられた言葉がスッと入っているのを見かけること、ありませんか?「これって何のためにあるの?」「なくても意味が通じるような…?」なんて、ちょっと不思議に思ったことがある人もいるかもしれませんね。特に、英語学習を始めたばかりの方や、中学生、高校生、そして大学受験やTOEICでより複雑な文構造に挑戦している皆さんにとって、この「挿入構文」と呼ばれるものは、文の流れを掴みにくくする厄介な存在に感じることもあるでしょう。
でも、心配しないでください!実はこの挿入構文、正しく理解すれば、文章に奥行きを与えたり、話し手のニュアンスを加えたりする、とっても表現豊かなテクニックなんです。この記事では、そんな挿入構文の基本的な役割から、具体的な使い方、見分け方、そして訳し方のコツまで、一つひとつ丁寧に、そして分かりやすく解説していきます。この記事を読み終わる頃には、きっと挿入構文を味方につけて、より自然で洗練された英語表現を理解し、そして自分でも使えるようになっているはずですよ!

挿入って聞くと、なんだか文がややこしくなりそうだけど、これでスッキリわかるかな?
挿入構文の基本 – なぜ文の途中に言葉を挟むの?
まずは、挿入構文がどんなもので、どんな目的で使われるのか、基本的なところから見ていきましょう。「挿入」という名前の通り、文のメインの流れとは別に、補足的な情報や話し手の気持ちなどを「差し込む」働きがあるんです。
挿入構文とは? – 文の途中に挟み込まれる補足情報
挿入構文(または単に「挿入」や「挿入句・挿入節」)とは、文の主要な構造(主語・動詞・目的語など)とは直接的な文法関係を持たず、補足的な情報や説明、話し手の意見や感情などを付け加えるために、文の途中や最後に挟み込まれる語句や節のことを指します。
多くの場合、挿入される部分は、コンマ (,) やダッシュ (―)、カッコ ( ) などで区切られて、文の他の部分と区別されます。そして、その挿入部分を取り除いても、残りの文だけで文法的に正しい文として成り立つのが大きな特徴です。
例えば、
- My brother, who is a doctor, lives in London. (私の兄[弟]は、医者なのだが、ロンドンに住んでいる。)
→ “who is a doctor” は、my brother についての補足情報で、これを取り除いても “My brother lives in London.” という文が成り立ちます。これは関係代名詞の非制限用法の一種ですが、広い意味で挿入と捉えられます。
- This book, to be honest, is not very interesting. (この本は、正直に言うと、あまり面白くない。)
→ “to be honest” は話し手の意見を挿入しており、なくても “This book is not very interesting.” と文が成り立ちます。
- The weather, as you know, has been terrible. (天気は、ご存知の通り、ずっとひどい。)
このように、挿入構文は、文の骨組みに肉付けをして、より詳しい情報やニュアンスを伝える役割を果たしているんです。
挿入の目的 – 説明の追加、感情の表現、話の転換など
では、なぜわざわざ文の途中に言葉を挿入するのでしょうか? その目的は様々です。
- 補足説明や情報の追加: 主な内容に、関連する情報や詳細な説明を付け加えたいとき。
例: Mt. Fuji, the highest mountain in Japan, is beautiful. (富士山は、日本で一番高い山だが、美しい。)
- 話し手の意見や感情の表明: 主観的な考えや気持ちを伝えたいとき。
例: The movie was, in my opinion, a masterpiece. (その映画は、私の意見では、傑作だった。)
- 聞き手への呼びかけや注意喚起: 会話の流れの中で、相手に呼びかけたり、注意を促したりするとき。
例: This is, you see, a very important point. (これはね、わかるでしょう、とても重要な点なんだ。)
- 話の脱線や転換: 主な話題から少し逸れたり、別の話題に移ったりするときのクッションとして。
例: I was talking to John – he just got a new car, by the way – about our vacation plans. (ジョンと話していたんだが – そういえば彼は新しい車を買ったばかりなんだ – 私たちの休暇の計画についてね。)
- ためらいや言い淀み、強調: 言葉を選んだり、特定の点を強調したりするために、間を置くような効果。
例: Well, I suppose, it could be true. (ええと、まあ、それは本当かもしれないね。)
このように、挿入構文は、単に情報を伝えるだけでなく、コミュニケーションをより円滑にしたり、表現に深みを持たせたりするのに役立っているんです。
挿入される語句の種類 – 単語・句・節と様々
挿入される言葉は、1語の単語から、いくつかの語が集まった句、そして主語と動詞を含む節まで、様々な形をとります。
- 単語の挿入:
例: He is, however, a very kind person. (しかしながら、彼はとても親切な人だ。)
(however: しかしながら – 接続副詞)
- 句の挿入 (前置詞句、不定詞句、分詞構文など):
例: The report, in short, was a disaster. (その報告書は、要するに、大失敗だった。)
(in short: 要するに – 前置詞句)
例: To tell the truth, I don’t like this plan. (実を言うと、私はこの計画が好きではない。)
(To tell the truth: 実を言うと – 不定詞句。文頭に来ることも多い。)
例: The old man, walking slowly, crossed the street. (その老人は、ゆっくりと歩きながら、道を渡った。)
(walking slowly: ゆっくりと歩きながら – 分詞構文)
- 節の挿入 (主語 + 動詞 を含む):
例: This method, I believe, is the most effective. (この方法は、私が信じるには、最も効果的だ。)
(I believe: 私が信じるには)
例: He said, “I’m tired,” yawning loudly. (彼は「疲れたよ」と、大きなあくびをしながら言った。)
(yawning loudly: 大きなあくびをしながら – 分詞構文が節のように機能)
挿入されるものは、文のメインの流れとは独立していることが多いので、それ自体が一つの小さな文のようになっていることもありますね。まるで、会話の途中でちょっとした「つぶやき」や「合いの手」を入れるような感覚に近いかもしれません。

へぇ~、挿入って、文に彩りを添えるスパイスみたいなものなんだね!色々な目的があるんだなぁ。
よく使われる挿入構文のパターンと見分け方
それでは、具体的にどんな挿入構文がよく使われるのか、その代表的なパターンと、それらをどう見分ければいいのかを見ていきましょう。これらを覚えておけば、長文読解も怖くありません!
コンマ (,) で区切られる挿入 – 最も一般的な形
挿入構文で最もよく使われるのが、コンマ (,) で挟み込む形です。文の途中に入れる場合は、挿入部分の前後にコンマを打ちます。文末に挿入する場合は、挿入部分の前にコンマを打ちます。
1. 接続副詞 (however, therefore, moreover など)
however (しかしながら), therefore (それゆえに), thus (したがって), moreover (さらに), furthermore (さらに), consequently (その結果), nevertheless/nonetheless (それにもかかわらず) といった接続副詞は、文と文の意味的なつながりを示すために、よく挿入として使われます。
- The plan seemed perfect. There was, however, one major flaw.
(その計画は完璧に見えた。しかしながら、一つ大きな欠陥があった。)
- He studied hard; therefore, he passed the exam.
(彼は一生懸命勉強した。それゆえに、試験に合格した。)
※ セミコロン (;) の後に使われることも多いです。
- This new model is more efficient. Moreover, it is cheaper.
(この新しいモデルはより効率的だ。さらに、より安価だ。)
これらの接続副詞は、文頭や文末に来ることもありますが、文中に挿入されると、文の流れを一度区切って、論理的なつながりを強調する効果があります。
2. 副詞句 (of course, in fact, for example など)
of course (もちろん), in fact (実際は), as a matter of fact (実のところ), for example/for instance (例えば), in short (要するに), in other words (言い換えれば), by the way (ところで), on the other hand (一方では) といった副詞的な働きをする句も、頻繁に挿入として使われます。
- She is, of course, a very talented musician.
(彼女は、もちろん、非常に才能のある音楽家だ。)
- The weather forecast was sunny, but, in fact, it rained all day.
(天気予報は晴れだったが、実際には、一日中雨だった。)
- There are many kinds of sports, for example, soccer, baseball, and tennis.
(たくさんの種類のスポーツがある、例えば、サッカー、野球、そしてテニスだ。)
- I need to finish this report by tomorrow. This means, in other words, I have to work late tonight.
(明日までにこの報告書を終えなければならない。これは、言い換えれば、今夜遅くまで働かなければならないということだ。)
これらの副詞句は、話し手の確信度を示したり、具体例を挙げたり、話題を転換したりと、様々な役割を果たします。
3. I think / I believe / I suppose などの「思考・伝聞」を表す節
I think (私は思う), I believe (私は信じる), I suppose/guess (私は推測する), it seems (~のようだ), they say (~と言われている), as far as I know (私の知る限りでは) といった、話し手の思考や判断、あるいは伝聞を表す短い節も、よく挿入されます。
- This plan will, I think, be successful.
(この計画は、私が思うに、成功するだろう。)
- The rumor is, it seems, true.
(その噂は、どうやら、本当のようだ。)
- He is, they say, a millionaire.
(彼は、噂によると、百万長者だそうだ。)
- She is, as far as I’m concerned, the best candidate.
(私に関する限りでは、彼女が最適な候補者だ。)
これらの挿入節は、断定的な響きを和らげたり、情報源をほのめかしたりする効果があります。 会話では特に頻繁に使われますね。
4. 関係代名詞の非制限用法 (who, which)
すでに出てきましたが、関係代名詞の非制限用法(先行詞について補足的な説明を加える用法で、先行詞の直後にコンマを置き、関係詞節を続ける)も、一種の挿入構文と見なせます。
- My father, who is 60 years old, still works full time.
(私の父は、60歳なのだが、まだフルタイムで働いている。)
- I visited Paris, which is the capital of France, last year.
(私は昨年パリを訪れたが、そこはフランスの首都である。)
非制限用法の関係詞節は、それがなくても文の主要な意味は通じますが、加えることで情報がより豊かになります。
関係代名詞の非制限用法では、that は使えない、というルールを覚えていますか? who か which を使います。また、コンマが必須であることにも注意しましょう。
ダッシュ (―) で区切られる挿入 – 強調や明確な区切り
コンマよりもやや強い区切りや、強調、あるいは突然の思考の転換を示したいときには、ダッシュ (―) が使われることがあります。ダッシュには、em dash (エムダッシュ、—) と en dash (エヌダッシュ、–) がありますが、挿入でよく使われるのは em dash の方です。ハイフン (-) とは長さが違うので注意しましょう。(ここでは便宜上、全角のダッシュ「―」を使います。)
- She is an excellent student ― perhaps the best in her class ― and also a talented artist.
(彼女は優秀な生徒であり ― おそらくクラスで一番だろう ― そして才能ある芸術家でもある。)
→ “perhaps the best in her class” が、前の “excellent student” をさらに強調・補足しています。
- All three of them ― John, Mary, and Tom ― passed the exam.
(彼ら3人全員 ― ジョン、メアリー、そしてトム ― が試験に合格した。)
→ “All three of them” の具体的な内容を列挙しています。同格の挿入に近いですね。
- He finally arrived ― two hours late.
(彼はついに到着した ― 2時間遅刻で。)
→ 文末にダッシュで補足情報を加えています。
ダッシュは、コンマよりも視覚的に目立つため、挿入部分をより際立たせる効果があります。また、コンマが多用されている文の中で、さらに挿入を行いたい場合にも、区別をつけるためにダッシュが使われることがあります。
カッコ ( ) で区切られる挿入 – 付加的・補足的な情報
カッコ ( ) [英語では parentheses と言います] も、挿入によく使われる記号です。カッコで囲まれた部分は、文の主要な流れからはやや独立した、付加的・補足的な情報や、ちょっとした注釈、あるいは話し手の個人的なコメントであることが多いです。
- The company’s profit increased significantly last year (see Figure 3 for details).
(その会社の利益は昨年大幅に増加した(詳細は図3参照)。)
→ 読者への参照情報を示しています。
- He told me he would come (though I didn’t really believe him).
(彼は来ると言った(もっとも私はあまり彼を信じていなかったが)。)
→ 話し手の心の声を挿入しています。
- Many people (including me) are looking forward to the event.
(多くの人々が(私も含めて)そのイベントを楽しみにしている。)
カッコ内の情報は、それがなくても文全体の意味はほぼ変わらない、おまけのような情報であることが多いです。コンマやダッシュによる挿入よりも、さらに「脇道に逸れた」感じが強くなりますね。
レポートや学術論文などでは、参考文献や追加のデータを示すためにカッコがよく使われます。また、戯曲のセリフで、役者の動作や表情を指示するト書き (stage directions) もカッコで囲まれますね。
挿入構文の見分け方 – 取り除いても文が成立するか?
挿入構文かどうかを見分ける最も確実な方法は、その挿入されていると思われる部分を文から取り除いてみたときに、残りの部分だけで文法的に正しい、意味の通じる文が成り立つかどうかを確認することです。
例: The city, once a small fishing village, has now become a major tourist destination.
この文で、”once a small fishing village” が挿入かどうかを確かめてみましょう。
これを取り除くと、”The city has now become a major tourist destination.” (その都市は今や主要な観光地となった。) という、文法的に正しく、意味も通じる文が残りますね。したがって、”once a small fishing village” は挿入句であると判断できます。
長文読解で複雑な文に出会ったとき、どこが文の骨格(主語・動詞など)で、どこが修飾語句や挿入なのかを見極めることは、内容を正確に理解するために非常に重要です。挿入部分は、いったんカッコに入れて脇に置いておき、まずは文の主要な構造を掴む、という読み方も有効ですよ。

コンマ、ダッシュ、カッコで使い分けがあるんだ!取り除いてみるって、いい方法かも!
挿入構文を効果的に使いこなすために – 訳し方と注意点
挿入構文を理解するだけでなく、自分でも効果的に使えるようになると、英語の表現力が格段にアップします。ここでは、挿入構文を自然に訳すコツと、使う上での注意点についてお話しします。
挿入構文の自然な訳し方 – 「~だが」「~はさておき」など
挿入構文を日本語に訳すときは、挿入されている内容と文全体の流れを考慮して、自然な日本語になるように工夫する必要があります。直訳するとぎこちなくなることが多いので注意しましょう。
挿入の種類や文脈によって、様々な訳し方が考えられます。
- 補足説明: 「~なのだが」「~で、それは」「~、つまり」
例: My sister, a lawyer, lives in New York.
→ 私の姉は、弁護士なのだが、ニューヨークに住んでいる。
- 話し手の意見・感情: 「~と私は思う」「~は確かだ」「残念ながら~」
例: This cake is, I must say, delicious.
→ このケーキは、言わせてもらえば、とても美味しい。
- 聞き手への配慮: 「ご存知の通り」「おわかりでしょうが」「率直に言えば」
例: The exam was, as you probably know, very difficult.
→ 試験は、おそらくご存知でしょうが、とても難しかった。
- 対比・逆接: 「しかしながら」「それどころか」「一方では」
例: He looks young; he is, in reality, over fifty.
→ 彼は若く見えるが、実際には、50歳を超えている。
- 例示: 「例えば」「具体的には」
例: Some fruits, such as apples and oranges, are rich in vitamins.
→ いくつかの果物、例えばリンゴやオレンジなどは、ビタミンが豊富だ。
訳す際には、挿入部分を先に訳してから主文に戻るか、主文を訳している途中で自然な形で挟み込むか、あるいは文末に「~ちなみに」のように付け加えるかなど、いくつかのパターンが考えられます。文全体の意味がスムーズに伝わるように、柔軟に対応しましょう。
場合によっては、挿入部分をカッコに入れて訳したり、注釈として扱ったりするのも有効です。
挿入を使いすぎると読みにくくなる? – バランスが大切
挿入構文は表現を豊かにする便利なツールですが、使いすぎると、かえって文が読みにくくなったり、話が分かりにくくなったりする可能性があります。
特に、長い挿入句や挿入節が頻繁に出てくると、文の主要な流れが見失われがちです。一つの文に複数の挿入を重ねるのも、避けた方が無難でしょう。
挿入を使うときは、
- その情報が本当に補足として必要か?
- 挿入することで、文全体の分かりやすさが損なわれないか?
- もっとシンプルに別の文で表現できないか?
といったことを一度考えてみると良いでしょう。挿入は、あくまでも「スパイス」のようなもの。適度に使うことで効果を発揮しますが、入れすぎは禁物です。バランス感覚を大切にしましょう。
フォーマルな文体とインフォーマルな文体での使い分け
挿入構文の種類によっては、フォーマルな場面に適したものと、インフォーマルな会話でよく使われるものがあります。
- フォーマルな文体で好まれる挿入:
- 接続副詞 (however, therefore, moreover など)
- 関係代名詞の非制限用法
- 学術的な注釈や参照 (カッコを使ったもの)
- インフォーマルな会話でよく使われる挿入:
- I think, you know, I mean などの短い節
- of course, by the way などの副詞句
- ためらいや言い換えを表すもの
例えば、論文やビジネス文書のようなフォーマルな文章で、”you know” (あのね、ええと) のようなくだけた挿入を多用するのは避けるべきです。逆に、友達とのカジュアルな会話で、”therefore” や “moreover” を頻繁に使うと、少し堅苦しい印象を与えるかもしれません。
場面や相手に応じて、適切な挿入表現を選ぶことも大切ですね。
TOEICや英検などの試験ではどう扱われる?
TOEIC L&Rテストや英検などの英語の試験では、挿入構文は主に長文読解問題で、文の構造を複雑にし、読解力を試すために使われることが多いです。
- 読解問題: 挿入部分を見抜き、それがなくても文の主要な意味が通じることを理解できるかがポイントです。挿入部分に惑わされずに、主語、動詞、目的語といった文の骨格を正確に捉える練習が必要です。また、挿入されている接続副詞や副詞句が、前後の文脈とどういう論理関係にあるのかを理解することも重要になります。
- 文法問題: 関係代名詞の非制限用法のコンマの有無や、接続副詞の適切な選択などが問われる可能性があります。また、挿入された語句の品詞や形が正しいかどうかを判断させる問題も考えられます。
- リスニング問題: 会話の中で、”I think” や “you know” のような短い挿入が自然な流れで入ってくることがあります。これらに慣れていないと、聞き取りの妨げになることも。普段から、ネイティブの自然な会話音声に触れておくことが大切です。
試験では、挿入構文は「ひっかけ」や「難易度を上げる」要素として使われることもあります。でも、基本的なルールとパターンをしっかり押さえていれば、落ち着いて対処できるはずですよ!

挿入って、使いすぎもダメなんだ…。バランスが大事なのね。訳し方も色々あって勉強になります。
まとめ – 挿入構文を味方につけて、英語表現の達人へ!
今回は、英語の文に深みと彩りを与える「挿入構文」について、その基本的な役割から具体的なパターン、見分け方、そして効果的な使い方まで、詳しく見てきました。これで、今までなんとなくモヤモヤしていた挿入の謎が、少しでも解き明かされたなら嬉しいです。
最後に、この記事で学んだ挿入構文の重要なポイントをまとめておきましょう。
- 挿入構文とは:
- 文の主要な構造とは別に、補足情報や話し手の意見などを挟み込む語句や節。
- コンマ (,)、ダッシュ (―)、カッコ ( ) などで区切られることが多い。
- 挿入部分を取り除いても、残りの文だけで文法的に成り立つ。
- 挿入の目的:
- 補足説明、感情表現、話の転換など様々。
- 主な挿入のパターン:
- 接続副詞 (however, therefore など)
- 副詞句 (of course, in fact など)
- 思考・伝聞を表す節 (I think, it seems など)
- 関係代名詞の非制限用法
- 見分け方と訳し方:
- 挿入部分を取り除いて文が成立するか確認する。
- 訳すときは、文脈に合わせて自然な日本語になるように工夫する。
- 使う上での注意点:
- 使いすぎると読みにくくなるので、バランスが大切。
- フォーマル/インフォーマルな場面での使い分けを意識する。
挿入構文は、一見すると文を複雑にしているように感じるかもしれませんが、書き手や話し手の意図をより細やかに伝え、コミュニケーションを豊かにするための重要なテクニックです。この構文を理解し、自分でも使えるようになれば、あなたの英語表現は格段に洗練され、よりネイティブに近い自然なものになるでしょう。
最初は、長文の中で挿入部分を見つける練習から始めてみてください。 そして、徐々に自分でも短い挿入句を使ってみるなど、少しずつステップアップしていけば大丈夫です。楽しみながら、英語の奥深さを味わっていってくださいね!
この記事が、皆さんの英語学習の旅をより実りあるものにするための一助となれば、これ以上嬉しいことはありません。頑張ってください!

挿入構文、バッチリ理解できた気がします!これで長文も怖くないし、自分でも使ってみたいな!


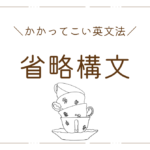
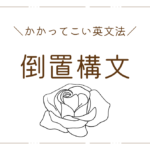
コメント