英語の文法で「不定詞」って出てくると、「うーん、なんだか難しそう…」って思っちゃいませんか? 特に「名詞的用法」「形容詞的用法」「副詞的用法」なんて、3つも使い方があるって聞くと、頭が混乱しちゃいますよね。「to + 動詞の原形」の形はよく見るけど、それが「~すること」って訳される時と、「~するために」って訳される時があって、どう使い分けるの?って悩んでいる方も多いはず。
でも、不定詞は英語を豊かに表現するための、とっても便利なツールなんです!今回は、その中でも基本となる「名詞的用法」にスポットライトを当てて、徹底的に解説していきますよ!「~すること」と訳されるこの用法が、文の中でどんな役割を果たしているのか、どうやって使うのか、そして間違いやすいポイントまで、初心者の方にも分かりやすく、例文をたくさん使いながら見ていきましょう。この記事を読めば、不定詞の名詞的用法はもう怖くない!自信を持って使いこなせるようになります!

不定詞の名詞的用法…「~すること」って訳すのは知ってるけど、それだけじゃないのかな?
不定詞の名詞的用法とは?基本のキホンを押さえよう!
まずは、不定詞の名詞的用法がどんなものなのか、その基本的な役割と意味からしっかり確認していきましょう。ここが理解できると、具体的な使い方もグッと分かりやすくなりますよ。
不定詞のおさらい:そもそも不定詞って何だっけ?
本題に入る前に、ちょっとだけ「不定詞」そのものについておさらいです。
不定詞とは、主に「to + 動詞の原形」の形をとり、文の中で特定の品詞に役割が固定されず、名詞・形容詞・副詞という3つの異なる働きをすることができる、とっても便利な言葉でしたね。(※toの付かない原形不定詞もありますが、ここでは主にto不定詞を扱います)
動詞の「~する」という意味を持ちながら、文脈に応じて色々な役割をこなせる、まさに変幻自在の表現なんです。
名詞的用法の役割:「~すること」という意味の名詞の塊になる!
その3つの働きのうち、今回注目するのが「名詞的用法」です。
その名の通り、不定詞(to + 動詞の原形)が、まるで一つの「名詞」のように機能する使い方を指します。そして、その意味は基本的に「~すること」と訳すことができます。
例:
- to swim → 泳ぐこと
- to study English → 英語を勉強すること
- to help others → 他の人を助けること
このように、「to + 動詞の原形」のかたまり全体が、「~すること」という意味の名詞の塊(名詞句)になる、とイメージしてください。
そして、普通の「名詞」が文の中で主語(S)になったり、補語(C)になったり、目的語(O)になったりできるように、名詞的用法の不定詞も、文の中で同じように主語・補語・目的語の役割を果たすことができるんです!
名詞的用法の見分け方:「~すること」と訳せるかチェック!
不定詞が出てきたときに、それが名詞的用法なのか、それとも他の用法(形容詞的・副詞的)なのかを見分ける一番簡単な方法は、「~すること」と訳してみて、文の意味が自然に通るかどうかを確認することです。
もし「~すること」と訳して文意がしっくりくれば、それは名詞的用法である可能性が高いです。
例:
- I like to play tennis.
- 「テニスをすることが好きだ」→ 自然な意味! → 名詞的用法(目的語)
- My hobby is to collect coins.
- 「私の趣味はコインを集めることだ」→ 自然な意味! → 名詞的用法(補語)
- To read books is fun.
- 「本を読むことは楽しい」→ 自然な意味! → 名詞的用法(主語)
一方、もし「~すること」と訳してもしっくりこない場合は、他の用法(形容詞的:「~するための」 / 副詞的:「~するために」など)を考えてみる必要があります。
もちろん、文法的な役割(S, C, Oになっているか)を確認するのが一番確実ですが、まずは「~すること」と訳せるか試してみるのが、簡単な見分け方の第一歩ですよ!
名詞的用法の使い方①:主語(S)になる不定詞「~することは…」
では、ここからは名詞的用法の具体的な使い方を、文の中での役割ごとに見ていきましょう。まずは、不定詞が文の主語(S)になる場合です。
基本的な形:「To + 動詞の原形 …」が文の主語になる
不定詞句(to + 動詞の原形 … のかたまり)が、そのまま文の主語になるパターンです。「~することは…だ」という意味の文を作ります。
【例文】
- To learn a foreign language is interesting. (外国語を学ぶことは面白い。)
- [To learn a foreign language] という不定詞句全体が、この文の主語(S)になっています。
- 動詞は is で、単数扱いになっている点にも注目です。不定詞句が主語になる場合、原則として単数扱いになります。
- To exercise every day keeps you healthy. (毎日運動することはあなたを健康に保つ。)
- [To exercise every day] が主語(S)。
- 動詞は keeps と三単現のsが付いていますね。これも主語が単数扱いだからです。
- To tell a lie is wrong. (嘘をつくことは間違っている。)
- [To tell a lie] が主語(S)。
このように、不定詞句が文の先頭に来て主語として機能することができます。
超重要!形式主語「It」を使う構文:「It is ~ to do …」
ただし、先ほどの「To + 動詞の原形 …」が主語になる形は、特に不定詞句が長くなると、文の最初が重たい「頭でっかち」な印象になりがちで、実際の英語では、特に会話ではあまり好まれません。
そこで登場するのが、形式主語(または仮主語)の “It” を使う、非常によく使われる構文です!
【構文の形】
It + be動詞 + [形容詞/名詞など] + (for 人) + to + 動詞の原形 …
【考え方】
- 本来の主語である不定詞句(真主語)は長くて重いので、一旦文の後ろの方に移動させる。
- 主語の位置が空いてしまうので、代わりに「仮の主語」として形だけの “It” を置く。
- 「It is [形容詞/名詞など]」の部分で、まず結論(~は…だ)を先に言ってしまう。
- そのあとで、「何が?」に対する答えとして、本当の主語である不定詞句(to do …)を付け加える。
【例文で比較】
- 元の形: To learn a foreign language is interesting.
- 形式主語構文: It is interesting to learn a foreign language. (外国語を学ぶことは面白い。)
- It = 形式主語
- to learn a foreign language = 真主語
- この方が、結論 (It is interesting) が先に分かり、文のバランスも良くなります。
- 元の形: To get up early is difficult for me.
- 形式主語構文: It is difficult for me to get up early. (私にとって早起きすることは難しい。)
- “for me” は不定詞の意味上の主語(誰にとって難しいか)を示しています。
- It is important to follow the rules. (ルールに従うことは重要だ。)
- It was nice to talk with you. (あなたと話せてよかった。)
- Is it possible to finish this today? (今日これを終えることは可能ですか?)
この「It is ~ to do …」の構文は、英語の基本中の基本であり、会話でも文章でも本当に頻繁に使われます。絶対にマスターしておきたい形です!
形式主語構文のメリット
- 文のバランスが良い: 長い主語が後ろに行くので、文全体のバランスが取れ、自然に聞こえます。
- 結論が先にわかる: “It is important…” のように、まず「何が重要か」という結論が先に提示されるため、聞き手(読み手)が内容を理解しやすくなります。
- 口語的で自然: 特に会話では、形式主語 “It” を使う方が圧倒的に自然です。
不定詞を主語として使いたい場合は、まずこの「It is ~ to do …」の形を思い浮かべるようにしましょう。
形式主語 “It” は、天候・時間・距離などを表す It とは別物で、あくまで「to不定詞句」を指す仮の主語です。It自体に具体的な意味はありません。
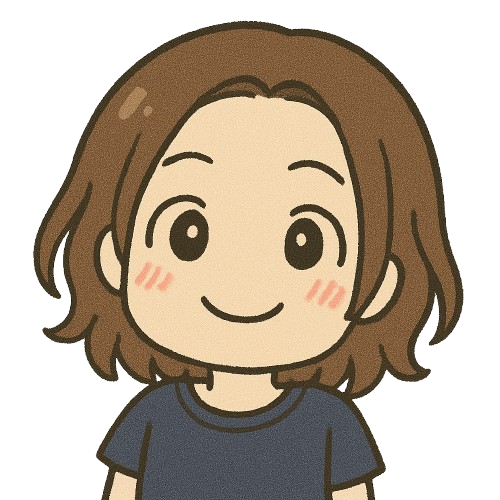
形式主語の It、便利ですね!こっちの方が自然なんだ!これなら使えそう!
名詞的用法の使い方②:補語(C)になる不定詞「~は…することだ」
次に、不定詞が文の補語(C)になる場合を見ていきましょう。これは主に第2文型(SVC)で見られる使い方です。
補語としての役割:「主語 = ~すること」の関係を表す (SVC)
第2文型(SVC)は、「主語(S) + 動詞(V) + 補語(C)」の構造で、「主語(S) = 補語(C)」というイコールの関係が成り立つ文型でしたね。補語(C)は、主語(S)が「どのようなものか」「どのような状態か」を説明する役割を果たします。
不定詞が名詞的用法で補語(C)になる場合、「主語(S) = to + 動詞の原形 … (~すること)」という関係になり、「主語は~することだ」という意味を表します。主に、主語の内容を具体的に説明するために、be動詞の後ろに置かれます。
【構文の形】
[主語 S] + be動詞 + [to + 動詞の原形 …] (C)
例文で確認:「私の夢は~することだ」「目標は~することだ」
どんな時に使われるか、例文を見てみましょう。主語が「夢(dream)」「趣味(hobby)」「目標(goal)」「計画(plan)」「問題(problem)」「重要なこと(important thing)」などの場合に、その具体的な内容を不定詞で説明するパターンが非常に多いです。
- My dream is to travel around the world. (私の夢は世界中を旅することです。)
- [My dream (S)] = [to travel around the world (C)]
- Her main goal is to pass the entrance exam. (彼女の主な目標は入学試験に合格することです。)
- [Her main goal (S)] = [to pass the entrance exam (C)]
- Our plan for this weekend is to go camping. (私たちの今週末の計画はキャンプに行くことです。)
- [Our plan for this weekend (S)] = [to go camping (C)]
- The best way to learn English is to use it every day. (英語を学ぶ最良の方法は毎日それを使うことです。)
- [The best way to learn English (S)] = [to use it every day (C)]
- His ambition was to become president. (彼の野心は社長になることだった。)
- [His ambition (S)] = [to become president (C)] ※過去形の例
このように、be動詞の後ろに「to + 動詞の原形」が来て、「主語が具体的に何であるか(何することか)」を説明している場合、それは名詞的用法の補語だと判断できます。「~すること」と訳すとぴったり合いますね。
主語と不定詞の間に「=(イコール)」の関係が成り立つかどうか、確認してみると分かりやすいですよ!
名詞的用法の使い方③:目的語(O)になる不定詞と「疑問詞+to不定詞」
最後に、不定詞が文の目的語(O)になる場合と、それに関連する便利な形「疑問詞 + to不定詞」を見ていきましょう。これも非常に重要な使い方です。
目的語としての役割:「~することを…する」 (SVOなど)
名詞的用法の不定詞は、動詞の目的語(O)、つまり「~を」「~に」にあたる部分になることもできます。「~すること」を目的語として、「~することを(動詞)する」という意味の文を作ります。
【構文の形】
[主語 S] + [動詞 V] + [to + 動詞の原形 …] (O)
ただし、どんな動詞でも不定詞を目的語にとれるわけではありません。目的語として「to不定詞」をとることが多い動詞は、ある程度決まっています。
目的語に不定詞をとる主な動詞リスト (want, hope, decide など)
以下に、目的語として「to不定詞」をよく使う代表的な動詞を挙げます。これらの動詞の後ろに「to + 動詞の原形」が来ていたら、「~することを…する」という名詞的用法の可能性が高いです。
- want to do (~したい)
- hope to do (~することを望む)
- wish to do (~したいと願う)
- expect to do (~するつもりだ、~することを期待する)
- need to do (~する必要がある)
- decide to do (~することを決める)
- plan to do (~することを計画する)
- promise to do (~することを約束する)
- offer to do (~することを申し出る)
- refuse to do (~することを拒む)
- agree to do (~することに同意する)
- learn to do (~できるようになる、~することを学ぶ)
- try to do (~しようと試みる、努力する)
- manage to do (なんとか~する、うまく~し遂げる)
- pretend to do (~するふりをする)
- mean to do (~するつもりである)
- choose to do (~することを選ぶ)
- fail to do (~しそこなう、~できない)
- hesitate to do (~するのをためらう)
- prepare to do (~する準備をする)
- seem to do (~するように思われる) ※SVC文型の一部として
- appear to do (~するように見える) ※SVC文型の一部として
他にもたくさんありますが、まずはこれらの基本的な動詞と「to不定詞」の組み合わせを覚えておくと良いでしょう。
例文で確認:「~したい」「~することを決めた」など
実際に目的語として不定詞が使われている例文を見てみましょう。
- I want to visit Italy someday. (私はいつかイタリアを訪れたい。)
- want の目的語(O)が [to visit Italy someday]。
- She hopes to become a famous singer. (彼女は有名な歌手になることを望んでいる。)
- hopes の目的語(O)が [to become a famous singer]。
- We decided to start a new project. (私たちは新しいプロジェクトを始めることを決めた。)
- decided の目的語(O)が [to start a new project]。
- He learned to swim when he was six. (彼は6歳の時に泳げるようになった。)
- learned の目的語(O)が [to swim]。
- Please try to understand my situation. (私の状況を理解しようと努めてください。)
- try の目的語(O)が [to understand my situation]。
動詞の後ろに「to + 動詞の原形」が来て、「~すること」という意味で目的語になっているのが分かりますね。
【不定詞と動名詞の違いに注意!】
動詞の中には、目的語として「to不定詞」だけでなく「動名詞(-ing形)」もとれるものがあります (like, love, start, begin, continue, prefer など)。この場合、意味がほとんど変わらないこともありますが、動詞によっては意味が変わることもあります (try, remember, forget, stop, regret など)。例えば、try to do は「~しようと努力する」、try doing は「試しに~してみる」という意味になります。この違いは非常に重要なので、別の記事で詳しく解説しますね!
「疑問詞 + to不定詞」:名詞句としてS, C, Oになる便利な形
名詞的用法の特別な形として、「疑問詞 (what, when, where, which, how, whether ※why以外) + to不定詞」の形があります。これは、全体で一つの名詞の塊(名詞句)となり、文の中で主語(S)、補語(C)、目的語(O)になることができます。
【意味】
疑問詞の意味に「~すべきか」を加えた意味になります。
- what to do : 何をすべきか
- when to leave : いつ出発すべきか
- where to go : どこへ行くべきか
- which way to choose : どちらの道を選ぶべきか
- how to use this machine : この機械の(どのように使うべきか→)使い方
- whether to tell him the truth (or not) : 彼に真実を話すべきかどうか
【例文】
- I can’t decide which dress to wear to the party. (パーティーにどちらのドレスを着ていくべきか決められない。)
- decide の目的語(O)になっています。
- Could you show me how to operate this computer? (このコンピューターの操作方法を教えていただけますか?)
- show の間接目的語 me に対する直接目的語のような働き。
- The biggest question is when to announce the results. (最大の問題はいつ結果を発表すべきかです。)
- be動詞 is の補語(C)になっています。
- What to do next is our main concern now. (次に何をすべきかが、今の私たちの主な関心事です。)
- 文全体の主語(S)になっています。
この「疑問詞 + to不定詞」は、”what should I do” や “how should I use…” のような「疑問詞 + S + should + V」の節を、より簡潔に表現する方法として、非常に便利で会話でもよく使われます。ぜひマスターして使ってみてください!
「疑問詞 + to不定詞」って、見た目は疑問文みたいだけど、文の中では名詞なんですね?
その通りです!形に疑問詞 (what, howなど) が含まれているので、疑問文の一部のように見えるかもしれませんが、これはあくまで「何をすべきか」「どうすべきか」という意味の「名詞の塊」なんです。なので、普通の疑問文のように文末に?が付いたり、語順が変わったりはしません。文の中で、名詞が置かれる場所(主語、補語、目的語)にそのままポンと置かれるイメージですね。

目的語になるパターン、すごくよく使いそう!疑問詞 + to不定詞も便利で覚えたいです!
まとめ:不定詞の名詞的用法をマスターして表現の幅を広げよう!
今回は、不定詞の3つの用法の中でも基本となる「名詞的用法」について、その意味、役割、そして具体的な使い方(主語、補語、目的語)を徹底的に解説してきました。最後に、今回の重要ポイントをまとめて、しっかり記憶に定着させましょう!
- 不定詞の名詞的用法とは:
- 形: to + 動詞の原形
- 意味: 「~すること」
- 働き: 文の中で名詞と同じように、主語(S)、補語(C)、目的語(O)になる。
- 主語(S)になる場合: 「~することは…だ」
- 基本形: [To do …] is/are …
- 重要構文: 形式主語 “It” を使う「It is ~ to do …」の形がはるかに一般的で自然!
- 補語(C)になる場合: 「~は…することだ」
- SVC文型で、be動詞の後ろに置かれ、「主語 = ~すること」の関係を表す。
- 例: My hobby is to collect stamps.
- 目的語(O)になる場合: 「~することを…する」
- 特定の動詞 (want, hope, decide, try など) の後ろに置かれる。
- 例: I want to learn English.
- ※動名詞(-ing)との使い分けが必要な動詞もある。
- 疑問詞 + to不定詞: 「何を~すべきか」などの意味の名詞句
- what/when/where/which/how/whether + to do
- 文中で主語(S)、補語(C)、目的語(O)になれる。
- 例: Please tell me what to do.
- 見分け方: 不定詞が「~すること」と訳せて、文の中でS, C, Oの役割を果たしていれば名詞的用法。
不定詞の名詞的用法は、「~すること」を英語で表現するための基本的な方法です。特に形式主語 “It” を使った構文や、目的語として使われるパターン、そして「疑問詞 + to不定詞」は、日常会話から試験まで、あらゆる場面で頻繁に登場します。
今回の内容をしっかり理解し、例文を参考にしながら実際に使ってみることで、不定詞への苦手意識はきっとなくなります。名詞的用法をマスターして、英語の表現の幅をさらに広げていきましょう!

名詞的用法、スッキリ理解できました!「~すること」ってシンプルだけど、色々な役割があるんですね!しっかり復習します!

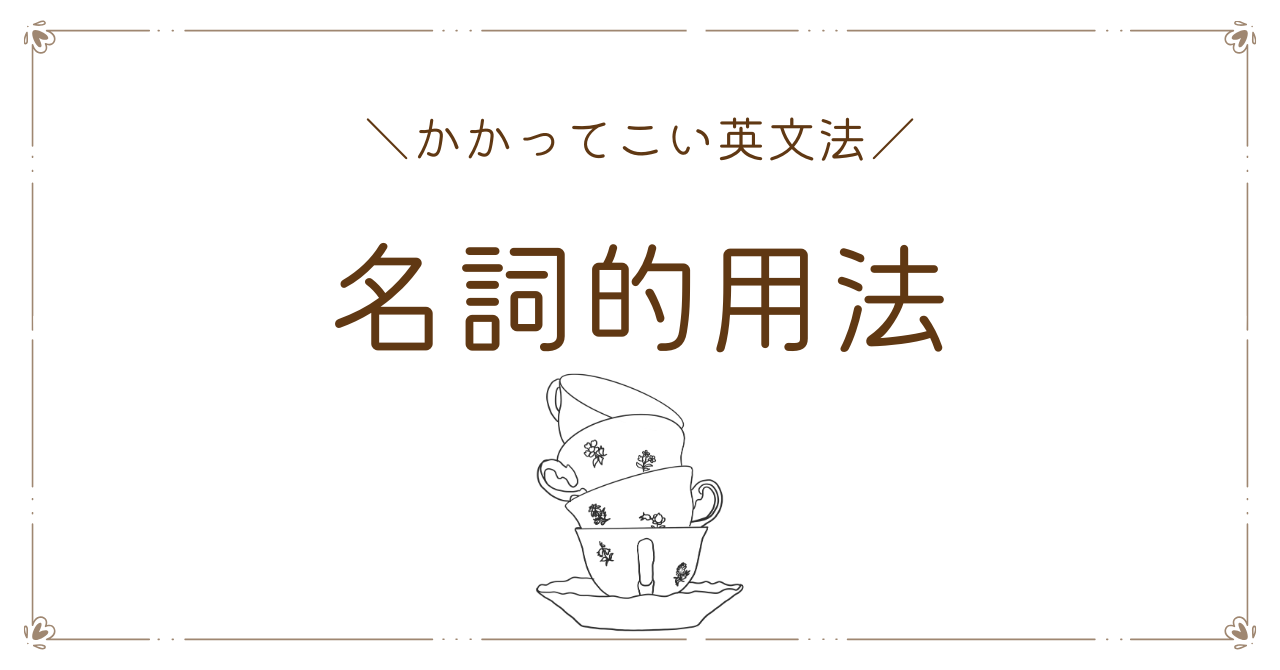
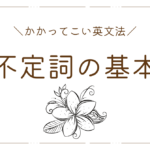
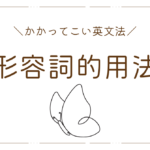
コメント