英語で「~すること」を表す動名詞(~ing形)、便利ですよね! “I like swimming.” みたいに、動詞を名詞みたいに使えるのはとっても助かります。でも、”I don’t like his singing.” (私は彼の歌が好きじゃない) とか、”Thank you for coming.” (来てくれてありがとう) のように、動名詞の前に “his” とか、時には何も付いていない時があって、「あれ?この singing って誰が歌うこと?」「coming って誰が来たこと?」って、動作主が誰なのか迷ってしまうこと、ありませんか?
動名詞が表す動作を「誰が」するのかを示すのが「意味上の主語」という考え方です。そして、その示し方には「所有格(my, his, Ken’sなど)」を使う方法と「目的格(me, him, Kenなど)」を使う方法があって、どっちを使えばいいのか混乱しがち…。この記事では、そんな動名詞の意味上の主語について、基本的な考え方から、所有格と目的格の使い分け、省略されるケースまで、初心者の方にも「なるほど!」と分かるように、例文たっぷりで徹底解説していきます!これを読めば、動名詞の意味上の主語のモヤモヤが解消し、より正確な英語が使えるようになりますよ!
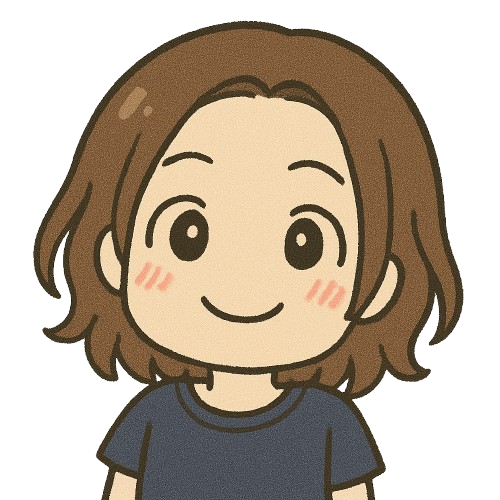
意味上の主語…?動名詞にも主語があるんですか? his singing とか言われてもピンとこないです…。
動名詞の意味上の主語って何?基本の考え方を理解しよう
まずは、「動名詞の意味上の主語」という考え方そのものが何なのか、なぜ必要なのか、基本的なところからしっかり押さえていきましょう。ここが理解できれば、具体的な使い分けもスムーズに頭に入ってきます。
動名詞のおさらい:「~すること」を表す名詞の働き
本題に入る前に、動名詞の基本を少しだけ復習しましょう。
動名詞 (Gerund) とは、「動詞の原形 + ing」の形で、文の中で名詞と同じ働きをするものでしたね。意味は基本的に「~すること」と訳されます。
- 例: Reading books is my hobby. (本を読むことは私の趣味です。) ← 主語(S)
- 例: I enjoy watching movies. (私は映画を見ることを楽しみます。) ← 目的語(O)
- 例: My favorite pastime is listening to music. (私の好きな気晴らしは音楽を聴くことです。) ← 補語(C)
- 例: Thank you for helping me. (私を手伝ってくれることに感謝します。) ← 前置詞 for の目的語
このように、動名詞は「~ing」の形をとりながら、文の中では名詞として扱われる、便利な表現でした。
意味上の主語とは?動名詞の動作主は誰?
さて、動名詞は元々動詞ですから、「~する」という動作や行為の意味を含んでいますよね。例えば “singing” なら「歌うこと」です。
ここで疑問になるのが、「じゃあ、その『歌う』っていう動作は、一体『誰が』するの?」ということです。文によっては、文脈から明らかだったり、特に誰かを特定する必要がなかったりする場合もありますが、「誰が~すること」なのかをはっきり示したい場合もたくさんあります。
この、動名詞が表す動作を実際に行う人やモノのことを、文法用語で「意味上の主語 (Subject of the Gerund)」と呼びます。形の上では文の主語(S)とは違うかもしれないけれど、「意味の上では」その動名詞の動作主である、ということですね。
例:
- “I remember singing this song.” (私はこの歌を歌ったことを覚えている。)
- → 「歌った」のは誰? → 文の主語と同じ「私 (I)」ですね。この場合、意味上の主語は I です。
- “Do you mind my singing this song?” (私がこの歌を歌うことは気に障りますか? → 私が歌ってもいいですか?)
- → 「歌う」のは誰? → 「私 (my)」ですよね。この場合、意味上の主語は my (I) です。
- このように、文の主語 (You) と動名詞 singing の意味上の主語 (my) が違う場合、意味上の主語を明示する必要が出てくるわけです。
なぜ意味上の主語を示す必要があるの?
意味上の主語をわざわざ示す必要があるのは、主に以下のような理由からです。
- 文の主語と動名詞の動作主が違う場合: 上の “Do you mind my singing?” の例のように、文の主語とは別の誰か(何か)が動名詞の動作をする場合に、誰がするのかを明確にするために必要です。
- 意味を正確に伝えたい場合: 例えば “I appreciate your help.” (あなたの助けに感謝します) の help は名詞ですが、動名詞を使って「あなたが手伝ってくれたこと」に感謝したい場合は “I appreciate your helping me.” のように、誰が助けてくれたのかをはっきりさせる方がより正確です。
- 誤解を避けたい場合: 意味上の主語を明示しないと、誰がその動作をするのか曖昧になったり、誤解されたりする可能性がある場合に示します。
つまり、動名詞の意味上の主語は、動名詞が表す「~すること」という行為を「誰が(何が)するのか」を特定し、文の意味をより明確にするために重要な要素なんですね。
では、具体的にどうやって意味上の主語を示せばいいのでしょうか? 次のセクションで詳しく見ていきましょう!
不定詞にも「意味上の主語」がありましたが、動名詞にもあるんですね!考え方は似ていますが、示し方が少し違うので注意が必要です。

動名詞にも「誰がするのか」を示す必要があるんですね!言われてみれば確かに…。 “my singing” とか、そういうことだったのか!
動名詞の意味上の主語の示し方:所有格?それとも目的格?
動名詞の意味上の主語をどうやって示すのか、ここが今回の最重要ポイントです!主に「所有格」を使う方法と「目的格」を使う方法があり、どちらを使うべきか、ルールとニュアンスの違いをしっかり理解しましょう。
原則は「所有格」! my, your, his, her, its, our, their, 名詞’s
動名詞の意味上の主語を示す際の最も正式で、伝統的な文法ルールは、「所有格」を使うというものです。
【所有格とは?】
「~の」という意味を表す形ですね。
- 代名詞の所有格: my (私の), your (あなたの), his (彼の), her (彼女の), its (それの), our (私たちの), their (彼らの/彼女らの/それらの)
- 名詞の所有格: 名詞 + ‘s (例: Ken’s, my father’s, the cat’s)
これらの所有格を、動名詞の直前に置くことで、「誰が~すること」なのかを示します。
【形】
[所有格] + [動名詞 (-ing)]
【例文】
- I am proud of my son’s winning the prize. (私は息子がその賞を獲得したことを誇りに思う。)
- winning (獲得すること) の意味上の主語は my son なので、所有格 my son’s を前に置く。
- Do you mind my smoking here? (私がここでタバコを吸うことは気に障りますか? → 吸ってもいいですか?)
- smoking (吸うこと) の意味上の主語は I なので、所有格 my を前に置く。
- She complained about his being late. (彼女は彼が遅刻したことについて不平を言った。)
- being late (遅刻すること) の意味上の主語は he なので、所有格 his を前に置く。※動名詞 being の例
- We celebrated their passing the exam. (私たちは彼らが試験に合格したことを祝った。)
- passing (合格すること) の意味上の主語は they なので、所有格 their を前に置く。
- Is there any chance of our team’s winning the championship? (私たちのチームが選手権で優勝する可能性はありますか?)
- winning (優勝すること) の意味上の主語は our team なので、所有格 our team’s を前に置く。
このように、フォーマルな場面や書き言葉、文法的に正確さを期す場合は、動名詞の意味上の主語は所有格で示すのが基本ルールとされています。
口語では「目的格」もOK! me, you, him, her, it, us, them, 名詞
しかし、特にインフォーマルな会話(話し言葉)では、動名詞の意味上の主語として、所有格の代わりに「目的格」が使われることも非常に多いんです。
【目的格とは?】
動詞や前置詞の目的語になる形ですね。
- 代名詞の目的格: me (私を/に), you (あなたを/に), him (彼を/に), her (彼女を/に), it (それを/に), us (私たちを/に), them (彼らを/に など)
- 名詞: 目的格も主格と同じ形 (例: Ken, my father, the cat)
これらの目的格(または名詞)を、動名詞の直前に置きます。
【形】
[目的格 / 名詞] + [動名詞 (-ing)]
【例文】
- I appreciate you helping me. (あなたが私を手伝ってくれたことに感謝します。)
- 所有格なら “your helping”。口語では “you helping” もよく使われる。
- Do you mind me asking a personal question? (私が個人的な質問をすることは気に障りますか?)
- 所有格なら “my asking”。口語では “me asking” も一般的。
- What do you think about him joining our team? (彼が私たちのチームに参加することについてどう思いますか?)
- 所有格なら “his joining”。口語では “him joining” も使われる。
- There is no chance of Ken winning the race. (ケンがそのレースで勝つ見込みはない。)
- 所有格なら “Ken’s winning”。名詞の場合は目的格でも形は同じだが、所有格を使わないことが多い。
このように、特に話し言葉では、所有格よりも目的格の方が自然に聞こえると感じるネイティブスピーカーも多いようです。文法的には所有格がより正しいとされますが、目的格も広く使われているのが現状です。
所有格 vs 目的格:使い分けのポイントと注意点
では、所有格と目的格、どちらを使えばいいのでしょうか? 使い分けのポイントと注意点を整理しましょう。
【基本的な使い分け】
- フォーマルな書き言葉、文法的な正確さを重視する場合: → 所有格を使うのが望ましい。(my doing, Ken’s doing)
- インフォーマルな会話(話し言葉): → 目的格も広く使われ、より自然に聞こえることが多い。(me doing, Ken doing)
【どちらを使うか迷ったら?】
テストやフォーマルな文章では所有格を使うのが無難です。しかし、会話では目的格も問題なく使えます。どちらが絶対的に正しいというよりは、文脈やフォーマル度によって使い分けられる、と理解しておくと良いでしょう。
【注意点】
- 意味上の主語が「無生物」の場合: 無生物(物や事柄)が意味上の主語になる場合、所有格 (‘s) はあまり使われず、目的格(名詞の形)または “of + 名詞” を使うのが普通です。
- 〇 I was surprised at the news arriving so late. (その知らせがそんなに遅く届いたことに驚いた。) (目的格)
- △ I was surprised at the news’s arriving so late. (所有格 ‘s は不自然)
- 〇 What is the chance of the plan succeeding? (その計画が成功する見込みはどのくらいですか?) (“of” を使う形)
- 意味上の主語が長い句の場合: 意味上の主語が「名詞 + 修飾語句」のように長くなる場合、所有格 (‘s) を付けるのが不自然になるため、目的格(名詞句そのまま)を使うのが一般的です。
- 〇 I remember the tall man standing by the door. (ドアのそばに立っていた背の高い男性のことを覚えている。)
- × I remember the tall man’s standing by the door. (不自然)
- 動名詞が文の主語になる場合: 動名詞句全体が文の主語になる場合、意味上の主語は所有格で示すのがより標準的とされています。
- 〇 His being late caused the problem. (彼が遅刻したことが問題を引き起こした。)
- △ Him being late caused the problem. (口語では使われることもあるが、書き言葉では避けるのが無難)
- 動名詞の意味を強調したい場合: 目的格を使うと、意味上の主語(人や物)そのものに焦点が当たりやすく、所有格を使うと、動名詞が表す「行為」の方に焦点が当たりやすい、という微妙なニュアンスの違いを指摘する人もいます。(例: I saw him running. vs I saw his running. 後者は「彼が走っている様子」を強調)ただし、これは微妙な差であり、常に意識する必要はないでしょう。
所有格と目的格の使い分けは、ネイティブの間でも揺れが見られる部分であり、完全に厳密なルールがあるわけではありません。まずは「基本は所有格、口語では目的格もよく使う」という点を押さえておけば大丈夫です。
TOEICなどの文法問題では、フォーマルな文脈が多いため、動名詞の意味上の主語は「所有格」を選ぶのが正解とされる可能性が高いです。
所有格と目的格、どっちを使うか迷います…。テストでは所有格の方がいいんですね?
そうですね、文法的な正確さが求められるテストやフォーマルな文章では、所有格を使うのが一番安全です。ただ、実際の会話では目的格が本当に普通に使われているので、「間違い」と決めつけずに、そういう使い方もあるんだな、と知っておくことが大切だと思いますよ。両方の形に慣れておくのが理想ですね!

所有格が基本だけど、目的格もよく使うんですね!使い分けの注意点も分かりやすかったです!これで迷わずに済みそう!
動名詞の意味上の主語が「省略」されるケースとは?
動名詞の前にいつも所有格や目的格が付いているわけではありませんよね? 意味上の主語が示されていないように見えることもよくあります。それは、意味上の主語が省略されている場合です。どんな時に省略されるのか、主なケースを見ていきましょう。
① 文の主語(S)と一致する場合
動名詞の意味上の主語が、その文全体の主語(S)と同じ場合は、わざわざ示す必要がないため、通常は省略されます。これは最も一般的な省略パターンです。
【例文】
- I enjoy reading novels. (私は小説を読むことを楽しむ。)
- 楽しむのも(S)、読むのも(意味上の主語)、「私(I)」なので省略。 (× I enjoy my reading novels.)
- She is good at playing the piano. (彼女はピアノを弾くことが上手だ。)
- 上手なのも(S)、弾くのも(意味上の主語)、「彼女(She)」なので省略。 (× She is good at her playing the piano.)
- He stopped smoking last year. (彼は去年タバコを吸うのをやめた。)
- やめたのも(S)、吸っていたのも(意味上の主語)、「彼(He)」なので省略。
- Practicing every day is important. (毎日練習することは重要だ。)
- この場合、練習するのが誰かは文脈によりますが、文の主語(Practicing)の動作主は特に示されていません。
文の主語と同じ動作主について話していると文脈から明らかな場合は、意味上の主語を繰り返す必要はないんですね。
② 文の目的語(O)と一致する場合(特定の動詞)
特定の動詞の後ろで、文の目的語(O)が動名詞の意味上の主語と一致する場合も、意味上の主語は示されません。ただし、これは限られた動詞(excuse, forgive, pardon など)で見られる少し特殊なパターンです。
【例文】
- Please excuse me for being late. (私が遅刻したことをお許しください。)
- 許す相手(O)は「私(me)」、遅刻した(being late)のも「私」。目的語 me が意味上の主語を兼ねている。
- (※ Please excuse my being late. と所有格を使う形も可能ですが、目的語を置く形の方が普通です。)
- Forgive him for saying such a thing. (彼がそんなことを言ったのを許してあげてください。)
- 許す相手(O)は「彼(him)」、言った(saying)のも「彼」。
このパターンは、動名詞の意味上の主語を目的格で示す形(例: excuse me being late)と似ていますが、excuse や forgive などの動詞が「人 for 行為」という形をとるために、このような構造になります。
③ 一般の人々を指す場合 (People in general)
動名詞の動作主が、特定の誰かではなく、世間一般の人々(we, you, people, one など)を指す場合も、意味上の主語は通常省略されます。
【例文】
- Smoking is prohibited here. (ここでは喫煙は禁止されている。)
- 誰が喫煙することが禁止されているか? → 一般の人々。なので意味上の主語は省略。
- Seeing is believing. (見ることは信じることだ。→百聞は一見にしかず)
- 誰が見て、誰が信じるのか? → 一般的に人々が。
- Learning a new language takes time. (新しい言語を学ぶことには時間がかかる。)
- 誰が学ぶのか? → 一般的に言語を学ぶ人が。
主語が誰であっても当てはまるような、一般的な事柄について述べる場合は、わざわざ意味上の主語を示す必要はないんですね。
④ 文脈から明らかな場合
文の主語や目的語と一致しなくても、会話の流れや前後の文脈から、動名詞の動作主が誰(何)であるかが明らかな場合は、意味上の主語が省略されることもあります。
【例文】
- Thank you for coming today. (今日は来てくれてありがとう。)
- 誰が来たのか? → 会話の相手である「あなた (you)」であることは明らか。なので “your coming” としなくても意味は通じる。
- How about going for a walk? (散歩に行くのはどうですか?)
- 誰が行くのか? → 話し手と聞き手である「私たち (us)」であることが多い。文脈によるが、通常省略される。
- This book is worth reading. (この本は読む価値がある。)
- 誰が読むのか? → 本を読むであろう一般の人々、または聞き手。省略されるのが普通。
特に口語では、文脈で分かることは省略される傾向が強いですね。
このように、動名詞の意味上の主語は、必ずしも常に示されるわけではなく、文脈や状況に応じて省略されることも多い、ということを覚えておきましょう。
意味上の主語を省略するかどうか迷ったら、「省略しても誰が動作主か誤解なく伝わるか?」を考えてみると良いでしょう。もし曖昧になる可能性があるなら、所有格や目的格で明示した方が親切です。
まとめ:動名詞の意味上の主語を理解して正確な英語へ!
今回は、動名詞を使う上で重要な「意味上の主語」について、その基本的な考え方から、所有格と目的格による示し方、使い分け、そして省略されるケースまで詳しく解説してきました。最後に、今回の学習ポイントを整理して、知識を確実にしましょう!
- 動名詞の意味上の主語とは: 動名詞(~ing形)が表す動作を「誰が(何が)するのか」を示す言葉。
- なぜ必要か: 文の主語と動作主が違う場合や、意味を明確にしたい場合に必要。
- 意味上の主語の示し方:
- 原則: 所有格 (my, your, his, her, its, our, their, Ken’s など) を動名詞の前に置く。
- フォーマルな場面、書き言葉、文法的な正確さを重視する場合に適している。
- 口語・インフォーマル: 目的格 (me, you, him, her, it, us, them, Ken など) も動名詞の前に非常によく使われる。
- 会話ではこちらの方が自然に聞こえることも多い。
- 使い分け: 場面やフォーマル度で判断。テストでは所有格が無難。無生物や長い句が主語の場合は目的格が普通。
- 原則: 所有格 (my, your, his, her, its, our, their, Ken’s など) を動名詞の前に置く。
- 意味上の主語が省略されるケース:
- 文の主語と一致する場合。
- 文の目的語と一致する場合 (excuse O for doing など)。
- 一般の人々を指す場合。
- 文脈から明らかな場合。
- ポイント: 動名詞の前に所有格や目的格があれば、それが意味上の主語!省略されている場合は、文脈から誰が動作主かを考える。
動名詞の意味上の主語は、少し細かい文法事項のように思えるかもしれませんが、これを正しく理解し、使いこなせるようになると、誰が何をしたのかを明確に伝えることができ、より正確で自然な英語表現が可能になります。
特に、所有格と目的格の使い分けは、フォーマルさとインフォーマルさのニュアンスの違いにも関わってきます。まずは基本ルールをしっかり押さえ、たくさんの例文に触れる中で、実際の使われ方に慣れていくことが大切です。動名詞の意味上の主語をマスターして、あなたの英語力をさらに向上させましょう!

意味上の主語、スッキリしました!所有格と目的格の使い分けも、省略されるパターンもよく分かりました!これからは意識して使ってみます!

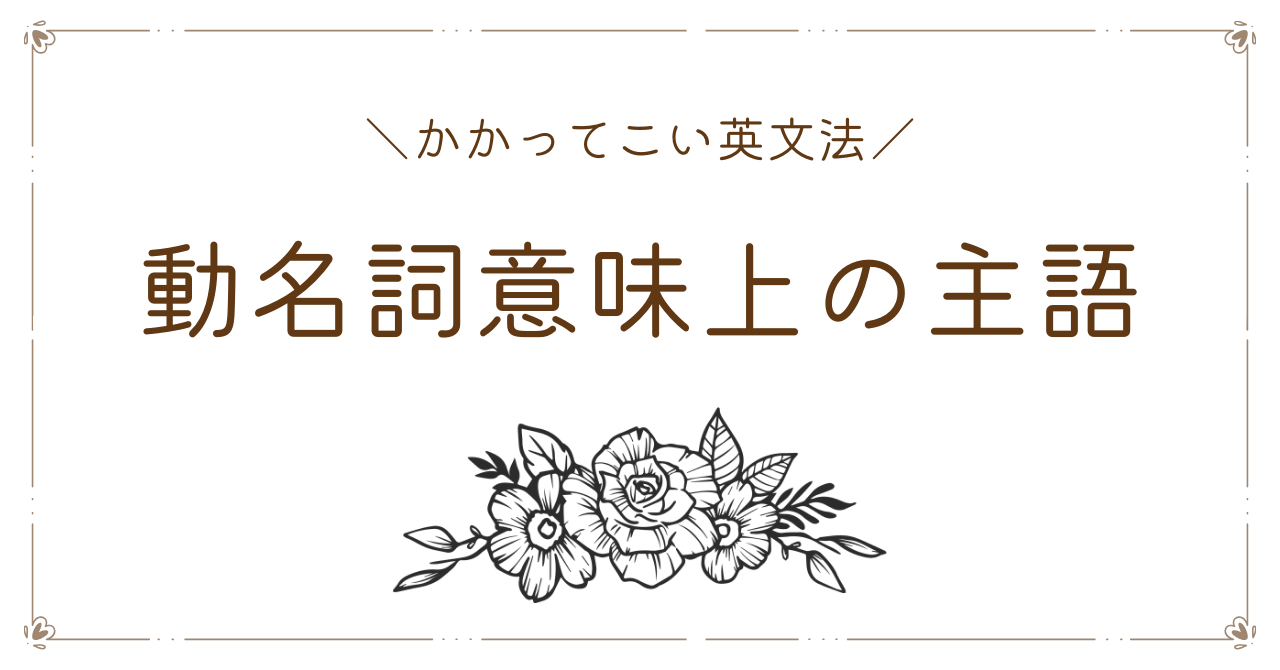
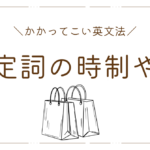
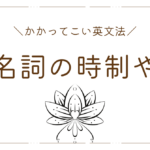
コメント