英語の勉強を始めると、必ずと言っていいほど耳にする「5文型」。SVOCなんていうアルファベットの組み合わせが出てきて、「なんだか難しそう…」「これって本当に覚える必要あるの?」なんて感じている方もいるかもしれませんね。学校で習った記憶はあるけれど、正直よく分からなかった…という経験、私も昔ありました。
でも実は、この英語の5文型というのは、英文の基本的な骨組みを理解するための、とっても大切な地図なんです! これが分かると、複雑に見える英文もスッキリ整理できて、読むスピードも正確さもぐんとアップします。この記事では、そんな英語の基本的な構造である5つの文型(SV, SVC, SVO, SVOO, SVOC)について、それぞれの特徴や見分け方、そしてなぜ学ぶことが大切なのかを、たくさんの例文と一緒に、基礎からじっくり、丁寧に解説していきます。これを読めば、あなたも5文型マスターに一歩近づけるはずです!

5文型って、学校で習ったけど難しかった記憶が… SVOCとか、記号ばかりでよく分からなかったんだよね…。
英語の基礎!そもそも5文型って何?なぜ重要?
英文法の学習において、避けては通れない「5文型」。まずは、この5文型が一体何なのか、そしてなぜそれを学ぶことが英語力アップにつながるのか、基本的なところから確認していきましょう。
5文型とは? – 英語の文の基本的な5つのパターン
英語の「文型」というのは、簡単に言うと、英語の文がどのような語順で組み立てられているか、その基本的なパターンを分類したものです。ほとんどの英文は、その構造によって、以下の5つの種類のどれかに当てはめることができるんです。
- 第1文型 (SV)
- 第2文型 (SVC)
- 第3文型 (SVO)
- 第4文型 (SVOO)
- 第5文型 (SVOC)
このS, V, O, C というアルファベットは、文を構成する要素を表しています。
- S (Subject): 主語 – 文の主体。「~は」「~が」にあたる部分。
- V (Verb): 動詞 – 主語の動作や状態を表す。「~する」「~である」にあたる部分。
- O (Object): 目的語 – 動詞の動作が及ぶ対象。「~を」「~に」にあたる部分。名詞や代名詞がなる。
- C (Complement): 補語 – 主語(S)や目的語(O)が「どのようなもの・状態か」を説明する語。名詞や形容詞がなる。
(※これらに加えて、文を修飾する M (Modifier): 修飾語 という要素もありますが、これは文の骨格となる文型要素には通常含めません。)
なぜ英語の文がこの5つのパターンに分類できるかというと、それは文の中心となる「動詞(V)」の性質(どんな意味で、後ろにどんな要素を必要とするか)によって、文の形が決まるからなんです。例えば、「run(走る)」のような動詞は主語だけで意味が成り立つことが多いですが、「eat(食べる)」のような動詞は「何を」食べるのか目的語が必要になりますよね。このように、動詞の性格に合わせて文の構造が決まってくる、というわけです。
5文型を学ぶことは、いわば英文の「設計図」を読むスキルを身につけるようなものです。この設計図が読めれば、どんなに部品(単語)が多くても、全体の構造を正確に理解できるようになります。
なぜ5文型を学ぶの? – 学習するメリットを解説
「でも、文のパターンを覚えるのって面倒くさそう…」と思うかもしれません。しかし、5文型を理解することには、英語学習においてたくさんのメリットがあるんです!
- 英文の構造が正確に把握できる: 文の骨組み(S, V, O, C)が明確になり、複雑な文でも意味を取り違えにくくなります。特に、関係詞や分詞などで修飾されて長くなった文を読むときに威力を発揮します。
- 読解スピードと精度が向上する: 文の構造を瞬時に見抜けるようになると、どこが重要な情報か素早く判断でき、読むスピードが上がります。また、意味を正確に捉えられるようになります。
- 正しい英作文ができるようになる: どの動詞がどの文型をとるのかを知ることで、語順のミスが減り、より自然で正確な英文を書けるようになります。単語をただ並べるのではなく、正しい「型」にはめて文を作る意識が身につきます。
- 動詞の語法(使い方)が身につく: 5文型は動詞の性質に基づいているため、文型を学ぶことは動詞の正しい使い方を学ぶことと直結します。「この動詞は目的語が2つ必要だな」「この動詞の後ろには形容詞が来るんだな」といった感覚が養われます。
- TOEICなどの試験対策にも有効: 文法問題はもちろん、長文読解問題でも、文構造を素早く正確に把握する力は非常に重要です。5文型の知識は、試験のスコアアップにも貢献します。
5文型は、単なる文法知識の暗記ではなく、英語を正確に読み、書き、理解するための実践的なツールだと言えるでしょう。英語の基礎体力作りのようなものですね。
5文型を見分けるための重要ポイント – V, O, Cの役割
5つの文型を正しく見分けるためには、文の要素、特に「動詞(V)」「目的語(O)」「補語(C)」の役割をしっかり理解しておくことが大切です。
動詞(V)の種類の重要性
文型を決定づける最も重要な要素は動詞(V)です。動詞には大きく分けて2つの種類があります。
- 自動詞 (Intransitive Verb): 目的語(O)を必要としない動詞。その動詞だけで意味がある程度完結する。「走る(run)」「寝る(sleep)」「着く(arrive)」など。主に第1文型、第2文型で使われます。
- 他動詞 (Transitive Verb): 目的語(O)を必要とする動詞。「~を」にあたる言葉がないと意味が不完全になる。「食べる(eat)」「読む(read)」「作る(make)」など。主に第3文型、第4文型、第5文型で使われます。
動詞が自動詞か他動詞かによって、後ろに目的語(O)が来るかどうかが決まります。これが文型を見分ける第一歩です。
目的語(O)とは?
目的語(O)は、動詞(V)の動作の対象となる語で、「~を」「~に」と訳されることが多いです。目的語になれるのは、名詞または代名詞(またはそれに相当する語句)です。他動詞の後ろに置かれます。
例: I read a book. (私は本を読む。) → “a book” が read の目的語(O)。
補語(C)とは?
補語(C)は、主語(S)または目的語(O)が「どのようなもの・状態か」を説明(補足)する語です。「Complement(補うもの)」という名前の通り、それがないと文の意味が不完全になる場合があります。補語になれるのは、主に名詞または形容詞(またはそれに相当する語句)です。
- 主格補語 (Subject Complement): 主語(S)を説明する補語。第2文型(SVC)で使われる。 S = C の関係が成り立つ。
- 目的格補語 (Object Complement): 目的語(O)を説明する補語。第5文型(SVOC)で使われる。 O = C の関係が成り立つ。
例: She is a doctor. (彼女は医者です。) → “a doctor” が主語 She を説明する主格補語(C)。 (She = a doctor)
例: The news made me happy. (その知らせは私を幸せにした。) → “happy” が目的語 me を説明する目的格補語(C)。 (me = happy)
OとCの見分け方
特に第2文型(SVC)のCと第3文型(SVO)のO、そして第4文型(SVOO)のO2と第5文型(SVOC)のCは混同しやすいので注意が必要です。見分けるための最大のポイントは、「イコール関係」が成り立つかどうかです。
- 第2文型 (SVC) → S = C (主語と補語がイコール、または主語の状態を説明)
- 第3文型 (SVO) → S ≠ O (主語と目的語はイコールではない)
- 第4文型 (SVOO) → O1 ≠ O2 (1つ目の目的語と2つ目の目的語はイコールではない)
- 第5文型 (SVOC) → O = C (目的語と補語がイコール、または目的語の状態を説明)
この「イコール関係」を意識することで、文型判断の精度がぐっと上がりますよ!

なるほど、動詞の種類(自動詞か他動詞か)と、OやCが前の語とイコール関係になるかどうかが文型を決める鍵なんだ! ちょっと分かってきたかも!
例文で学ぶ!5文型のそれぞれの形と見分け方を徹底解説
それでは、いよいよ5つの文型それぞれについて、具体的な形と意味、そして見分け方のポイントを例文を交えながら詳しく見ていきましょう!
第1文型 (SV) – 「SがVする」【主語 + 動詞】
- 構造: S + V
- 特徴: 最もシンプルな文型。動詞(V)は自動詞で、目的語(O)も補語(C)も必要としない。
- 意味: 「主語が(自分で)~する」「主語が存在する/移動する」など、主語の動作や存在を表す。
例文を見てみましょう。
- Birds sing. (S+V)
(鳥が歌う。) - He runs. (S+V)
(彼は走る。) - The sun rises. (S+V)
(太陽が昇る。) - I live in Tokyo. (S+V+M)
(私は東京に住んでいます。)
※ “in Tokyo” は場所を表す副詞句(M)で、文型要素には含めません。文の骨格は S+V です。 - She arrived at the station on time. (S+V+M+M)
(彼女は時間通りに駅に到着した。)
※ “at the station” (場所) や “on time” (時) は副詞句(M)です。
第1文型は、動詞の後ろに何も続かないこともありますが、例文のように副詞(句)(M)を伴うことが非常に多いです。副詞(M)は、時・場所・様態(どのように)などの情報を付け加えますが、文の骨格(文型)を判断する際には除外して考えましょう。「~を」「~に」にあたる名詞(O)や、Sとイコール関係になる名詞・形容詞(C)がなければ、第1文型と判断できます。
第2文型 (SVC) – 「SはCである/~になる」【主語 + 動詞 + 補語】
- 構造: S + V + C
- 特徴: 動詞(V)は主語(S)と補語(C)を結びつける役割を持つ(連結動詞 Linking Verb とも呼ばれる)。代表的なのはbe動詞。S = C の関係が成り立つ。
- C(補語)になれる品詞: 名詞 または 形容詞。
- 意味: 「主語は補語(の状態)である」「主語は補語になる」など、主語の性質・状態・変化を表す。
例文で確認しましょう。
- She is a pianist. (S+V+C)
(彼女はピアニストです。)
→ C = 名詞。 She = a pianist の関係が成り立ちますね。 - He looks happy. (S+V+C)
(彼は幸せそうに見える。)
→ C = 形容詞。 He = happy な状態、ということです。 - My dream became true. (S+V+C)
(私の夢は現実になった。)
→ C = 形容詞。 My dream = true な状態になった、という意味。 - This soup tastes delicious. (S+V+C)
(このスープはおいしい味がする。)
→ C = 形容詞。 This soup = delicious な味、ということです。 - The leaves turned red. (S+V+C)
(葉は赤くなった。)
→ C = 形容詞。 The leaves = red な状態に変化した、という意味。
第2文型で使われる代表的な動詞には以下のようなものがあります。
- be動詞: am, are, is, was, were
- ~になる: become, get, grow, turn, go, come, fall
- ~のままである: remain, keep, stay, lie
- ~に見える/思える: look, seem, appear
- 五感に関する動詞: feel, taste, smell, sound
SVCのCとSVOのOって、どっちも動詞の後ろに名詞が来ることがあるから、見分けにくい気がするんだけど…。
良いところに気づきましたね! 見分ける最大のコツは、先ほども触れた「S = C」の関係が成り立つかどうかです。
例えば、”She is a pianist.” (SVC) では「She = a pianist」が成り立ちます。
一方、”She plays the piano.” (SVO) では「She = the piano」は成り立ちませんよね? ピアノは彼女が演奏する対象(O)です。
動詞の後ろの名詞が、主語(S)とイコール関係にあればC(第2文型)、イコール関係でなければO(第3文型)と判断できます。
第3文型 (SVO) – 「SがOをVする」【主語 + 動詞 + 目的語】
- 構造: S + V + O
- 特徴: 動詞(V)は他動詞で、動作の対象となる目的語(O)を必要とする。S ≠ O の関係。
- O(目的語)になれる品詞: 名詞 または 代名詞(またはそれに相当する句や節)。
- 意味: 「主語が目的語を~する」という、動作が対象に及ぶことを表す最も一般的な形の一つ。
例文を見てみましょう。
- I like apples. (S+V+O)
(私はリンゴが好きです。)
→ O = 名詞。 私 ≠ リンゴ ですね。 - He reads a newspaper every morning. (S+V+O+M)
(彼は毎朝新聞を読みます。)
→ O = 名詞句。”every morning” は時を表す副詞句(M)。 彼 ≠ 新聞 です。 - We enjoyed the party very much. (S+V+O+M)
(私たちはそのパーティーをとても楽しみました。)
→ O = 名詞句。”very much” は程度を表す副詞句(M)。 私たち ≠ パーティー です。 - She knows him well. (S+V+O+M)
(彼女は彼をよく知っています。)
→ O = 代名詞。”well” は様態を表す副詞(M)。 彼女 ≠ 彼 です。
第3文型は英語で最もよく使われる文型の一つです。多くの他動詞がこの形をとります。動詞の後ろに名詞(代名詞)があり、それが主語とイコール関係でなければ、第3文型と判断できます。
第4文型 (SVOO) – 「SがO1にO2をVする」【主語 + 動詞 + 目的語1 + 目的語2】
- 構造: S + V + O1 + O2
- 特徴: 動詞(V)は「与える」系の意味を持つ他動詞(授与動詞)で、目的語を2つ取る。O1(間接目的語)は通常「人」、O2(直接目的語)は通常「物・事」を表すことが多い。O1 ≠ O2 の関係。
- 意味: 「主語が(O1)に(O2)を~する」という意味を表す。
例文を見てみましょう。
- My mother gave me this watch. (S+V+O1+O2)
(母は私に この腕時計をくれた。)
→ O1 = me (人), O2 = this watch (物)。 私 ≠ この腕時計 ですね。 - He teaches us mathematics. (S+V+O1+O2)
(彼は私たちに 数学を教えている。)
→ O1 = us (人), O2 = mathematics (事)。 私たち ≠ 数学 です。 - Can you show me the way to the station? (S+V+O1+O2)
(私に駅までの道を教えてくれませんか?)
→ O1 = me (人), O2 = the way (事)。 私 ≠ 道 です。 - My father bought me a new bicycle. (S+V+O1+O2)
(父は私に 新しい自転車を買ってくれた。)
→ O1 = me (人), O2 = a new bicycle (物)。 私 ≠ 新しい自転車 です。
第4文型を取る代表的な動詞(授与動詞)には、give, teach, show, tell, send, lend, offer, pay, bring, pass などがあります。また、buy, make, cook, find, get, choose, sing など、「(人の)ために~してあげる」という意味合いを持つ動詞も第4文型をとることがあります。
第3文型への書き換え
第4文型 (SVO1O2) は、多くの場合、第3文型 (SVO2 + 前置詞 + O1) の形に書き換えることができます。
例:
- My mother gave me this watch. (SVOO) → My mother gave this watch to me. (SVO + to + O)
- He teaches us mathematics. (SVOO) → He teaches mathematics to us. (SVO + to + O)
- My father bought me a new bicycle. (SVOO) → My father bought a new bicycle for me. (SVO + for + O)
- She asked me a question. (SVOO) → She asked a question of me. (SVO + of + O)
書き換えの際に使う前置詞は、動詞によって異なります。
・to を使う動詞: give, teach, show, tell, send, lend, offer, pay など(相手に到達するイメージ)
・for を使う動詞: buy, make, cook, find, get, choose, sing など(相手のために何かをするイメージ)
・of を使う動詞: ask (尋ねる)
どの動詞がどの前置詞と結びつくかは、少しずつ覚えていく必要があります。
第5文型 (SVOC) – 「SがOをCの状態にVする」【主語 + 動詞 + 目的語 + 補語】
- 構造: S + V + O + C
- 特徴: 動詞(V)は特定の他動詞。目的語(O)と、その目的語を説明する補語(C)を必要とする。O = C の関係が成り立つ。
- C(目的格補語)になれる品詞: 名詞, 形容詞 が基本。動詞によっては、動詞の原形, 現在分詞(-ing), 過去分詞(-ed) などもCになることがある(これは少し発展的な内容です)。
- 意味: 「主語は目的語が補語であると~する(思う、考えるなど)」「主語は目的語を補語の状態にする(する、させるなど)」という意味を表す。
例文を見てみましょう。
- We call our dog Pochi. (S+V+O+C)
(私たちは私たちの犬をポチと呼びます。)
→ O = our dog, C = Pochi (名詞)。 our dog = Pochi の関係ですね。 - The news made her sad. (S+V+O+C)
(その知らせは彼女を悲しませた。)
→ O = her, C = sad (形容詞)。 her = sad な状態にした、ということです。 - I found the book interesting. (S+V+O+C)
(私はその本が面白いとわかった。)
→ O = the book, C = interesting (形容詞)。 the book = interesting だと思った、という意味。 - Please keep the room clean. (S+V+O+C)
(部屋をきれいにしておいてください。)
→ O = the room, C = clean (形容詞)。 the room = clean な状態を保つ、ということです。 - I saw him cross the street. (S+V+O+C) ※発展
(私は彼が通りを渡るのを見た。)
→ O = him, C = cross (動詞の原形)。 知覚動詞 see の場合、Cに原形不定詞が来ることがあります。彼 = 通りを渡る、という関係。 - She let me use her computer. (S+V+O+C) ※発展
(彼女は私に彼女のコンピューターを使わせてくれた。)
→ O = me, C = use (動詞の原形)。 使役動詞 let の場合、Cに原形不定詞が来ます。私 = コンピューターを使う、という関係。
第5文型を取る代表的な動詞には、以下のようなものがあります。
- OをCと呼ぶ/名付ける: call, name
- OをCの状態にしておく/保つ: keep, leave
- OがCだとわかる/思う/考える: find, think, believe, consider
- OをCの状態にする: make, turn, get, drive
- 知覚動詞(OがCするのを見る/聞く/感じる): see, hear, feel, watch, notice (Cに原形・現在分詞・過去分詞)
- 使役動詞(OにCさせる/してもらう): make, let, have (Cに原形・過去分詞)
第5文型は少し複雑に見えますが、「O = C」の関係(目的語とその説明)を見抜くことができれば、理解しやすくなります。第4文型 (SVOO) では O1 ≠ O2 でしたが、第5文型 (SVOC) では O = C となる点が大きな違いです。
例:
- He found me a good seat. (SVOO) → O1=me, O2=a good seat. me ≠ a good seat. (彼は私によい席を見つけてくれた。)→ 第4文型
- He found the seat empty. (SVOC) → O=the seat, C=empty. the seat = empty. (彼はその席が空いているのを見つけた。)→ 第5文型
このように、同じ動詞でも取る文型によって意味が変わることもあるので注意が必要ですね。

第5文型、ちょっと難しいかも… でも、O=Cの関係がポイントなのね! 知覚動詞とか使役動詞は、また別の機会に詳しく知りたいな!
5文型をマスターするための学習法と注意点
ここまで5つの文型を一つずつ見てきましたが、これらの知識を実際に使えるようにするためには、どんな学習を心がければよいのでしょうか? ここでは、5文型を効果的に身につけるためのヒントと注意点をご紹介します。
文型判断は動詞がカギ!辞書を活用しよう
繰り返しになりますが、文型を決定づけるのは動詞の性質です。英文を読むときや書くときには、常に「この動詞は自動詞かな?他動詞かな?」「後ろに目的語や補語は必要かな?」「もし必要なら、どんな形の目的語や補語が来るのかな?」と意識することが大切です。
自信がないときや、知らない動詞に出会ったときは、面倒くさがらずに辞書を引く習慣をつけましょう。多くの英和辞典には、動詞の語義だけでなく、それが自動詞(vi)か他動詞(vt)か、そしてどの文型(SVC, SVOOなど)を取るのかといった情報が載っています。

辞書で文型情報を確認する癖をつけることで、動詞の正しい使い方を着実に身につけることができます。
複雑な文も基本は5文型!修飾語(M)を見抜く練習
実際の英文は、ここまで見てきたシンプルな例文ばかりではありません。関係代名詞や分詞、前置詞句、副詞句など、様々な修飾語句(M)が付いて、一見複雑に見えることがよくあります。
しかし、どんなに長い文でも、その骨格となっているのは基本的に5文型のどれかです。複雑な文に出会ったら、まずは焦らずに文の核となる主語(S)と動詞(V)を見つけ、次に目的語(O)や補語(C)にあたる部分を探します。そして、それ以外の部分、つまり文の骨格には直接関係ない修飾語(M)を特定し、カッコでくくるなどして区別する練習をすると効果的です。
例:
- The girl [with long hair] bought a beautiful dress [at the new shop] [near the station] [yesterday].
この文の骨格は The girl (S) bought (V) a beautiful dress (O) で、第3文型(SVO)です。 [with long hair] は The girl を修飾する形容詞句、[at the new shop], [near the station], [yesterday] はそれぞれ場所や時を表す副詞(句)(M)ですね。
このように、修飾語(M)を取り除いて文の骨組みを見る練習を繰り返すことで、どんなに長い文でも構造を正確に捉える力が養われます。
暗記ではなく理解!例文で感覚をつかむ
5文型を学ぶ上で大切なのは、SVOCといった記号やパターンをただ暗記するのではなく、それぞれの文型が持つ意味やニュアンスを、具体的な例文を通して感覚的に理解することです。
- 「第1文型は主語が何かをする、存在する感じだな」
- 「第2文型は主語イコール何かって説明する感じ」
- 「第3文型は動作が対象に向かう一番普通の形」
- 「第4文型は誰かに何かをあげる感じ」
- 「第5文型は目的語の状態を説明したり、変化させたりする感じ」
このように、各文型の「コアな意味」をイメージできるようになると、新しい単語や表現に出会ったときも、「これは第〇文型っぽいな」と推測しやすくなります。
また、学んだ知識を定着させるためには、自分で簡単な例文を作ってみるのも非常に効果的です。「この動詞は第4文型も取れるんだな、じゃあ『I bought my sister a book.』みたいに使えるかな?」といった具合に、アウトプットすることで理解が深まります。
5文型の学習は、一朝一夕に完璧になるものではありません。たくさんの英文に触れ、文型を意識する経験を積み重ねる中で、徐々に感覚が磨かれていきます。焦らず、楽しみながら取り組んでいきましょう!

修飾語をカッコでくくるの、分かりやすい! これなら長い文も怖くないかも! 自分で例文を作るのも良さそうだね、やってみよう!
まとめ:5文型を理解して英語の基礎を固めよう!
今回は、英語の文章の基本的な骨組みである「5文型」について、その定義から見分け方、学習のメリットやポイントまで、詳しく解説してきました。最後に、今回の内容を簡潔にまとめておきましょう。
- 英語の文は、その構造によって基本的に以下の5つの文型に分類されます。
- 第1文型 (SV): 主語 + 動詞
- 第2文型 (SVC): 主語 + 動詞 + 補語 (S=C)
- 第3文型 (SVO): 主語 + 動詞 + 目的語 (S≠O)
- 第4文型 (SVOO): 主語 + 動詞 + 目的語1 + 目的語2 (O1≠O2)
- 第5文型 (SVOC): 主語 + 動詞 + 目的語 + 補語 (O=C)
- 文型は、主に動詞(V)の性質(自動詞か他動詞か)と、目的語(O)・補語(C)の有無や関係性によって決まります。
- 目的語(O)は動詞の動作の対象(~を、~に)、補語(C)は主語や目的語の説明(S=C or O=C)。
- 文型を見分けるには、まずSとVを見つけ、次にOとC(特にイコール関係=が成り立つか)を確認し、修飾語(M)を区別することが重要です。
- 5文型を理解するメリットは、英文構造の正確な把握、読解力・英作文力の向上、動詞の語法の習得など、多岐にわたります。
- 学習のポイントは、動詞を意識し辞書を活用すること、修飾語(M)を見抜く練習をすること、単なる暗記ではなく例文を通して感覚をつかむことです。
5文型は、英語という言語の設計図とも言える、非常に重要な基礎知識です。これをしっかり身につけることで、英文の読み書きにおける土台がしっかりと固まります。最初は少し戸惑うこともあるかもしれませんが、この記事で解説したポイントを参考に、ぜひ日々の英語学習の中で5文型を意識してみてください。
複雑に見える英文の構造がクリアに見えてくるようになると、英語学習がもっと楽しく、そして効率的になるはずです。頑張ってくださいね!応援しています!

5文型、しっかり復習できた! SVOCの関係性とか、見分け方のコツがよく分かった! これで英文読解も英作文もレベルアップできそう! 頑張るぞー!

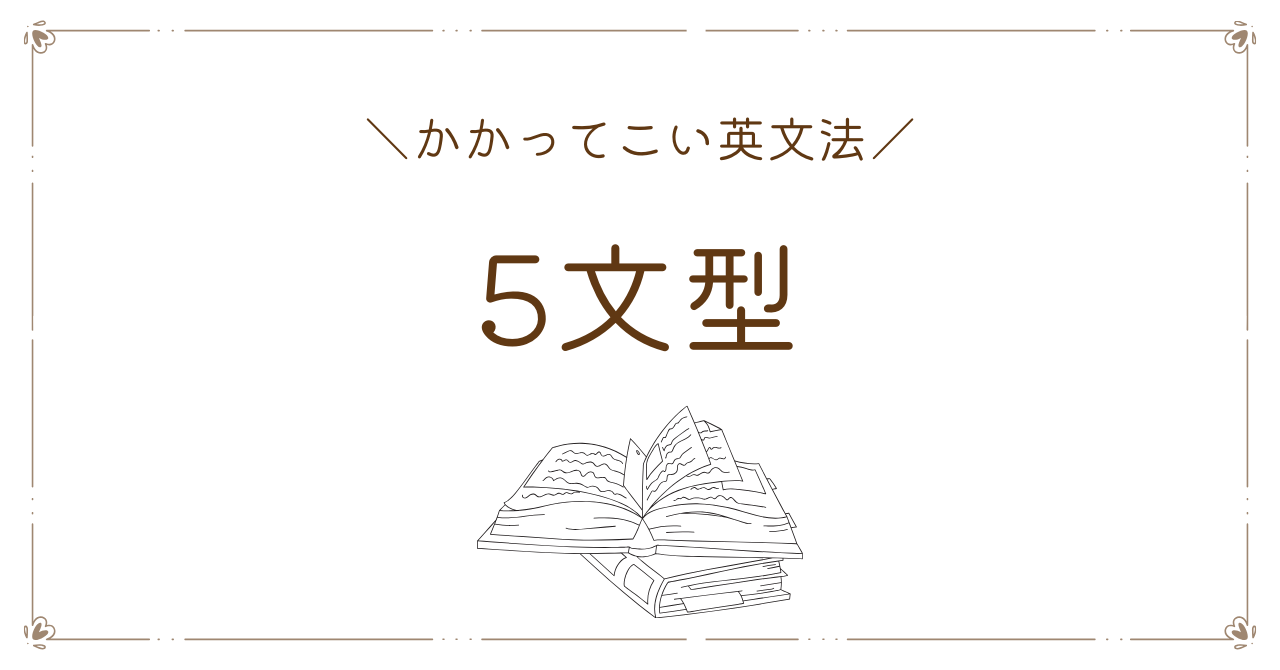
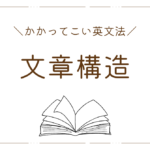
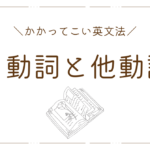
コメント