英語の文章を読んだり、ネイティブの会話を聞いたりしていると、「あれ?なんだか言葉が足りないような…?」と感じること、ありませんか? 実はそれ、英語の「省略構文」が使われているのかもしれません。言わなくてもわかることは省略する、というのは日本語でもよくありますが、英語にも独特の省略のルールがあるんです。英語学習を始めたばかりの方や、中学生、高校生、そしてTOEICなどでより自然な英語表現を目指す皆さんにとって、この省略構文は、最初は少し戸惑うかもしれませんが、慣れるととっても便利なんですよ。
「でも、何がどう省略されるの?」「省略されたら意味がわからなくならない?」そんな不安を感じる方もいるかもしれませんね。大丈夫!この記事では、そんな皆さんのために、英語の省略構文がどんなルールで使われるのか、どんなものが省略されやすいのか、そして省略された文をどう理解すればいいのかを、具体的な例文をたくさん見ながら、一つひとつ丁寧に解説していきます。この記事を読み終わる頃には、きっと省略構文の謎が解け、よりスムーズに英語を理解し、そして自分でも使えるようになっているはずです!

省略って聞くと難しそうだけど、これでスッキリわかるかな?
省略構文の基本ルール – なぜ英語は言葉を省略するの?
まずは、なぜ英語で言葉が省略されるのか、その基本的な考え方と、どんなルールがあるのかを見ていきましょう。「言わなくてもわかることは言わない」という、コミュニケーションの大原則が根底にあるんです。
「言わなくてもわかること」は省略するのが英語の自然な流れ
英語に限らず、どんな言語でも、会話や文章の中で繰り返しになる言葉や、文脈から明らかに推測できる言葉は、省略される傾向があります。これは、コミュニケーションをよりスムーズに、そして簡潔にするためです。何度も同じことを繰り返すと、くどく感じてしまいますよね。
英語では、特に以下のような場合に省略が起こりやすいです。
- 前の文や節で一度出てきた言葉の繰り返しを避けるため。
- 質問に対して答えるとき、質問文にあった言葉を繰り返さないため。
- 比較の文で、共通する部分を省略するため。
- 接続詞の後の主語とbe動詞など、特定のパターンで省略が許されるため。
省略は、話し言葉(口語)で特に多く見られますが、書き言葉(文語)でも、文を簡潔にするために使われます。省略を理解することは、ネイティブの自然な英語表現に近づくための大切な一歩なんですよ。
何が省略されやすい? – 動詞・目的語・補語など様々
では、具体的にどんな言葉が省略されやすいのでしょうか? 実は、文の様々な要素が省略の対象になります。
- 同じ動詞 (または動詞句) の繰り返し
例: A: Do you like coffee? (コーヒーは好き?)
B: Yes, I do. (はい、好きです。) ← Yes, I like coffee. の like coffee が省略。do が代動詞として機能。 - 同じ目的語や補語の繰り返し
例: She can play the piano, and her brother can (play the piano), too. (彼女はピアノが弾けるし、彼女の兄もそうだ。) - to不定詞の後の動詞の原形
例: I wanted to go, but I couldn’t (go). (行きたかったけど、行けなかった。) - that節の中の that (特に目的格の関係代名詞や、一部の接続詞)
例: I think (that) he is right. (彼は正しいと思う。) - 接続詞の後の「主語 + be動詞」
例: While (I was) walking in the park, I saw a cat. (公園を歩いているとき、猫を見た。) - 比較の文での共通部分
例: He is taller than I (am tall). (彼は私より背が高い。)
これらの例を見て、「あ、これ知ってる!」と思ったものもあるかもしれませんね。実は、私たちは無意識のうちにたくさんの省略表現に触れているんです。
省略は、文法的なルールに則って行われるので、何でもかんでも省略していいわけではありません。省略しても文の意味が正しく伝わることが大前提です。だからこそ、どんな場合に何が省略されるのか、そのパターンを知っておくことが大切なんですね。
省略を見抜くコツ – 文脈と文法知識が鍵
省略された文を正しく理解するためには、どうすればいいのでしょうか? ポイントは、文脈をしっかり把握することと、基本的な文法知識を働かせることです。
- 前後の文脈に注目する: 何が省略されているかは、多くの場合、その文の前後にある情報から推測できます。「何が繰り返されているか」「何が共通しているか」を探してみましょう。
- 文の構造を分析する: 「ここには本来動詞があるはずなのにないな…」「目的語がないけど、前の文に出てきたあれのことかな?」というように、文型や品詞の働きといった文法的な知識を使って、省略されている部分を補って考えてみましょう。
- よくある省略パターンを覚えておく:この記事で紹介するような、頻出の省略パターンを知っておけば、「あ、これはあのパターンの省略だな」と気づきやすくなります。
最初は難しく感じるかもしれませんが、たくさんの英文に触れていくうちに、だんだんと「ここは省略だな」と自然にわかるようになってきますよ。パズルのピースをはめるように、省略された言葉を補って意味を理解する楽しさも感じられるようになるはずです。

なるほど~!言わなくてもわかることは省略するんだね。日本語と似てるかも!
よく使われる省略構文のパターン – これだけは押さえよう!
それでは、実際に英語でよく使われる省略構文の具体的なパターンを見ていきましょう。これらをマスターすれば、英語の理解度が格段にアップしますよ!
反復を避けるための省略 – 同じ言葉は繰り返さない!
これが最も一般的な省略の理由です。一度出てきた語句を繰り返すのを避けるために、様々な要素が省略されます。
1. 動詞 (句) の省略 (代動詞 do/does/did の活用)
前の文で使われた動詞(句)が繰り返される場合、その動詞(句)を省略し、代わりに代動詞の do, does, did (または助動詞 can, will, may など) を使うことがよくあります。
- A: Do you like ice cream? (アイスクリームは好きですか?)
B: Yes, I do. (= Yes, I like ice cream.)
No, I don’t. (= No, I don’t like ice cream.) - She studies harder than her brother does. (彼女は兄よりも熱心に勉強する。)
(= … than her brother studies.) - He can swim faster than I can. (彼は私よりも速く泳げる。)
(= … than I can swim.) - A: Will you join us? (私たちに参加しますか?)
B: I’d love to, but I’m afraid I can’t. (ぜひそうしたいのですが、残念ながらできません。)(= … I’m afraid I can’t join you.)
代動詞 do/does/did や助動詞は、前の動詞の内容を「代わりに受ける」働きをするので、文がスッキリしますね。
2. 目的語・補語の省略
文脈から明らかな場合、目的語や補語が省略されることがあります。
- This pen is mine, and that one is yours. (このペンは私ので、あれはあなたのです。)
(= … and that one is your pen.) ← yours は “your pen” を意味する所有代名詞ですが、pen の繰り返しを避けています。 - A: Are you tired? (疲れていますか?)
B: Yes, I am (tired). (はい、疲れています。) - He is not as tall as his father (is tall). (彼は父親ほど背が高くない。)
3. to不定詞の後の動詞の原形の省略 (toの代不定詞)
to不定詞 (to + 動詞の原形) が繰り返される場合、動詞の原形だけを省略して to だけを残すことがあります。これを「代不定詞」と呼びます。
- A: Would you like to come with us? (私たちと一緒に行きませんか?)
B: I’d love to. (= I’d love to come with you.) - You don’t have to apologize if you don’t want to. (もし謝りたくないなら、謝る必要はありませんよ。)
(= … if you don’t want to apologize.) - She asked me to help her, and I promised I would (help her), but I didn’t have time to (help her).
(彼女は私に助けを求めたので、私はそうすると約束したが、助ける時間がなかった。)→ 3箇所で繰り返しが避けられています。
この “to” だけが残る形は、会話でも非常によく使われます。「~したいけど、できない」のような場面で “I want to, but I can’t.” のように言いますね。to の後に動詞がないことに気づけるかがポイントです。
接続詞の後の省略 – 主語とbe動詞が消える?
時 (when, whileなど)、条件 (if, unlessなど)、譲歩 (though, althoughなど) を表す副詞節の中で、主節の主語と同じ主語とbe動詞が続く場合、その「主語 + be動詞」が省略されることがよくあります。
接続詞 + (S’ + be) + ~
- While (I was) walking in the park, I saw an old friend.
(公園を歩いている間に、旧友に会った。)
→ 主節の主語 I と同じなので、I was が省略されています。 - When (you are) in Rome, do as the Romans do. (ことわざ:郷に入っては郷に従え)
(ローマにいるときは、ローマ人のするようにせよ。) - He works hard though (he is) still young.
(彼はまだ若いのだけれども、一生懸命働く。) - The concert will be cancelled if (it is) rainy tomorrow.
(もし明日雨ならば、コンサートは中止になるだろう。) - Be careful when (you are) crossing the street.
(道を渡るときは注意しなさい。)
この省略が起こると、接続詞の直後にいきなり -ing形や過去分詞、形容詞、前置詞句などが続く形になります。最初は少し戸惑うかもしれませんが、省略されている「主語+be動詞」を補って考えると、意味がクリアになりますよ。
「主語 + be動詞」なら何でも省略できるんですか?
いいえ、何でもというわけではありません。主に、副詞節の中で、かつ主節の主語と同じである、という条件が重要です。また、be動詞が本動詞として使われている場合や、進行形・受動態で使われているbe動詞が省略されやすいです。
比較構文での省略 – 比べる相手との共通点は言わない
比較の文 (A is taller than B. など) では、比較している対象の間で共通している部分は省略されるのが普通です。
- He is richer than I am. (彼は私よりも金持ちだ。)
(= He is richer than I am rich.) ← am rich の rich が省略。 - She can run faster than he can. (彼女は彼よりも速く走れる。)
(= She can run faster than he can run.) ← can run の run が省略。 - This book is more interesting than that one. (この本はあの本よりも面白い。)
(= … than that book is interesting.) ← book is interesting が省略され、that one (あの本) で受けています。”one” も一種の代名詞ですね。 - I have more CDs than my sister (has CDs). (私は姉よりも多くのCDを持っている。)
→ 口語では … than my sister does. とすることも多いです。
比較構文の最後が “than I.” や “than he.” のように主格の代名詞だけで終わっている場合、その後ろに “am (is/are)” や “do (does/did)” が省略されていると考えると、文法的に理解しやすくなりますね。(口語では目的格の me, him を使うこともあります。)
関係詞節の中の省略 – 目的格の関係代名詞や「関係代名詞+be動詞」
関係詞節(名詞を後ろから修飾する節)の中でも、省略が起こることがあります。
1. 目的格の関係代名詞 (that, who, whom, which) の省略
関係代名詞が、関係詞節の中で目的語の働きをしている場合(目的格)、その関係代名詞は省略することができます。これは非常に頻繁に起こる省略です。
- This is the book (that/which) I want to read. (これは私が読みたい本です。)
→ 関係詞節 I want to read (the book) の中で、(the book) が目的語なので、that/which は省略可能。 - The man (that/who/whom) I met yesterday was very kind. (昨日私が会った男性はとても親切だった。)
→ 関係詞節 I met (the man) yesterday の中で、(the man) が目的語なので、that/who/whom は省略可能。
省略されると、名詞の直後にいきなり「主語 + 動詞」が続く形になるので、最初は戸惑うかもしれませんが、慣れると「あ、ここに関係代名詞が隠れてるな」とわかるようになります。
2. 「主格の関係代名詞 + be動詞」の省略
関係代名詞が主格で、かつその後ろにbe動詞が続く場合、「主格の関係代名詞 + be動詞」をセットで省略できることがあります。この省略が起こると、名詞の直後に -ing形、過去分詞、形容詞、前置詞句などが続く形になります。
- The girl (who is) playing the piano is my sister. (ピアノを弾いている少女は私の妹です。)
→ The girl playing the piano … - The language (which is) spoken in Brazil is Portuguese. (ブラジルで話されている言語はポルトガル語です。)
→ The language spoken in Brazil … - The cat (that is) on the roof is black. (屋根の上の猫は黒いです。)
→ The cat on the roof …
これは、先ほどの「接続詞の後の主語+be動詞の省略」と似ていますね。名詞を後ろから修飾する分詞構文や形容詞句、前置詞句は、この「主格の関係代名詞+be動詞」が省略された形と考えることができるんです。
関係詞の省略は、長文読解で文の構造を素早く正確に把握するために、とても重要な知識です。特に目的格の省略は頻出なので、しっかりマスターしましょう!
その他、会話や慣用表現での省略
上記以外にも、特に会話や決まった言い回しの中では、様々な省略が見られます。
- 命令文の主語 You の省略: (これは省略というより、命令文の基本形ですね)
例: (You) Come here. (ここへ来なさい。) - あいさつや短い応答での省略:
例: A: How are you? (元気ですか?)
B: (I’m) Fine, thank you. And you? (元気です、ありがとう。あなたは?)
例: A: Thank you. (ありがとう。)
B: (You’re) Welcome. (どういたしまして。) - 見出しや広告、メモなどでの簡潔な表現のための省略:
例: Two dead in crash. (衝突事故で2名死亡。) ← Two people are dead… のようなbe動詞や冠詞の省略。 - 慣用句の中での省略 (例: No smoking. No parking.)
例: (There is) No problem. (問題ないよ。)
例: (It is a) Pity! (残念!) / (What a) Shame! (なんてことだ!)
会話では、相手に誤解なく伝わる範囲で、できるだけ簡潔に話そうとするため、省略が頻繁に起こります。フォーマルな場面ではあまり省略しない方が良い場合もありますが、日常会話では省略をうまく使うことで、より自然でテンポの良いコミュニケーションが取れるようになりますよ。

わあ、省略って本当に色々なところで使われるんですね!慣れるまで大変そう…。
省略構文を理解し、使いこなすためのポイント
省略構文は、一見すると複雑で難しく感じるかもしれませんが、いくつかのポイントを押さえて練習すれば、必ず理解し、使いこなせるようになります。ここでは、そのためのヒントをいくつか紹介します。
省略されている箇所を補って考える練習
省略された文に出会ったら、「ここには何が省略されているんだろう?」と、元の形を復元して考える練習をしてみましょう。最初は時間がかかるかもしれませんが、これを繰り返すことで、だんだんとパターンが見えてきて、省略されている部分を素早く補えるようになってきます。
例えば、”She plays tennis better than I do.” という文を見たら、「do は何を指しているんだろう? あ、前の plays tennis を受けているんだな。だから、I play tennis のことか」というように、頭の中で復元してみるんです。
教科書や問題集の例文だけでなく、洋画のセリフや洋楽の歌詞など、身近な英語の中からも省略表現を探してみるのも楽しいですよ。
たくさんの英文に触れて「省略の感覚」を養う
省略のルールを頭で理解することも大切ですが、それ以上に、たくさんの生の英語に触れることで、「こういう時はこう省略されるんだな」という感覚を養うことが重要です。ネイティブスピーカーは、文法ルールを意識しているというよりも、自然な言葉の流れの中で、ごく当たり前に省略を使っています。
多読や多聴を通して、様々なパターンの省略表現に慣れ親しむことで、だんだんと「ここはおそらく省略だな」と直感的にわかるようになってきます。最初はわからなくても、解説を読んだり、辞書で調べたりしながら、少しずつ経験値を積んでいきましょう。
自分でも省略を使って話したり書いたりしてみる
インプットだけでなく、自分でも省略表現を意識して使ってみる(アウトプットする)ことも、理解を深め、定着させるためには非常に効果的です。
例えば、
- 友達との簡単な英会話で、”Yes, I do.” や “I’d love to.” のような応答を使ってみる。
- 日記や短いエッセイを英語で書くときに、反復を避けるための省略を試してみる。
- 接続詞の後の「主語+be動詞」の省略を使って、少し長い文をスッキリさせてみる。
最初は「これで合ってるかな?」と不安になるかもしれませんが、トライアンドエラーを繰り返すことで、だんだんと自信を持って使えるようになります。 間違いを恐れずに、積極的にチャレンジしてみてくださいね。
特に会話では、省略をうまく使えると、より流暢で自然な印象を与えることができます。相手が言ったことを繰り返さずに、代動詞や代不定詞でスマートに返せるとカッコイイですよね!
TOEICなどの試験ではどう対策する?
TOEIC L&Rテストのような試験では、省略構文が直接的に文法問題として問われることはそれほど多くないかもしれませんが、長文読解やリスニングで、省略された文を正しく理解する能力は非常に重要です。
- リーディング: 文の構造が複雑に見える場合、省略が使われていないか疑ってみましょう。特に、接続詞の直後や関係詞節の中、比較の文などは要注意です。省略されている部分を補って考えることで、文全体の意味がクリアになります。
- リスニング: 会話では省略が頻繁に使われるため、省略された形に耳が慣れていないと、聞き取れなかったり、意味を取り違えたりすることがあります。普段から、省略された自然な英語の音声にたくさん触れておくことが大切です。シャドーイングなども効果的でしょう。
文法問題としては、代動詞 do/does/did や代不定詞 to の用法、関係代名詞の省略などが問われる可能性があります。これらの基本的なルールはしっかり押さえておきましょう。
日頃から省略表現に意識を向けて学習していれば、試験でも慌てずに対処できるようになるはずです。

なるほど!練習と慣れが大切なんですね!自分でも使ってみようっと!
まとめ – 省略構文をマスターして、英語の達人を目指そう!
今回は、英語の「省略構文」について、その基本的な考え方から具体的なパターン、そして学習のポイントまで、詳しく見てきました。これで、今までモヤモヤしていた省略の謎が、少しでもスッキリしていただけたなら嬉しいです。
最後に、この記事で学んだ省略構文の重要なポイントをまとめておきましょう。
- 省略の基本:
- 言わなくてもわかることは省略するのが自然な流れ。
- 反復を避け、コミュニケーションを簡潔・スムーズにするため。
- 主な省略パターン:
- 動詞(句)の省略 (代動詞 do/does/did や助動詞で受ける)
- 目的語・補語の省略 (文脈から明らかな場合)
- to不定詞の後の動詞の原形の省略 (to の代不定詞)
- 接続詞の後の「主語 + be動詞」の省略 (特に副詞節)
- 比較構文での共通部分の省略
- 関係詞節の中の省略 (目的格の関係代名詞、「主格の関係代名詞+be動詞」)
- 会話や慣用表現での様々な省略
- 学習のポイント:
- 省略されている箇所を補って考える練習をする。
- たくさんの英文に触れて「省略の感覚」を養う。
- 自分でも省略を使って話したり書いたりしてみる (アウトプット)。
- 試験対策としては、読解・リスニングでの理解力向上が特に重要。
省略構文は、一見すると英語を難しくしているように感じるかもしれませんが、実は英語をより効率的で自然なものにするための知恵でもあるんです。この省略のルールを理解し、使いこなせるようになれば、あなたの英語力は格段に向上し、ネイティブスピーカーの英語がよりスムーズに理解できるようになるでしょう。
焦らず、一つひとつのパターンを丁寧に確認しながら、たくさんの英語に触れていってください。 そして、ぜひ自分でも省略表現を使ってみて、その便利さを実感してくださいね。応援しています!
この記事が、皆さんの英語学習の旅の一助となれば幸いです!

省略って奥が深いけど、使いこなせたら絶対カッコイイ!頑張って勉強します!

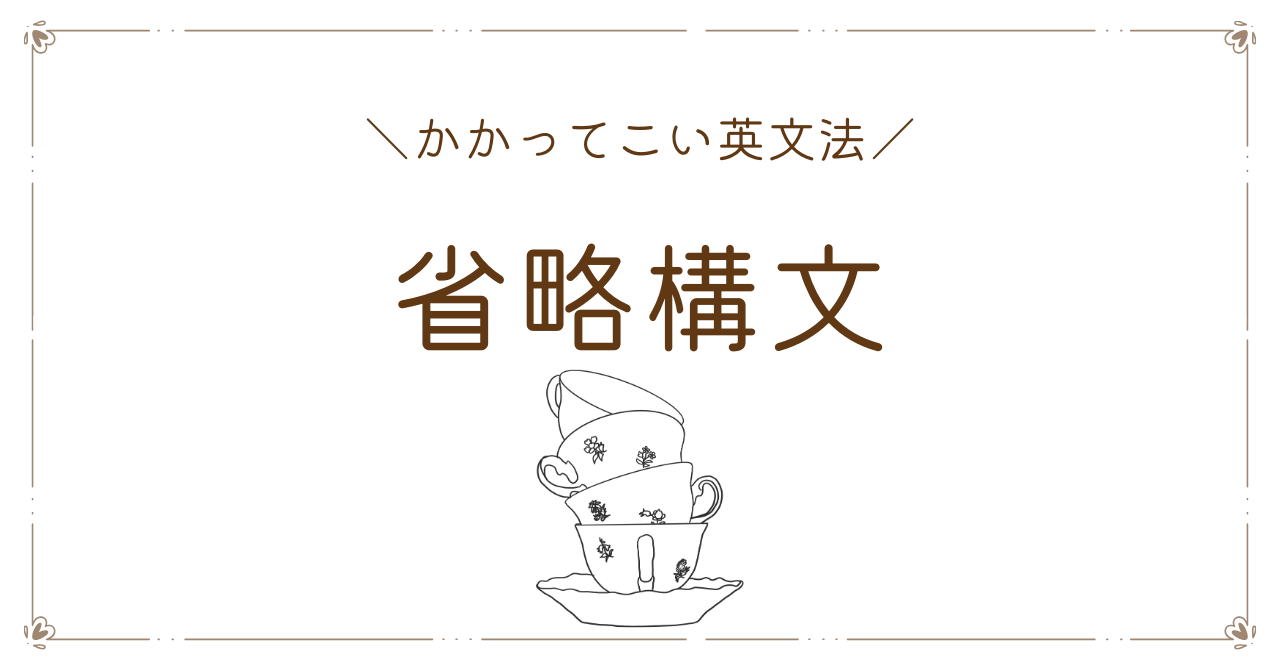
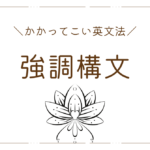

コメント