英語を勉強していると、「使役動詞」という言葉を耳にすることがありますよね。「make O C」とか「have O done」とか、なんだか色々な形が出てきて、「もう、わけがわからない!」って混乱してしまうこと、ありませんか? 「~させる」って訳されることが多いけど、じゃあ make も have も let も全部同じ意味なの? どうやって使い分けるの? そんな疑問で頭がいっぱいになってしまう… 私も昔はそうでした!
でも、この使役動詞は、英語で「誰かに何かをしてもらう」とか「何かが~の状態になるようにする」といった状況を表現するとても便利な動詞なんです。それぞれの動詞が持つ微妙なニュアンスの違いを理解して使いこなせるようになると、あなたの英語表現はぐっと豊かになりますよ! この記事では、そんなややこしくも重要な使役動詞(make, have, let)と、それによく似た働きをする動詞(get, help)について、それぞれの意味の違いや使い方、文の形を、たくさんの例文と一緒に、どこよりも分かりやすく解説していきます。これを読めば、もう使役動詞の使い分けに迷うことはありません!

使役動詞って、make とか have とか色々あって、違いがよく分からないんだよね…。全部「させる」じゃないの?
使役動詞の基本 – 「〜させる」だけじゃない?その役割と構造
まずは、使役動詞が一体どんなもので、なぜ英語学習で重要なのか、基本的なところから確認しましょう。ここを押さえておけば、個々の動詞の理解がぐっと深まりますよ。
そもそも使役動詞とは? – 基本的な定義と役割
「使役動詞」とは、文字通り「役(=働き)を使(=う)」、つまり「(人や物)に~させる」「(人や物)に~してもらう」という意味を表す動詞のことです。主語(S)が、他の誰か(目的語 O)に、ある動作(補語 Cにあたる部分)をさせたり、ある状態にさせたりする、という関係性を示します。
英語で代表的な使役動詞とされるのは、主に以下の3つです。
- make
- have
- let
これらの動詞は、文の構造として第5文型 (SVOC) を取ることが大きな特徴です。第5文型は「S + V + O + C」の形で、「主語(S)が、目的語(O)を、補語(C)の状態にする/させる」という意味を表します。使役動詞の場合、この「O」と「C」の間に「OがCする」という主語+述語のような隠れた関係(ネクサス関係)があるのがポイントです。
例: He made me clean the room. (彼は私に部屋を掃除させた。)
→ この文は SVOC の第5文型です。
→ S=He, V=made, O=me, C=clean the room
→ OとCの間には、「私が部屋を掃除する (I clean the room)」という隠れた意味関係があります。
このように、使役動詞は単に「~させる」と訳すだけでなく、文の構造(特にSVOC)と、OとCの関係性を理解することが大切なのです。
なぜ「使役」? – 日本語訳のイメージと強制力の違いに注意!
使役動詞はよく「~させる」と訳されるため、「強制」や「命令」といった強いイメージを持つかもしれません。確かに make にはそのようなニュアンスがありますが、have や let は必ずしも強制を意味するわけではありません。
- make: 強制力 が一番強い。「無理やり~させる」に近い。
- have: 義務、依頼、当然のこととして「~してもらう、させる」。状況によっては被害(~される)の意味も。
- let: 許可。「~させてあげる、~するのを許す」。強制とは逆のニュアンス。
このように、どの使役動詞を使うかによって、強制力の度合いや、話し手が状況をどう捉えているかが大きく変わってきます。「~させる」という日本語訳に引きずられず、それぞれの動詞が持つコアなニュアンスを理解することが非常に重要です。
また、「~させる」という訳がしっくりこない場合もあります。例えば “I had my hair cut.” は「髪を切らせた」というより「髪を切ってもらった」と訳す方が自然ですよね。文脈に合わせて柔軟に意味を捉えることも大切です。
使役動詞を使うメリット – 英語表現の幅がグンと広がる!
使役動詞を使いこなせるようになると、英語の表現力が格段にアップします。具体的には、こんなメリットがあります。
- 微妙なニュアンスを伝えられる: 強制なのか、依頼なのか、許可なのか、状況に応じた適切な動詞を選ぶことで、より正確に意図を伝えることができます。
- 簡潔で自然な表現ができる: 例えば「私は彼に私の車を修理してもらった」と言うとき、使役動詞 have を使えば “I had him repair my car.” や “I had my car repaired.” と、より英語らしい自然で簡潔な表現ができます。
- 複雑な状況を説明しやすくなる: 「誰かが誰かに何かをさせる/してもらう」という関係性を、SVOCという構造を使ってスムーズに表現できます。
- 英語の思考回路に近づける: 使役動詞の使い分けは、英語ネイティブの感覚を反映しています。これを学ぶことで、英語的な発想に慣れることができます。
最初は使い分けが難しく感じるかもしれませんが、マスターすれば強力な武器になるのが使役動詞なのです!
文型はSVOCが基本! – OとCの関係性とCの形が重要
使役動詞を理解する上で、文型、特に第5文型(SVOC)の知識は欠かせません。
S + V (使役動詞) + O (人/物) + C (動作/状態)
この構造で特に重要なのが、「補語(C)」の部分に何が来るかです。使役動詞の種類や意味によって、Cの形が変わるからです。
- 原形不定詞 (動詞の原形): make, have, let の場合、Cには動詞の原形が来ることが多いです。「Oが~する」という動作を表します。
例: I let him go. (go は原形) - to不定詞: get の場合、Cには to不定詞が来ます。「Oに~させる/してもらう」という意味。
例: I got him to help me. (to help は to不定詞) - 過去分詞 (-ed形): make, have, get の場合、Cに過去分詞が来ることがあります。「Oが~される」という受動的な意味や、「Oが~された状態になる」という完了の意味を表します。
例: I had my watch repaired. (repaired は過去分詞) - 形容詞: make の場合、Cに形容詞が来ることがあります。「Oを~な状態にする」という意味。
例: The news made me happy. (happy は形容詞) - 名詞: make の場合、Cに名詞が来ることがあります。「Oを~にする」という意味。
例: They made him captain. (captain は名詞)
このように、使役動詞をマスターするには、単に動詞の意味を覚えるだけでなく、「どの動詞が」「どんな意味合いで」「どんな形の補語(C)を取るのか」をセットで理解することが不可欠です。特に、Cに原形不定詞が来るのか、to不定詞が来るのか、過去分詞が来るのか、という点は、使役動詞の学習における最大のポイントと言えるでしょう。
また、Cが動作を表す場合、OとCの間には意味上の主語+述語の関係(OがCする / OがCされる)があることを常に意識してください。
例: I made him clean the room. (彼が掃除する)
例: I had my car repaired. (私の車が修理される)
この O と C の関係性を見抜くことが、使役構文を理解する鍵となります。
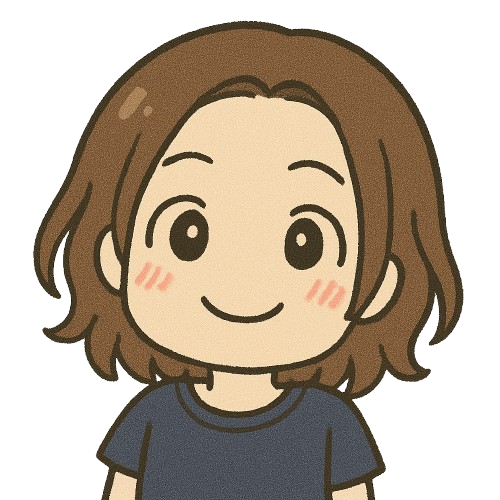
なるほど! 使役動詞って、ただ「させる」だけじゃなくて、強制力とか許可とか、ニュアンスが違うんだ! しかも、後ろに来る言葉の形(原形とか過去分詞とか)も動詞によって違うなんて! これはしっかり覚えないと!
代表的な使役動詞の使い方を徹底解説! (make, have, let, get, help)
ここからは、代表的な使役動詞 make, have, let と、準使役動詞とも呼ばれる get, help について、それぞれのニュアンスと使い方、そして文の形を詳しく見ていきましょう!
make – 強制力No.1!「(無理やり)~させる」「~の状態にする」
使役動詞の中で、最も強制力が強いのが make です。相手の意思に関わらず「無理やり~させる」というニュアンスを持つことが多いですが、必ずしもネガティブな意味だけではなく、「(必然的に)~の状態にする」という意味でも広く使われます。
make + O + C (原形不定詞):「Oに(無理やり)~させる」
- 形: S + make + O (人) + C (動詞の原形)
- 意味: 主語(S)が、目的語(O)の意思に反して、あるいは強制的に、ある動作(C)をさせる。
- 例文:
- My parents made me study abroad.
(両親は私を(無理やり)留学させた。) → 私の意思はあまり関係ないニュアンス。 - The boss made him work late.
(上司は彼に遅くまで働かせた。) → 強制的な指示。 - What made you change your mind?
(何があなたに考えを変えさせたのですか? / なぜ考えが変わったのですか?) → 状況や理由が変化を引き起こした。 - Don’t make me laugh!
(笑わせないでよ!) → 状況が笑いを引き起こす。
- My parents made me study abroad.
【注意点】
make O C (原形) は強制力が強いため、目上の人への依頼などには通常使いません。また、受動態 (be made to do) になると、原形不定詞が to不定詞に変わるので注意が必要です。
例: I was made to clean the room by my mother. (母に部屋を掃除させられた。)
make + O + C (形容詞/名詞):「Oを~な状態にする」「Oを~にする」
- 形: S + make + O (人/物) + C (形容詞/名詞)
- 意味: 主語(S)が、目的語(O)を、ある状態(C: 形容詞)や、あるもの(C: 名詞)にする。
- 例文 (C=形容詞):
- The movie made me sad.
(その映画は私を悲しい気持ちにさせた。) → O=me, C=sad (形容詞) - Hard work made him successful.
(勤勉さが彼を成功させた。) → O=him, C=successful (形容詞) - Please make yourself comfortable.
(どうぞ楽にしてください。) → O=yourself, C=comfortable (形容詞)
- The movie made me sad.
- 例文 (C=名詞):
- They made her chairperson.
(彼らは彼女を議長にした。) → O=her, C=chairperson (名詞) - We made him our leader.
(私たちは彼を私たちのリーダーにした。) → O=him, C=our leader (名詞句)
- They made her chairperson.
この用法は、O=C の関係がはっきりしており、第5文型(SVOC)の典型的な形です。「~させる」というより「~の状態にする」という意味合いが強いですね。
make + O + C (過去分詞):「Oを~される状態にする」
- 形: S + make + O (人/物) + C (過去分詞)
- 意味: 主語(S)が、目的語(O)が(他者によって)~される状態にする。特に、自分の意思や考えを「理解させる」という意味で “make oneself understood” がよく使われる。
- 例文:
- He couldn’t make himself understood in English.
(彼は英語で自分の言うことを理解させることができなかった。) → O=himself, C=understood (過去分詞)。「彼自身が理解される」状態にする、という意味。 - She tried to make her voice heard over the noise.
(彼女は騒音の中で自分の声を聞かせようとした。) → O=her voice, C=heard (過去分詞)。「彼女の声が聞かれる」状態にする、という意味。
- He couldn’t make himself understood in English.
この make O C (過去分詞) の形は、主に make oneself understood / heard などの慣用的な表現で使われることが多いです。
make のポイントまとめ:
- make O C (原形): Oに(無理やり)~させる。
- 強制力が強い。
- make O C (形容詞/名詞): Oを~(な状態)にする。
- make O C (過去分詞): Oを~される状態にする (主に慣用表現)。
have – 義務・依頼・当然「~してもらう、~させる」状況や被害「~される」
have も使役動詞として使われますが、make ほど強制力は強くありません。「(当然のこと、仕事として)~してもらう、~させる」という状況や、「(被害として)~される」という状況を表すのに使われます。
have + O + C (原形不定詞):「Oに(当然のこととして)~してもらう/させる」
- 形: S + have + O (人) + C (動詞の原形)
- 意味: 主語(S)が、目的語(O)に、仕事や役割として当然、あるいは依頼して、ある動作(C)をしてもらう/させる。make のような強制ではなく、Oがその動作をすることに抵抗がない、あるいはそれが普通である、というニュアンス。
- 例文:
- I’ll have my assistant call you back.
(アシスタントに後で電話させますね。) → アシスタントの仕事として当然。 - The teacher had the students read the textbook aloud.
(先生は生徒たちに教科書を音読させた。) → 授業の一環として。 - Could you have someone fix this computer?
(誰かにこのコンピューターを修理してもらえませんか?) → 依頼。
- I’ll have my assistant call you back.
この用法は、特にビジネスシーンなどで、部下や業者に何かを依頼したり指示したりする際によく使われます。
have + O + C (過去分詞):「Oを~してもらう(完了)」「Oを~される(被害)」
- 形: S + have + O (物/人) + C (過去分詞)
- 意味: この形は大きく分けて2つの意味があります。
- 【完了・依頼】主語(S)が、目的語(O)を(他の誰かに)~してもらう、~された状態にする。(主に O=物)
例: I had my hair cut yesterday.
(昨日、髪を切ってもらった。) → O=my hair, C=cut (過去分詞)。美容師さんに切ってもらった。 - 【被害】主語(S)が、目的語(O)を(意図せず)~されてしまう。(主に O=所有物や身体の一部)
例: I had my wallet stolen on the train.
(電車で財布を盗まれた。) → O=my wallet, C=stolen (過去分詞)。意図しない被害。
- 【完了・依頼】主語(S)が、目的語(O)を(他の誰かに)~してもらう、~された状態にする。(主に O=物)
- 例文 (完了・依頼):
- You should have your eyes checked.
(目を検査してもらった方がいいですよ。) → O=your eyes, C=checked - We had our house painted last month.
(先月、家を塗装してもらった。) → O=our house, C=painted - I need to have this document translated into English.
(この書類を英語に翻訳してもらう必要がある。) → O=this document, C=translated
- You should have your eyes checked.
- 例文 (被害):
- She had her bag snatched on the street.
(彼女は路上でバッグをひったくられた。) → O=her bag, C=snatched - He had his leg broken while skiing.
(彼はスキーをしていて脚を折った。) → O=his leg, C=broken
- She had her bag snatched on the street.
この have O C (過去分詞) の形は非常によく使われ、「~してもらう」なのか「~される(被害)」なのかは文脈で判断する必要があります。OとCの関係は「Oが~される」という受動関係です。
have のポイントまとめ:
- 強制力は make より弱い。
- have O C (原形): Oに(当然のこと/依頼して)~してもらう/させる。
- have O C (過去分詞): ① Oを(誰かに)~してもらう(完了)。 ② Oを~される(被害)。
let – 許可「~させてあげる、~するのを許す」
let は、make や have とは対照的に、「許可」を表す使役動詞です。「Oが~するのを許す」「Oに自由に~させてあげる」というニュアンスを持ちます。
let + O + C (原形不定詞):「Oに~させてあげる/~するのを許す」
- 形: S + let + O (人/物) + C (動詞の原形)
- 意味: 主語(S)が、目的語(O)が、ある動作(C)をすることを許可する、あるいは妨げずに自由にさせる。
- 例文:
- My parents didn’t let me go to the party.
(両親は私をパーティーに行かせてくれなかった。) → 行くことを許可しなかった。 - Please let me know if you have any questions.
(何か質問があれば知らせてください。) → 私に知らせることを許して=知らせて、という依頼表現。 - Let me introduce myself.
(自己紹介させてください。) → 自分が自己紹介することを許して、という丁寧な申し出。 - Don’t let this opportunity slip away.
(この機会を逃さないで。) → 機会が逃げるのを許さないで、という意味。 - Just let it be.
(そのままにしておきなさい。/なるようにさせなさい。) → 有名な曲のタイトルにもありますね。
- My parents didn’t let me go to the party.
【注意点】
let は受動態で使われることはほとんどありません。「~することを許される」と言いたい場合は、be allowed to do を使うのが一般的です。
例: I was allowed to go to the party. (私はパーティーに行くことを許された。)
また、let の後ろのCには、形容詞や過去分詞は通常来ません。
let のポイントまとめ:
- 許可を表す。「~させてあげる」。
- let O C (原形) の形のみ。
- 受動態は通常使わない (be allowed to do を使う)。
get – 説得・努力「~してもらう、~させる」完了・被害「~してもらう、~される」
get も使役的な意味で使われますが、厳密には使役動詞には分類されないこともあります(準使役動詞と呼ばれることも)。have と意味が似ている部分もありますが、get には「説得したり、努力したりして、Oに~してもらう/させる」というプロセスのニュアンスが含まれるのが特徴です。
get + O + to C (to不定詞):「Oに(説得・努力して)~してもらう/させる」
- 形: S + get + O (人) + to C (to不定詞)
- 意味: 主語(S)が、目的語(O)を説得したり、働きかけたりして、ある動作(C)をしてもらう/させる。have O C (原形) が比較的スムーズな状況を表すのに対し、get O to C は少し手間や努力がかかるニュアンス。Cが to不定詞になるのが最大のポイント!
- 例文:
- I finally got him to agree to my plan.
(私はついに彼を私の計画に同意させた。) → 説得に努力があったニュアンス。 - How can we get her to change her mind?
(どうすれば彼女に考えを変えてもらえるだろうか?) → 働きかけが必要。 - Could you get John to help us?
(ジョンに私たちを手伝ってもらうよう頼んでくれませんか?) → ジョンに働きかけてもらう依頼。
- I finally got him to agree to my plan.
get + O + C (過去分詞):「Oを~してもらう(完了)」「Oを~される(被害)」
- 形: S + get + O (物/人) + C (過去分詞)
- 意味: これは have O C (過去分詞) と非常に意味が近いです。
- 【完了・依頼】Oを(他の誰かに)~してもらう、~された状態にする。have よりも少し口語的な響きがある。
例: I need to get my car fixed.
(車を修理してもらう必要がある。) = I need to have my car fixed. - 【被害】Oを(意図せず)~されてしまう。have と同様。
例: He got his passport stolen.
(彼はパスポートを盗まれた。) = He had his passport stolen.
- 【完了・依頼】Oを(他の誰かに)~してもらう、~された状態にする。have よりも少し口語的な響きがある。
- 例文 (完了・依頼):
- Where did you get your hair done?
(どこで髪をやってもらったの?) → O=your hair, C=done - I must get this work finished by tomorrow.
(明日までにこの仕事を終わらせなければならない。) → O=this work, C=finished
- Where did you get your hair done?
- 例文 (被害):
- She got her fingers caught in the door.
(彼女はドアに指を挟まれた。) → O=her fingers, C=caught
- She got her fingers caught in the door.
have O done と get O done は多くの場合交換可能ですが、get の方がややインフォーマル(口語的)な響きを持つことがあります。
get のポイントまとめ:
- 説得・努力のニュアンスを含むことがある。
- get O to C (to不定詞): Oに(説得・努力して)~してもらう/させる。← to が必要!
- get O C (過去分詞): Oを~してもらう(完了)/~される(被害)。 (have O done とほぼ同じ意味だが、やや口語的)
help – 手伝う「Oが~するのを手伝う/~するのに役立つ」
help も使役動詞に含めて考えられることがあります(準使役動詞)。「~させる」というよりは、「Oが~するのを手伝う」「~するのに役立つ」という意味を表します。
help + O + (to) C (原形不定詞 / to不定詞):「Oが~するのを手伝う」
- 形: S + help + O (人) + (to) C (原形不定詞 or to不定詞)
- 意味: 主語(S)が、目的語(O)が、ある動作(C)をするのを手伝う、助ける。Cの部分は、原形不定詞でも to不定詞でもどちらでも良いのが大きな特徴(意味の違いはほとんどないが、原形の方がやや口語的)。
- 例文:
- Could you help me (to) carry this bag?
(このカバンを運ぶのを手伝ってくれませんか?) - He helped her (to) find her keys.
(彼は彼女が鍵を探すのを手伝った。) - Reading books helps you (to) improve your vocabulary.
(本を読むことは語彙力を向上させるのに役立つ。) → Sが物事の場合も。
- Could you help me (to) carry this bag?
※ O が省略されて S + help + (to) C の形になることもあります。
例: This medicine will help (to) relieve the pain. (この薬は痛みを和らげるのに役立つだろう。)
help のポイントまとめ:
- 「手伝う」「役立つ」の意味。
- help O (to) C (原形 or to不定詞): Oが~するのを手伝う。 ← to はあってもなくてもOK!
使役動詞/準使役動詞とCの形のまとめ
- make O C(原形) / C(形容詞/名詞) / C(過去分詞)
- have O C(原形) / C(過去分詞)
- let O C(原形)
- get O to C(to不定詞) / C(過去分詞)
- help O (to) C(原形/to不定詞)
特に C に動詞が来る場合の形(原形か to不定詞か)は、しっかり区別して覚えましょう!

うわー、やっぱり動詞によってCの形が違うんだ! get は to が必要で、help は to があってもなくてもいい… これは間違えやすいポイントだなぁ。しっかり復習しないと!
まとめ:使役動詞を使いこなして英語の表現力をアップさせよう!
今回は、英語学習で多くの人がつまずきやすい「使役動詞」とそれに類する動詞(make, have, let, get, help)について、それぞれのニュアンスや使い方、文の形を詳しく解説しました。最後に、重要ポイントを整理しておきましょう。
- 使役動詞の基本:
- 「(人/物)に~させる/してもらう」という意味を表す。
- 主に第5文型 (SVOC) を取る。
- OとCの間に意味上の主語+述語の関係がある (OがCする/される)。
- 動詞によって強制力やニュアンスが異なる(「~させる」という訳に注意)。
- C(補語)の形(原形、to不定詞、過去分詞など)が動詞によって決まる。
- 各動詞のポイント:
- make:強制力が最も強い。
- make O C(原形): ~させる(強制)
- make O C(形容詞/名詞): ~(な状態)にする
- make O C(過去分詞): ~される状態にする (make oneself understoodなど)
- have: 義務、依頼、当然、状況、被害。
- have O C(原形): ~してもらう/させる(当然/依頼)
- have O C(過去分詞): ~してもらう(完了) / ~される(被害)
- let:許可。
- let O C(原形): ~させてあげる/許す
- get: 説得、努力、完了、被害(準使役動詞)。
- get O to C(to不定詞): ~してもらう/させる(説得/努力) ← to が必須!
- get O C(過去分詞): ~してもらう(完了) / ~される(被害) (have O doneと類似)
- help: 手伝う、役立つ(準使役動詞)。
- help O (to) C(原形/to不定詞): ~するのを手伝う/役立つ ← to は任意!
- make:強制力が最も強い。
- 学習のコツ:
- 各動詞のニュアンスと、どの形のCを取るかをセットで覚える。
- 文脈の中で意味や使い方を判断する練習をする。
- 辞書を活用し、例文をしっかり確認する。
- 自分で例文を作ったり、音読したりして定着させる。
使役動詞は、単に文法ルールとして覚えるだけでなく、それぞれの動詞が持つ「気持ち」や「状況」を理解し、使い分けることが大切です。これができるようになると、あなたの英語はより nuanced(ニュアンス豊か)で、表現の幅がぐっと広がります。
最初は覚えることが多くて大変かもしれませんが、一つ一つ例文に触れながら、その感覚を掴んでいってください。使役動詞をマスターすれば、英語でのコミュニケーションがもっとスムーズに、もっと楽しくなるはずです! 頑張ってくださいね!

使役動詞、奥が深いけど、それぞれの違いと使い方がよく分かった! Cの形をしっかり覚えるのがポイントだね! これで英作文とか会話で使えるように練習するぞー!

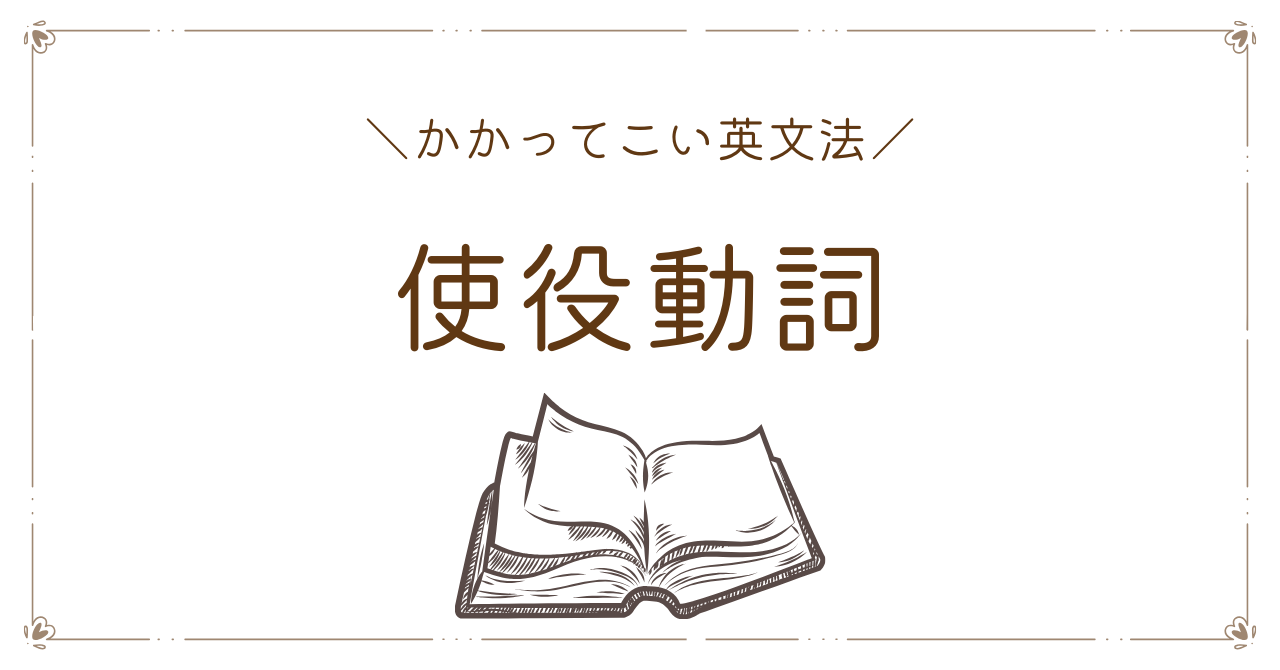
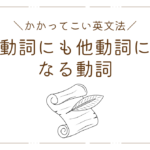

コメント