英語の勉強を始めたばかりのとき、「a book」「an apple」のように名詞の前にくっついている “a” や “an”。これって一体何なのでしょうか?「どっちを使えばいいの?」「そもそもこれって必要なの?」なんて疑問を持ったことがある人も多いんじゃないでしょうか。中学生や高校生はもちろん、大学生やTOEICのスコアアップを目指している方にとっても、この「冠詞(かんし)」、特に「不定冠詞」と呼ばれる a/an は、意外と奥が深くて、正しく使いこなすのが難しいと感じるポイントかもしれませんね。
でも、大丈夫!この記事では、そんな皆さんのために、不定冠詞 a/an の基本的な役割から、具体的な使い方、間違いやすいポイントまで、一つひとつ丁寧に、そして分かりやすく解説していきます。たくさんの例文と一緒に学んでいくので、きっと「なるほど!」と納得できるはず。この記事を読み終わる頃には、自信を持って a/an を使い分けられるようになっていること間違いなしですよ!

冠詞って、なんだか難しそうだけど、これでスッキリわかるかな?
不定冠詞 a/an の役割とは? – 「ひとつ」の印と初めての登場
まず、不定冠詞 a/an がどんな働きをするのか、基本的なところから見ていきましょう。名前の通り「不定」つまり「定まっていない」ものを指すときに使う冠詞なんです。
「不定」ってどういう意味? – 特定されていない「あるひとつ」
「不定冠詞」の「不定」とは、「特定されていない」という意味です。つまり、話し手と聞き手の間で「ああ、あれね!」と共通認識がない、「たくさんある中のどれでもいいから、あるひとつのもの」を指すときに使います。初めて話題に出るものや、漠然と「ある一つの~」と言いたい場合に使われることが多いんですよ。
例えば、
- I saw a cat in the park. (公園で猫を一匹見ました。)
この文では、どの猫なのか特定されていません。「公園にいた、とある一匹の猫」というニュアンスです。もしこれが「I saw the cat…」となると、聞き手も知っている特定の猫、例えば「昨日話したあの猫」のような意味合いになってきます。この “the” は「定冠詞」といって、また別の機会に詳しくお話ししますね。
不定冠詞 a/an は、基本的に「数えられる名詞の単数形」の前につきます。「ひとつだよ」という印でもあるんですね。
a と an の使い分けルール – 母音と子音の「音」が鍵
さて、不定冠詞には “a” と “an” の2つの形がありますが、これはどう使い分ければいいのでしょうか?ポイントは、不定冠詞の直後に続く単語の「最初の音」なんです。スペル(つづり)ではなく、「音」で判断するのがミソですよ!
基本ルール: 子音の前は a, 母音の前は an
これが大原則です。
- 子音の音で始まる単語の前には a を使います。
- a book (本) ← /b/ の音
- a cat (猫) ← /k/ の音
- a dog (犬) ← /d/ の音
- a table (テーブル) ← /t/ の音
- 母音の音(ア・イ・ウ・エ・オのような音)で始まる単語の前には an を使います。
- an apple (リンゴ) ← /æ/ の音
- an egg (卵) ← /e/ の音
- an idea (アイデア) ← /aɪ/ の音
- an orange (オレンジ) ← /ɔː/ の音
- an umbrella (傘) ← /ʌ/ の音
なぜこんな使い分けをするかというと、発音しやすくするためなんです。”a apple” だと「ア・アップル」となって母音が続いて言いづらいですよね?そこで “an apple”「アン・アップル」とすることで、スムーズに発音できるようになるんです。
母音は日本語のア・イ・ウ・エ・オに近い音ですが、英語にはもっとたくさんの母音の音があります。でも、最初のうちは「ア行の音で始まる単語の前は an」と覚えておけば、だいたい大丈夫ですよ!
注意!スペルではなく「発音」で判断する例 (hour, university)
ここが引っかかりやすいポイント!スペルが母音字 (a, i, u, e, o) で始まっていても、最初の音が子音なら “a” を使います。逆に、スペルが子音字で始まっていても、最初の音が母音なら “an” を使うんです。
具体的な例を見てみましょう。
- an hour (1時間)
→ “h” は子音字ですが、”hour” の最初の “h” は発音されず、「アワー /aʊər/」と母音で始まります。だから an hour なんです。 - an honest person (正直な人)
→ これも “honest” の “h” は発音されず、「オネスト /ˈɒnɪst/」と母音で始まります。なので an honest person。 - a university (大学)
→ “u” は母音字ですが、”university” の最初の音は「ユニヴァーシティ /juːnɪˈvɜːrsəti/」と、/j/ (ヤ行の子音に近い音) で始まります。だから a university なんですね。 - a useful tool (便利な道具)
→ “useful” も「ユースフル /ˈjuːsfəl/」と /j/ の音で始まるので a useful tool。 - a European country (ヨーロッパの国)
→ “European” は “E” (母音字) で始まりますが、発音は「ユーロピアン /ˌjʊərəˈpiːən/」で、/j/ の音で始まります。なので a European country。 - a one-way street (一方通行の道)
→ “one” は “o” (母音字) で始まりますが、発音は「ワン /wʌn/」で、/w/ (ワ行の子音に近い音) で始まります。そのため a one-way street。
これは本当に間違いやすいので、単語のスペルだけでなく、必ず「最初の音」を意識するようにしてくださいね!辞書で発音記号を確認するクセをつけると良いですよ。
形容詞などが名詞の前につく場合も、a/an はその直後の単語の音で判断します。
- a big apple (大きなリンゴ) ← big の /b/ (子音) で判断
- an old book (古い本) ← old の /oʊ/ (母音) で判断
不定冠詞が使われる名詞の種類 – 数えられる単数名詞が基本
不定冠詞 a/an は、どんな名詞にでも使えるわけではありません。原則として、「数えられる名詞(可算名詞)の単数形」の前につきます。
「数えられる名詞」とは、その名の通り、1つ、2つ、3つ…と数えることができる名詞のことです。
- book (本) → a book (一冊の本), two books (二冊の本)
- student (生徒) → a student (一人の生徒), three students (三人の生徒)
- idea (考え) → an idea (一つの考え), many ideas (たくさんの考え)
逆に、「数えられない名詞(不可算名詞)」や「複数形の名詞」には、原則として不定冠詞 a/an はつきません。
- water (水) → × a water (通常は言いません。コップ一杯の水なら “a glass of water” のように言います)
- information (情報) → × an information
- books (複数の本) → × a books
この「数えられる名詞」と「数えられない名詞」の区別も、冠詞を理解する上でとても大切になってきます。これについては、後のセクションでもう少し詳しく触れますね。

なるほど!「音」で決まるなんて知らなかった!あと、数えられる名詞の単数形だけなんだね。
不定冠詞 a/an の具体的な使い方と様々な意味 – 「ひとつ」だけじゃない!
不定冠詞 a/an の基本的な役割は「不特定のひとつ」を表すことですが、それ以外にもいくつかの意味や使い方があるんです。ここでは、具体的な例文を見ながら、a/an の持つ様々な顔を探っていきましょう。
「あるひとつの~」 – 不特定のものを指す基本用法
これが不定冠詞 a/an の最も基本的な使い方です。先ほども触れましたが、話し手と聞き手の間で特定されていない「とある~」「何らかの~」といったニュアンスで使われます。
- I want to buy a new car. (私は新しい車を一台買いたい。)
→ どんな車かはまだ決まっていない、漠然と「一台の新しい車」という感じです。 - She is reading a novel. (彼女は一冊の小説を読んでいる。)
→ 特定の小説ではなく、「何かしらの小説」を読んでいるという意味です。 - There is a bird singing in the tree. (木で鳥が一羽鳴いている。)
→ どの鳥かは特定せず、「一羽の鳥」がいることを伝えています。 - He is a doctor. (彼は医者です。)
→ 職業を表すときにも使われます。「医者という職業の一員である」というニュアンスです。他にも an engineer (エンジニア), a teacher (教師) など。 - What a beautiful flower! (なんて美しい花なんだろう!)
→ 感嘆文でも使われますね。「一つの美しい花」に対して感動している様子です。
「~というもの(種類全体)」 – 総称としての用法
不定冠詞 a/an は、時に「~という種類のもの全体」「~の代表」を指す総称的な意味で使われることがあります。この場合、「ある一つ」がその種類全体を代表している、という考え方です。
- A dog is a faithful animal. (犬というものは忠実な動物だ。)
→ 特定の一匹の犬ではなく、「犬という種類の動物は一般的に」という意味です。 - An airplane can fly faster than a train. (飛行機というものは電車よりも速く飛べる。)
→ 「飛行機という乗り物全般」について述べています。 - A child needs love. (子供というものには愛情が必要だ。)
→ 「子供という存在は皆」というニュアンスです。
この総称用法は、定冠詞 the を使って “The dog is a faithful animal.” や、複数形を使って “Dogs are faithful animals.” と表現することもできます。意味合いはほぼ同じですが、a/an を使うと「その種類の中の一例を取り上げて一般論を述べる」というニュアンスが少し出ることがあります。
ただし、この総称用法は、文脈によっては「ある一つの~」という通常の意味にも取れることがあるので、少し注意が必要です。多くの場合、文全体の内容から判断できますよ。
「~につき(per)」 – 割合や頻度を表す用法
不定冠詞 a/an は、「~ごとに」「~につき」という意味で、割合や頻度を表すことがあります。この用法は、”per” と同じような意味合いで使われます。
- I go to the gym twice a week. (私は週に2回ジムに行きます。)
→ “per week” (1週間につき) と同じ意味です。 - This car can run 60 miles an hour. (この車は時速60マイルで走れます。)
→ “per hour” (1時間につき) と同じです。”an” が使われるのは “hour” の最初の “h” が発音されないためですね。 - These apples cost 100 yen a piece. (これらのリンゴは1個につき100円です。)
→ “per piece” (1個につき) と同じです。 - He earns $50,000 a year. (彼は年に5万ドル稼ぎます。)
→ “per year” (1年につき) と同じです。
この使い方は、会話でも書き言葉でもよく出てくるので、覚えておくと便利ですよ。
「同じ~」 – “of a kind”, “of an age” などの表現
これは少し特殊な使い方ですが、”of a size” (同じ大きさの), “of an age” (同い年の), “of a mind” (同じ意見の) のように、“of a/an + 名詞” の形で「同じ種類の~」「同じ~の」という意味を表すことがあります。
- Birds of a feather flock together. (同じ羽の鳥は集まる。→類は友を呼ぶ)
→ ことわざですね。”of a feather” で「同じ種類の羽を持つ」という意味です。 - The two sisters are of an age. (その姉妹は同い年です。)
→ “of an age” で「同じ年齢の」という意味になります。 - They are all of a mind on this matter. (彼らはこの件に関して全員同じ意見だ。)
→ “of a mind” で「同じ考えの」。
これは決まった言い回しとして覚えてしまうのが良いでしょう。
固有名詞について特別な意味合いを持たせる場合
通常、人の名前や地名といった固有名詞には冠詞はつきませんが、不定冠詞 a/an がつくことで特別な意味合いを持つことがあります。
- 「~という名前の人」(話し手はその人をよく知らない)
例: A Mr. Smith called you this morning. (スミスさんという方から今朝電話がありましたよ。)
→ 話し手は「スミスさん」という名前を聞いただけで、その人がどんな人かはよく知らない、というニュアンスです。 - 「~のような人」「~の作品」
例: He thinks he is a Shakespeare. (彼は自分をシェイクスピアのような大文豪だと思っている。)例: This painting is a Picasso. (この絵はピカソの作品だ。)→ 有名な人の名前を使って、その人のような特徴を持つ人や、その人の作品を指します。 - 「~家の人」
例: She married a Kennedy. (彼女はケネディ家の人と結婚した。)→ 特定の家系の一員であることを示します。
これらは少し応用的な使い方ですが、知っておくと英語の理解が深まりますね。

へぇ~、a/an にも色々な意味があるんだなぁ。奥が深い!
不定冠詞を使わないケースと注意点 – 間違いやすいポイント整理
不定冠詞 a/an は「数えられる名詞の単数形」につくのが基本ですが、逆につかないケース、つまり冠詞が不要な場合もあります。また、定冠詞 the との使い分けも重要です。ここでは、不定冠詞を使わない主なケースと、注意すべきポイントを整理していきましょう。
数えられない名詞 (不可算名詞) には原則使わない
すでにお話しした通り、数えられない名詞(不可算名詞)には、原則として不定冠詞 a/an はつきません。 数えられない名詞とは、水や空気のように形が定まっていない物質名詞、情報や幸福のような抽象名詞、家具やお金のような集合名詞などがあります。
代表的な不可算名詞の例:
- 物質名詞: water (水), coffee (コーヒー), air (空気), sugar (砂糖), bread (パン), paper (紙)
- 抽象名詞: information (情報), advice (アドバイス), news (ニュース), happiness (幸福), beauty (美しさ), knowledge (知識), luck (運)
- 集合名詞: furniture (家具), luggage/baggage (手荷物), money (お金), equipment (設備), mail (郵便物)
これらの名詞は、基本的に1つ、2つと数えることができないため、”a water” や “an advice” のようには言いません。
- I need (some) information. (情報が必要です。) × an information
- She gave me (some) good advice. (彼女は私に良いアドバイスをくれた。) × a good advice
- We bought new furniture. (私たちは新しい家具を買った。) × a new furniture
「でも、パンを一個とか、アドバイスを一つとか言いたい時はどうするの?」って思いますよね。そういう時は、”a piece of ~” や “a loaf of ~” のような「助数詞」と呼ばれる言葉を使います。
・a piece of advice (一つのアドバイス)
・a loaf of bread (一斤のパン)
・a sheet of paper (一枚の紙)
・two glasses of water (コップ二杯の水)
このように、数えるための単位を補うことで表現できるんです。
ただし、不可算名詞でも、文脈によって「種類」や「一杯/一皿の~」といった意味で可算名詞として扱われ、a/an がつくこともあります。例えば、
- I’d like a coffee, please. (コーヒーを一杯ください。) ← この場合は「一杯のコーヒー」として数えています。
- There are many different cheeses in this shop. (この店にはたくさんの種類のチーズがある。) ← cheese は通常不可算名詞ですが、ここでは「様々な種類のチーズ」として複数形になっています。
これは少しややこしいですが、基本は「不可算名詞には a/an はつかない」と覚えておきましょう。
複数形の名詞には使わない
これも基本的なルールですが、複数形の名詞には不定冠詞 a/an はつきません。 a/an は「ひとつの」という意味を持っているので、複数のものには使えないんですね。
- I have books. (私は本を何冊か持っています。) × a books
- There are cats in the garden. (庭に猫が何匹かいます。) × a cats
じゃあ、複数形の名詞の前には何もつけないの?それとも何か他の言葉がつくの?
良い質問ですね! 複数形の名詞の前には、文脈によって何もつけないこともありますし、”some” (いくつかの), “many” (たくさんの), “a lot of” (たくさんの), “the” (特定の複数の~) などの言葉がつくことがあります。
- I like apples. (私はリンゴが好きです。) ← 一般的なリンゴ全体を指すので何もつかない。
- I bought some apples. (私はリンゴをいくつか買いました。)
- She has many friends. (彼女にはたくさんの友達がいます。)
- Look at the beautiful flowers! (あの美しい花々を見て!) ← 特定の花々を指している。
冠詞を省略する特別なケース (食事、スポーツ、役職など)
特定の名詞が特定の状況で使われる場合、慣用的に冠詞(a/an も the も)が省略されることがあります。これはルールというよりも、そういう言い方をする、と覚えてしまうのが早道です。
食事の名前
breakfast (朝食), lunch (昼食), dinner (夕食) などの食事の名前は、それが一般的な「食事」を指す場合、冠詞をつけません。
- What do you usually have for breakfast? (普段朝食に何を食べますか?)
- Let’s have lunch together. (一緒に昼食を食べましょう。)
ただし、特定の食事を指す場合や、形容詞がつく場合は a/an や the がつくこともあります。
- We had a wonderful dinner last night. (昨夜は素晴らしい夕食をとった。) ← “wonderful” という形容詞がついている。
- The breakfast I had this morning was delicious. (今朝食べた朝食は美味しかった。) ← 特定の朝食。
スポーツやゲームの名前
soccer (サッカー), baseball (野球), tennis (テニス), chess (チェス) などのスポーツやゲームの名前も、一般的に冠詞をつけません。
- I like to play soccer. (私はサッカーをするのが好きです。)
- She is good at chess. (彼女はチェスが得意です。)
役職・身分が補語になる場合
「~になる (become)」や「~に任命される (be appointed)」などの動詞の後に、役職や身分を表す名詞が補語として続く場合、特にその役職が一つしかないような場合に冠詞が省略されることがあります。
- He became President of the company. (彼はその会社の社長になった。)
→ 社長は通常一人なので、無冠詞になることがあります。ただし、”He is a president.” (彼は社長の一人だ。) のように、一般的な職業として言う場合は a がつきます。 - She was elected captain of the team. (彼女はチームのキャプテンに選ばれた。)
これは文脈や慣習による部分も大きいので、少し注意が必要です。
特定の場所や施設が本来の目的で使われる場合
school (学校), church (教会), hospital (病院), prison (刑務所), bed (ベッド) などの名詞が、その場所の本来の目的(学校なら勉強、病院なら治療、ベッドなら睡眠)で使われる場合、冠詞をつけないことがあります。
- I go to school by bus. (私はバスで学校へ行きます。) ← 勉強するために行く。
- He is in hospital. (彼は入院中です。) ← 治療を受けている。
- It’s time to go to bed. (もう寝る時間だ。) ← 睡眠のために行く。
もしこれらの場所に「建物として」言及する場合などは、a/an や the がつきます。
- There is a school near my house. (私の家の近くに学校が一軒あります。) ← 建物として。
- I visited him in the hospital. (私は彼を病院に見舞った。) ← 特定の病院の建物。
冠詞の有無で意味が変わる名詞の例として、”go to school” (通学する) と “go to the school” (その学校へ行く、例えば保護者として訪問するなど) がよく挙げられますね。冠詞って奥が深い!
by + 交通手段
“by bus” (バスで), “by train” (電車で), “by car” (車で) のように、交通手段を表す場合も冠詞をつけません。
- I came here by car. (私は車でここへ来ました。)
これらの無冠詞のケースは、慣用的なものが多いので、例文ごと覚えてしまうのがおすすめです。
定冠詞 the との使い分け – 特定か不特定か
不定冠詞 a/an と最も対比されるのが定冠詞 the です。この二つの使い分けは、冠詞をマスターする上での最大のポイントと言っても過言ではありません。
基本的な考え方は、
- 不定冠詞 a/an: 不特定のもの。「たくさんある中のどれかひとつ」「初めて話題に出るもの」
- 定冠詞 the: 特定のもの。「話し手と聞き手の間で共通認識があるもの」「文脈や状況から特定できるもの」「すでに話題に出たもの」
という違いです。
よくあるパターンは、
- 最初に話題に出るときは a/an を使う。
例: I bought a new bag yesterday. (昨日、新しいバッグをひとつ買いました。) - 同じものが2回目以降に話題に出るときは the を使う。
例: The bag is very cute. (そのバッグはとても可愛いです。)
→ 2回目なので、どのバッグか特定できていますね。
他にも、
- 状況から明らかに特定できるもの:
Can you pass me the salt, please? (その塩を取ってくれませんか?) ← 食卓にあって、目の前にある塩。Open the door. (そのドアを開けて。) ← 部屋に一つしかないドアや、特定のドア。 - 世界に一つしかないもの:
the sun (太陽), the moon (月), the earth (地球) - 最上級や序数詞と一緒のとき:
the tallest building (一番高い建物), the first day (最初の日)
定冠詞 the の用法はこれまた奥が深いので、別の記事でじっくり解説したいと思いますが、まずは「特定されているかどうか」を基準に a/an と a/the を使い分ける感覚を養うことが大切です。
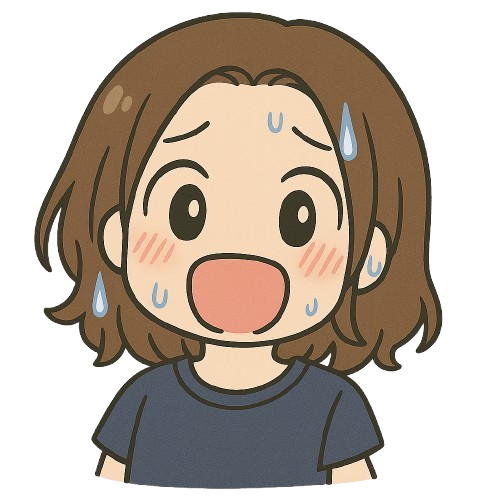
うわー、冠詞を使わないケースもたくさんあるし、the との使い分けも難しい…。覚えられるかなぁ。
まとめ – 不定冠詞 a/an をマスターして英語力アップ!
今回は、英語の小さな巨人「不定冠詞 a/an」について、その基本的な役割から具体的な使い方、注意点まで詳しく見てきました。覚えることがたくさんあって大変だったかもしれませんが、ポイントを押さえれば必ず使いこなせるようになりますよ!
最後に、不定冠詞 a/an の大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 役割:
- 特定されていない「あるひとつの~」を表す。
- 基本的に数えられる名詞の単数形につく。
- a と an の使い分け:
- 不定冠詞の直後に続く単語の「最初の音」で判断する。
- 子音の音の前は a (例: a book, a university)。
- 母音の音の前は an (例: an apple, an hour)。
- 様々な意味:
- 「あるひとつの~」(基本)
- 「~というもの(種類全体)」(総称) (例: A dog is faithful.)
- 「~につき(per)」 (例: twice a week)
- 「同じ~」 (例: birds of a feather)
- 固有名詞について「~という人」「~の作品」 (例: a Mr. Smith, a Picasso)
- 使わない主なケース:
- 数えられない名詞 (例: water, information)
- 複数形の名詞 (例: books)
- 慣用的に無冠詞になる場合 (食事、スポーツ、by + 交通手段など)
- 定冠詞 the との区別:
- a/an は「不特定」、the は「特定」。
冠詞は、ネイティブスピーカーにとっては当たり前の感覚で使っているものなので、私たち日本人にとってはなかなか完全にマスターするのが難しい部分です。でも、基本的なルールを理解し、たくさんの英語に触れて、間違いを恐れずに実際に使ってみることで、少しずつ感覚が身についていきます。
最初は「これで合ってるかな?」と不安になるかもしれませんが、意識して使ううちに、自然と正しい形が口から出てくるようになりますよ。不定冠詞 a/an をしっかり使いこなせるようになれば、あなたの英語はもっと自然で、もっと正確なものになるはずです。焦らず、一歩ずつ、英語学習を楽しんでいきましょう!
この記事が、皆さんの冠詞学習の助けになれば、とっても嬉しいです!

ポイントが整理されててわかりやすかった!今日から意識して使ってみよう!

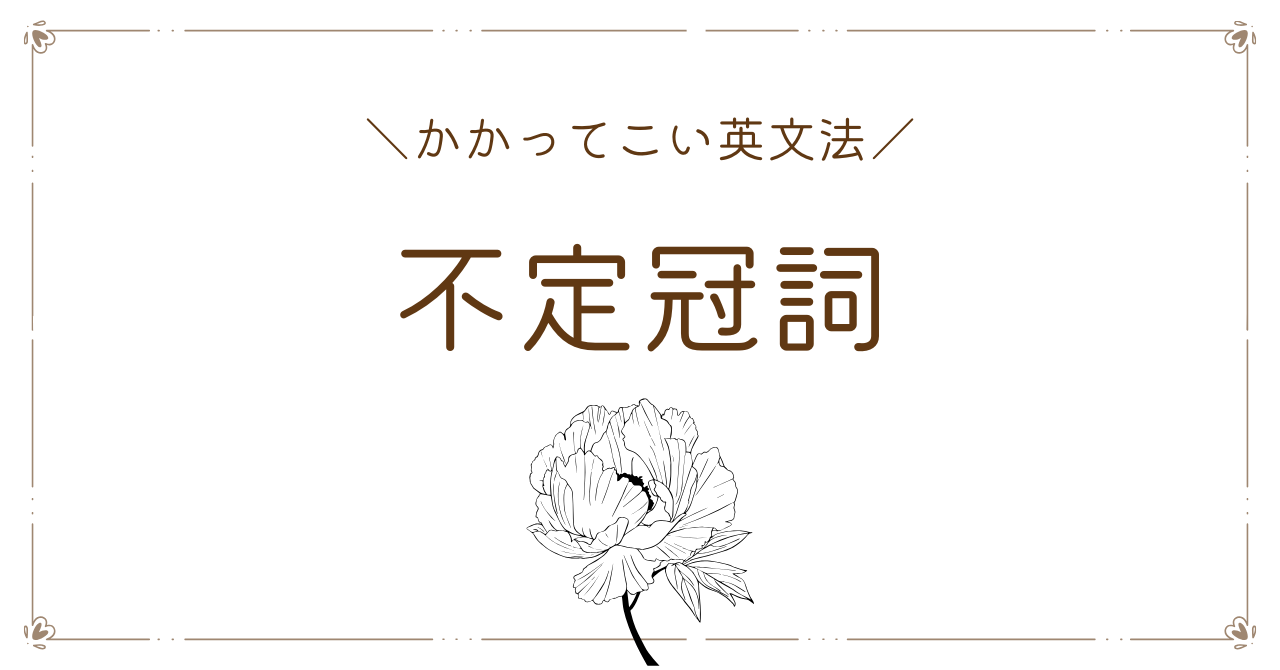
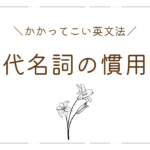
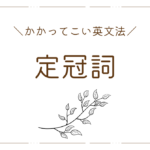
コメント