不定詞の勉強をしていると、”To tell the truth,” とか “Needless to say,” みたいに、文の最初にカンマ(,)付きでポンと置かれている「to + 動詞の原形」のフレーズに出会うこと、ありませんか?「え、これって不定詞のどの用法なんだろう?」「文の主語と関係なさそうだけど、どういう意味?」って、ちょっと戸惑ってしまう方もいるかもしれませんね。普通の不定詞の用法とは少し違う感じで、なんだか特別なルールがあるのかな?って思っちゃいますよね。
実はこれ、「独立不定詞(どくりつふていし)」と呼ばれるもので、多くは慣用的なフレーズとして使われているんです!この記事では、そんなちょっと特殊な「独立不定詞」について、その正体から、なぜ「独立」と呼ばれるのか、そして会話や文章で非常によく使われる代表的な慣用表現まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。独立不定詞は、決まったフレーズを覚えてしまえば、表現の幅を広げるとても便利なツールになりますよ!

独立不定詞…?初めて聞きました!To tell the truth とかは見たことあるけど、そういう名前だったんですね!
- 独立不定詞って何?その正体と特徴を理解しよう
- これで完璧!よく使われる独立不定詞の慣用表現フレーズ集
- 発言の真意・本音を伝える表現 (To tell the truth, To be frank…)
- 状況をさらに悪化させる表現 (To make matters worse)
- 話を切り出す・順序を示す表現 (To begin with, To start with)
- 譲歩や確信を表す表現 (To be sure)
- 周知の事実を示す表現 (Needless to say, Strange to say)
- 比喩や言い換えを表す表現 (So to speak)
- 要約や簡潔化を表す表現 (To put it simply, To sum up…)
- その他の重要な慣用表現 (To do someone justice, Not to mention…)
- まとめ:独立不定詞を使いこなして表現を豊かに!
独立不定詞って何?その正体と特徴を理解しよう
まずは、「独立不定詞」がどのようなもので、なぜそう呼ばれるのか、基本的な特徴から掴んでいきましょう。普通の不定詞の用法との違いを意識すると分かりやすいですよ。
独立不定詞の定義:文全体を修飾する「お決まりフレーズ」
独立不定詞 (Independent Infinitive / Absolute Infinitive) とは、簡単に言うと、文全体の意味合いを修飾したり、話し手の態度や挿入的なコメントを示したりする、副詞のような働きをする不定詞(多くは to不定詞)の慣用的な表現のことです。
最大の特徴は、その不定詞が表す動作の主語(意味上の主語)が、文の主語(主節の主語)とは一致しない、あるいは「一般の人々 (we, you, people など)」であるために、特に明示されずに使われる点です。
例:
- To tell the truth, I don’t really like natto. (実を言うと、私は納豆があまり好きではありません。)
- この文の主語は “I” ですが、「真実を言う (tell the truth)」のは、必ずしもこの文の主語 “I” だけを指しているわけではありません。話し手自身が「(私が)実を言うと」と前置きしている、あるいは「一般的に真実を述べるならば」といったニュアンスで、文全体にかかる副詞句のように機能しています。
- Needless to say, health is more important than wealth. (言うまでもなく、健康は富よりも重要だ。)
- 「言う必要がない」のは誰か? 特定の誰かではなく、一般的に見てそうだ、ということですよね。これも文全体を修飾する挿入句のような働きです。
このように、文の主語とは「独立」して、お決まりのフレーズとして文に情報を付け加える、というのが独立不定詞のイメージです。
なぜ「独立」?文の主語との関係と「懸垂不定詞」
「独立」という名前は、先ほど説明したように、不定詞の意味上の主語が、文の主語から「独立」している(=一致しない、または特定されていない)ことから来ています。
ここで少し注意したいのが、「懸垂不定詞(けんすいふていし、Dangling Infinitive)」という言葉です。これは、不定詞の意味上の主語が文中に明確に示されておらず、文法的に「宙ぶらりん(dangling)」の状態になってしまっている、文法的に誤り、または不適切とされる不定詞の使い方を指すことがあります。
例:
- △ To get a good grade, hard work is necessary. (良い成績を取るためには、努力が必要だ。)
- この文の主語は “hard work” ですが、「良い成績を取る」のは誰でしょう? 文法的には hard work が成績を取るように読めてしまい、不自然です。(正しくは → To get a good grade, you need to work hard. / For you to get a good grade, hard work is necessary. のように、意味上の主語を明確にするか、主節の主語と一致させる必要があります。)
しかし、今回テーマにしている “To tell the truth,” や “Needless to say,” といった独立不定詞は、長年使われる中で慣用表現として定着し、広く受け入れられているため、懸垂不定詞とはみなされず、文法的に問題ないとされています。
つまり、
- 独立不定詞: 意味上の主語が文の主語と一致しないが、慣用表現として定着し、広く使われているもの。OK!
- 懸垂不定詞: 意味上の主語が不明確で、文法的に不自然または誤りとされるもの。(自分で勝手に作るのは避けるべき)
という違いがあります。私たちが学ぶべきなのは、この「慣用表現として定着した独立不定詞」の方ですね。
独立不定詞は、自分でゼロから作るものではなく、「こういう決まった言い方があるんだな」と、フレーズごと覚えて使うのが基本です!
独立不定詞は副詞的用法の一種?
独立不定詞は、文法的にどう分類されるのでしょうか?
働きとしては、文全体を修飾したり、話し手の態度を示したりするので、不定詞の「副詞的用法」の一種と考えることができます。副詞的用法の中でも、特に文修飾の機能を持つものが、慣用句として定着したのが独立不定詞、というイメージですね。
ちょうど、独立分詞構文(例: Generally speaking, …)が分詞構文の特殊な形であるのと似ています。
ただし、独立不定詞はもはや決まり文句として使われるため、毎回「これは副詞的用法の文修飾だ」と分析するよりも、「こういう意味の挿入句だ」と捉える方が実用的かもしれません。
大切なのは、独立不定詞が文の他の部分から切り離されて、文頭や文中にポンと挿入される副詞句のようなものとして機能する、というイメージを持つことです。
多くの場合、独立不定詞の後ろ(または前後)にはカンマ(,)が付き、文の他の部分と区切られます。

独立不定詞って、慣用句みたいなものなんですね!だから文の主語と関係なくてもOKなんだ!謎が解けました!
これで完璧!よく使われる独立不定詞の慣用表現フレーズ集
独立不定詞の正体が分かったところで、次は実際にどんな表現がよく使われるのか、代表的なものを意味や使い方、例文とともに見ていきましょう!これらを覚えておけば、会話や文章でとても役立ちますよ。
発言の真意・本音を伝える表現 (To tell the truth, To be frank…)
自分の正直な気持ちや、話の核心に触れる前に、前置きとして使われる表現です。
- To tell the truth, / To speak the truth,
- 意味: 実を言うと、本当のことを言うと
- ニュアンス: 少し言いにくい本音や、意外な事実を打ち明ける前に使います。
- 例文: To tell the truth, I didn’t enjoy the party very much. (実を言うと、パーティーはあまり楽しめなかったんだ。)
- 成り立ち?: (If I am) to tell the truth… (もし私が本当のことを言うならば…)から?
- To be frank (with you), / To be honest (with you),
- 意味: 率直に言うと、正直に言って
- ニュアンス: “To tell the truth” とほぼ同じですが、より「遠慮なく、ありのままに」という気持ちが強いかもしれません。”with you” を付けると、相手に対して正直に話す、というニュアンスが加わります。
- 例文: To be frank with you, I think your plan is unrealistic. (率直に言って、あなたの計画は非現実的だと思います。)
- 例文: To be honest, I forgot about our appointment. (正直に言うと、約束のこと忘れてたんだ。)
- 成り立ち?: (If I am) to be frank… (もし私が率直であるならば…)から?
これらの表現は、会話で本音を語る際のスムーズな導入として非常に便利です。
状況をさらに悪化させる表現 (To make matters worse)
「悪いこと」が起こった上で、「さらに追い打ちをかけるように悪いことが起こった」と述べるときに使う、決まり文句です。
- To make matters worse,
- 意味: さらに悪いことには、おまけに悪いことには、事もあろうに
- ニュアンス: すでに良くない状況があり、それに加えて別の良くない出来事が起こったことを示します。「泣きっ面に蜂」のような状況ですね。
- 例文: I lost my wallet, and to make matters worse, it started to rain heavily. (財布をなくした上に、さらに悪いことには、雨が激しく降り始めた。)
- 例文: The train was delayed, and to make matters worse, I left my umbrella at home. (電車が遅れて、さらに悪いことには、傘を家に忘れてきた。)
- 成り立ち?: (This happened) to make matters worse. (事態をさらに悪化させるために(これが起こった))のような目的の不定詞が独立した? 少し解釈が難しいですが、結果的に状況が悪化したことを示すフレーズとして定着しています。
不幸な出来事が重なった状況を描写する際に、覚えておくと使える表現です。
話を切り出す・順序を示す表現 (To begin with, To start with)
いくつかの理由や項目を列挙する際に、「まず第一に」「手始めに」と、話を切り出すために使われる表現です。
- To begin with, / To start with,
- 意味: まず第一に、手始めに、そもそも
- ニュアンス: 議論や説明を始めるとき、あるいは複数の理由やポイントの最初のものを提示するときに使います。”First of all,” とほぼ同じ意味です。「そもそも」という意味で、根本的な原因や理由を指摘する際に使われることもあります。
- 例文: There are several reasons why I quit the job. To begin with, the salary was too low. (私が仕事を辞めたのにはいくつか理由がある。まず第一に、給料が低すぎたことだ。)
- 例文: To start with, let’s review what we learned last week. (手始めに、先週学んだことを復習しましょう。)
- 例文: Why didn’t you call me? To begin with, I didn’t have your number. (なんで電話くれなかったの? そもそも、君の番号を知らなかったんだよ。)
- 成り立ち?: (If we are) to begin with… (もし我々がこれから始めるならば…)のような意味合いから?
プレゼンテーションや議論、説明などで話を整理して伝える際に非常に役立つフレーズです。
譲歩や確信を表す表現 (To be sure)
相手の意見や事実を一旦認めつつ、その後に反対意見や別の側面を述べるときに使う「譲歩」の表現、または「確かに」と確信を込めて同意する際に使われます。
- To be sure,
- 意味: 確かに~だが、なるほど(譲歩)、確かに(確信)
- ニュアンス:
- 譲歩: 文頭や文中に挿入され、「確かにその点は認めるけれど、しかし…」と、反対意見や対照的な事実を導入する。 (…, but …) が後に続くことが多い。
- 確信: 「本当に」「疑いなく」という意味で、同意や事実の強調に使う。(やや古風な言い方かも)
- 例文(譲歩): He is young, to be sure, but he is very experienced. (彼は確かに若いが、とても経験豊富だ。)
- 例文(譲歩): To be sure, the task was difficult, but we managed to complete it. (確かに、その仕事は困難だったが、私たちはなんとか完成させることができた。)
- 例文(確信): “Is this the right way?” “To be sure!” (「こっちで合ってる?」「もちろんだとも!」)
- 成り立ち?: (It is) to be sure (that…) (…ということは確かである)のような形から?
特に譲歩の用法は、議論や文章でバランスの取れた視点を示す際に役立ちます。
周知の事実を示す表現 (Needless to say, Strange to say)
「言うまでもないことだが」「奇妙なことだが」と、聞き手も知っているであろう事実や、意外な事実を導入する際に使われます。
- Needless to say,
- 意味: 言うまでもなく、もちろん
- ニュアンス: 聞き手も当然分かっているであろう、自明の理を述べる前に置きます。”It goes without saying that…” と同じ意味です。
- 例文: Needless to say, practice is essential for mastering a skill. (言うまでもなく、技術を習得するには練習が不可欠だ。)
- 例文: He is very smart, and, needless to say, he passed the exam easily. (彼はとても賢く、そして言うまでもなく、簡単に試験に合格した。)
- 成り立ち?: (It is) needless to say (that…) (…ということは言う必要がない)から?
- Strange to say, / Strange to relate,
- 意味: 奇妙なことに(言えば)、不思議な話だが
- ニュアンス: これから述べる内容が、普通では考えられないような、不思議で奇妙な出来事であることを示唆します。”Strange to relate” は少し古風な言い方です。
- 例文: Strange to say, I saw the same black cat three times today. (奇妙なことに、私は今日同じ黒猫を3回見た。)
- 例文: It snowed heavily in April, strange to say. (4月に大雪が降った、奇妙なことに。)
- 成り立ち?: (It is) strange to say (that…) (…と言うのは奇妙なことだ)から?
“Needless to say” は非常によく使われる便利な表現ですね。
比喩や言い換えを表す表現 (So to speak)
直接的な表現を避けたり、分かりやすく言い換えたりするために「いわば」「例えて言えば」という意味で使われる表現です。
- So to speak,
- 意味: いわば、例えて言えば、言ってみれば
- ニュアンス: 直前の表現が比喩的な言い方であることや、少し言葉を補って言い換えていることを示します。文末や文中に挿入されることが多いです。
- 例文: He is a walking dictionary, so to speak. (彼はいわば生き字引だ。)
- 例文: This new technology is, so to speak, the key to our future. (この新しい技術は、いわば、私たちの未来への鍵なのです。)
- 成り立ち?: (If I am allowed) so to speak… (もしそう言うことが許されるならば…)のようなニュアンスから?
少し硬い表現や、分かりにくい比喩を使った後に添えることで、表現を和らげる効果があります。
要約や簡潔化を表す表現 (To put it simply, To sum up…)
話をまとめたり、複雑な内容を分かりやすく言い換えたりする際に使われます。
- To put it simply [briefly/mildly/bluntly],
- 意味: 簡単に言えば / 手短に言えば / 控えめに言えば / 端的に言えば
- ニュアンス: “put it ~” は「~に表現する」という意味。”To put it + 副詞” の形で、「(副詞)な言い方をすれば」という意味になります。話の要点を伝えたり、表現の仕方(控えめ、単刀直入など)を示したりするのに使います。
- 例文: To put it simply, our project failed. (簡単に言えば、私たちのプロジェクトは失敗した。)
- 例文: He was, to put it mildly, not very happy about the result. (控えめに言っても、彼はその結果にあまり満足していなかった。)
- To sum up, / To summarize,
- 意味: 要するに、要約すると
- ニュアンス: これまでの話の要点をまとめて結論を述べるときに使います。プレゼンテーションやレポートの締めくくりなどでよく使われます。”In summary,” と同じ意味です。
- 例文: To sum up, we need to reconsider our marketing strategy. (要するに、私たちはマーケティング戦略を再考する必要がある。)
- To be brief, / To make a long story short,
- 意味: 手短に言えば、かいつまんで言えば
- ニュアンス: 長い話を短くまとめて伝える際に使います。”To make a long story short” はより口語的な表現です。
- 例文: To be brief, the party was a great success. (手短に言えば、パーティーは大成功だった。)
- 例文: We had a lot of trouble getting here, but to make a long story short, we finally made it. (ここに来るまで色々大変だったんだけど、かいつまんで言えば、なんとかたどり着いたよ。)
これらの表現は、話を分かりやすく整理したり、効果的に締めくくったりするのに役立ちますね。
その他の重要な慣用表現 (To do someone justice, Not to mention…)
- To do someone justice, / To give someone their due,
- 意味: ~を公平に評価すれば、~のために言っておくと、~の名誉のために言えば
- ニュアンス: ある人に対して、批判的な意見や不利な状況がある中で、その人の良い点や正しい点を公平に評価して述べるときに使います。
- 例文: The movie wasn’t great, but to do the actors justice, they performed very well. (映画は素晴らしくなかったが、役者たちの名誉のために言っておくと、彼らの演技はとても良かった。)
- 例文: To give him his due, he is a hard worker, although he lacks experience. (彼を公平に評価すれば、経験は足りないが、彼は努力家だ。)
- Not to mention ~, / To say nothing of ~,
- 意味: ~は言うまでもなく、~に加えて
- ニュアンス: すでに述べたことに加えて、さらに強調したい情報(言うまでもないほど明らかなこと、あるいはより重要なこと)を付け加える際に使います。”~” の部分には名詞(句)が来ます。”Let alone ~” に近い意味合いですが、こちらは肯定的な文脈でも使えます。
- 例文: He speaks French fluently, not to mention English. (彼は英語は言うまでもなく、フランス語も流暢に話す。)
- 例文: The hotel offers great food, to say nothing of the comfortable rooms. (そのホテルは快適な部屋は言うまでもなく、素晴らしい食事も提供している。)
- 成り立ち?: “We do not need to mention ~” (~に言及する必要はない)のような意味合いから?
これらの表現も、文脈に深みを与えたり、論点を明確にしたりするのに役立ちます。
独立不定詞の慣用表現は本当にたくさんあります!ここで紹介したのは代表的なものですが、他にも色々な表現があります。出会うたびに少しずつ覚えていくのが良いでしょう。
たくさんありすぎて覚えきれるか不安です… 全部覚えないとダメですか?
いえいえ、そんなことはありませんよ!もちろん、たくさん知っているに越したことはありませんが、まずは今回紹介した中でも、特に太字で強調されているような、よく使われる基本的な表現から覚えていくのがおすすめです。例えば、”To tell the truth”, “Needless to say”, “To begin with”, “So to speak” あたりは、使えると会話や文章がぐっと豊かになります。焦らず、一つひとつ確実に自分のものにしていきましょう!
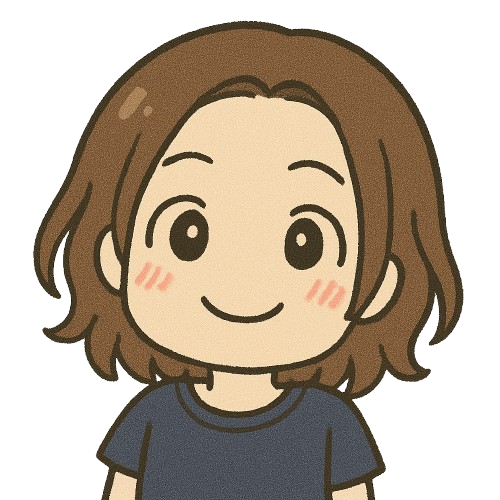
本当にたくさんあるんですね!でも、意味と使い方が分かると、便利そうなフレーズばかり!まずはよく使うものから挑戦してみます!
まとめ:独立不定詞を使いこなして表現を豊かに!
今回は、不定詞の中でも少し特殊で、慣用的な使われ方をすることが多い「独立不定詞」について、その基本的な考え方から代表的なフレーズまで、詳しく見てきました。最後に、今回の重要ポイントを整理しておきましょう。
- 独立不定詞とは:
- 主に「to + 動詞の原形」の形で、文頭や文中にカンマ(,)とともに置かれることが多い。
- 文全体の意味合いを修飾したり、話し手の態度を示したりする副詞句のような働きをする。
- 不定詞の意味上の主語が、文の主語と一致しないか、一般の人々であるため、慣用的に主語が明示されない。
- 多くは決まったフレーズ(慣用表現)として使われる。
- 注意点:
- 文法的に問題のある「懸垂不定詞」とは区別される(慣用表現はOK)。
- 基本的には決まったフレーズをそのまま覚えて使うのが良い。
- 代表的な慣用表現(例):
- To tell the truth, / To be frank, (実を言うと、率直に言うと)
- To make matters worse, (さらに悪いことには)
- To begin with, / To start with, (まず第一に)
- To be sure, (確かに~だが)
- Needless to say, (言うまでもなく)
- Strange to say, (奇妙なことに)
- So to speak, (いわば)
- To put it simply, (簡単に言えば)
- To sum up, (要するに)
- Not to mention ~, (~は言うまでもなく)
- ポイント:独立不定詞は便利な表現だが、多用は避け、文脈に合ったものを選ぶ。まずはよく使われる基本フレーズからマスターしよう!
独立不定詞は、一見すると「これって文法的にどうなってるの?」と不思議に思うかもしれませんが、その多くは「よく使われるお決まりのフレーズ」として理解し、そのまま覚えてしまうのが最も効率的で実践的なアプローチです。
これらの表現を自然に使えるようになると、会話に前置きを加えたり、文章の論理構成を明確にしたり、表現にニュアンスを加えたりするのに非常に役立ちます。ぜひ、今回学んだフレーズを実際のコミュニケーションの中で意識して使ってみてください。使えば使うほど、あなたの英語表現はもっと豊かで洗練されたものになっていきますよ!

独立不定詞、慣用句として覚えれば怖くないですね!便利なフレーズがたくさんあったので、少しずつ使ってみたいと思います!

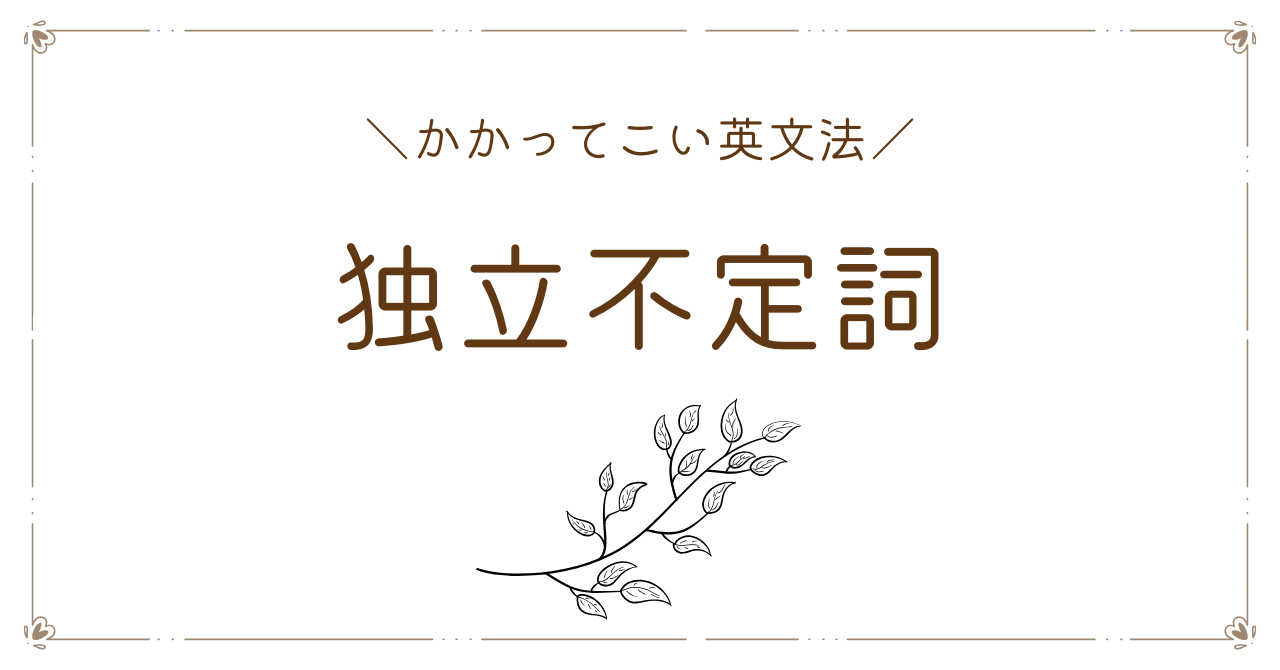
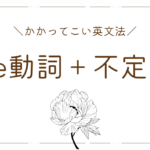
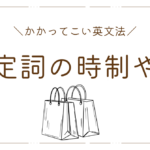
コメント