英語で「~の」って言いたいとき、名詞に「’s」をつけるのか、それとも「of」を使うのか、迷ってしまうことってありませんか?「John’s bag」なのか「the bag of John」なのか…どっちが自然なんだろう?って。英語学習を始めたばかりの方や、学生さん、TOEICのスコアアップを目指している方にとって、この名詞の所有格の使い分けは、意外とつまずきやすいポイントかもしれませんね。
でも、安心してください!この記事では、そんな名詞の所有格の作り方や使い分けのルールを、基礎からじっくり、そしてとっても分かりやすく解説していきます。アポストロフィS (‘s) を使う場合、前置詞 of を使う場合、それぞれのパターンや注意点、さらには「二重所有格」なんていうちょっと発展的な内容まで、しっかりカバーしますよ。この記事を読めば、今までモヤモヤしていた所有格のルールがクリアになって、自信を持って英語で「~の」を表現できるようになるはずです!一緒に所有格マスターを目指しましょう!

「~の」の表現、これでバッチリ使いこなせますね!
名詞の所有格とは?「誰の」「何の」を明確にする表現
まずは、名詞の所有格ってそもそも何なのか、基本的なところから押さえていきましょう。難しく考えずに、リラックスして聞いてくださいね。
所有格の基本的な役割:「~の」で所有や所属を示す
名詞の所有格というのは、読んで字のごとく、「誰が何かを所有しているか」や「何かが何かに所属しているか」を示す形のことです。日本語で言うところの「~の」という助詞に近い働きをします。
例えば、
- Tom’s car (トムの車) → 車はトムが所有している
- the cat‘s tail (その猫のしっぽ) → しっぽはその猫に所属している
- the color of the sky (空の色) → 色は空というものに属する性質
こんな風に、2つの名詞の関係性を「~の」という意味でつなぐのが所有格の役割なんです。これがないと、「トム 車」「猫 しっぽ」みたいに単語がバラバラで、意味が分かりにくくなってしまいますよね。
‘s と of を使い分ける?所有格の2つの表現方法
英語で「~の」を表す主な方法は、大きく分けて2つあります。
- アポストロフィS (‘s) を使う方法: 名詞の語尾に ‘s (アポストロフィ エス) を付ける形です。複数形の名詞が -s で終わる場合は、アポストロフィ (‘) だけを付けることもあります。
- 例: Sarah‘s idea (サラのアイデア), my parents’ house (私の両親の家)
- 前置詞 of を使う方法: 「the A of B」という形で、「BのA」という意味を表します。
- 例: the title of the book (その本のタイトル), the population of Japan (日本の人口)
「じゃあ、いつ ‘s を使って、いつ of を使えばいいの?」って思いますよね。これが所有格を学ぶ上での大きなポイントになります。大まかなルールはありますが、例外や慣用的な表現もあるので、これから詳しく見ていきましょう。
基本的には、「生き物」の所有は ‘s を使い、「無生物」の所有は of を使うことが多い、と覚えておくと最初のとっかかりとしては良いですよ。でも、これだけではカバーしきれない場合もあるので、注意が必要です。
なぜ所有格の使い分けが大切なの?より自然な英語のために
「別にどっちを使っても意味は通じるんじゃないの?」と思うかもしれません。確かに、簡単なコミュニケーションなら、多少不自然でも相手が察してくれることはあります。でも、より正確で自然な英語を目指すなら、所有格の使い分けはとっても重要なんです。
例えば、「机の脚」を “the table’s leg” と言ってしまうと、ネイティブスピーカーには少し不自然に聞こえることがあります。正しくは “the leg of the table” です。このように、適切な所有格の形を選ぶことで、あなたの英語はずっとスムーズで洗練された印象になります。
また、TOEICなどの英語の試験では、文法的な正しさが問われますから、所有格のルールをしっかり理解しておくことはスコアアップにも繋がります。それに、正しい文法で話したり書いたりできると、自信にも繋がりますよね!

なるほど、’s と of の使い分けって大事なんですね!しっかり覚えたいです!
アポストロフィS (‘s) を使う名詞の所有格:作り方と具体的な使い方
それではまず、アポストロフィS (‘s) を使う所有格の作り方と、どんな場合に使うのかを詳しく見ていきましょう。’s の付け方にはいくつかパターンがあるので、一つずつ確認していきますね。
単数名詞の所有格:基本は名詞 + ‘s
一番基本的なパターンです。単数の名詞(人、動物、物など)の所有格は、その名詞の語尾に ‘s を付けます。
- a boy → a boy‘s cap (少年の帽子)
- my sister → my sister‘s room (私の姉/妹の部屋)
- the dog → the dog‘s food (その犬の食べ物)
- Japan → Japan‘s culture (日本の文化)
- the company → the company‘s profit (その会社の利益)
これはシンプルで分かりやすいですよね。発音は、元の名詞の音に /z/, /s/, /ɪz/ のいずれかの音を加える形になります(元の名詞の最後の音によります)。
複数名詞の所有格:-sで終わる名詞と終わらない名詞の違い
次に、複数名詞の所有格です。これは、その複数名詞が -s で終わるかどうかで ‘s の付け方が変わってきます。
1. 複数名詞が -s で終わらない場合
man (men), woman (women), child (children), people (人々) のように、複数形が -s で終わらない不規則変化の名詞の場合は、単数名詞と同じように ‘s を付けます。
- men → men‘s clothing (紳士服)
- women → women‘s rights (女性の権利)
- children → children‘s toys (子供たちのおもちゃ)
- people → people‘s opinions (人々の意見)
2. 複数名詞が -s で終わる場合
boys, students, cats のように、複数形が規則的に -s で終わる名詞の場合は、語尾にアポストロフィ (‘) だけを付けます。 s を重ねて ‘s とはしないのが一般的です。
- boys → boys’ dreams (少年たちの夢)
- students → students’ lockers (生徒たちのロッカー)
- my friends → my friends’ advice (私の友達たちのアドバイス)
- the cats → the cats’ bowls (その猫たちのボウル)
この場合、発音は元の複数名詞の発音と変わらないことが多いです。例えば、”boys” と “boys'” の発音は同じ /bɔɪz/ です。書くときだけアポストロフィの位置に注意しましょうね。
-sで終わる人名の所有格:’s? それともアポストロフィだけ?
ちょっと悩ましいのが、James, Charles, Chris のように、元々 -s で終わる単数の人名の場合です。この場合の所有格は、実は2通りの書き方が許容されています。
- ‘s を付ける: James‘s book, Charles‘s idea, Chris‘s phone
- アポストロフィ (‘) のみを付ける: James‘ book, Charles‘ idea, Chris‘ phone
どちらの形も文法的には間違いではありません。一般的には、‘s を付ける方が現代の英語ではより一般的とされています。特に、発音の上で /ɪz/ の音を加えて「ジェームズィズ」のように読む場合は ‘s を付けることが多いです。
ただし、古典的な名前(例: Jesus’, Moses’, Socrates’)や、’s を付けると発音しにくい場合、あるいは新聞社などのスタイルガイドによってはアポストロフィのみを推奨していることもあります。
どっちを使えばいいか迷ったら、とりあえず ‘s を付けておけば、ほとんどの場合で問題ないでしょう。ただし、所属する組織や媒体に特定のルールがある場合は、それに従ってくださいね。
例:
- This is Chris’s new car. (これがクリスの新しい車です。)
- I read an article about Dickens’s novels. (ディケンズの小説についての記事を読みました。)
または Dickens’ novels も可。
‘s を使うのは主に「人」や「生き物」:所有のニュアンス
では、どんな場合にこの ‘s を使う所有格が適しているのでしょうか? 最も基本的なのは、「人」や「動物」といった「生き物」が何かを所有している、あるいはそれに関係していることを示す場合です。
- my mother‘s bag (母のかばん)
- the dog‘s kennel (その犬の小屋)
- the bird‘s song (その鳥の歌)
- John‘s success (ジョンの成功)
このように、所有者や主体が生命を持っている場合に ‘s を使うと、とても自然な英語になります。
例外的に’s を使うケース:時間・距離・天体・組織・国など
「生き物」以外は of を使うのが基本、と先ほど少し触れましたが、実は「無生物」でも ‘s を使う例外的なケースがいくつかあります。これらは慣用的に使われることが多いので、覚えておくと便利ですよ。
1. 時間を表す名詞
- today‘s newspaper (今日の新聞)
- yesterday‘s news (昨日のニュース)
- a week‘s holiday (1週間の休暇)
- two hours’ delay (2時間の遅れ) (複数なので ‘ のみ)
- next year‘s plan (来年の計画)
2. 距離を表す名詞
- a mile‘s walk (1マイルの散歩)
- ten minutes’ drive (10分のドライブ)
3. 金額・価値を表す名詞
- a dollar‘s worth of candy (1ドル相当のキャンディ)
- ten thousand yen‘s worth of damage (1万円相当の損害)
4. 天体・自然現象を表す名詞
- the sun‘s rays (太陽光線)
- the earth‘s surface (地表)
- the storm‘s fury (嵐の猛威)
5. 国・都市・場所・組織・乗り物などを擬人化して表す場合
- Japan‘s economy (日本経済)
- London‘s theaters (ロンドンの劇場)
- the company‘s policy (その会社の方針)
- the school‘s reputation (その学校の評判)
- the ship‘s crew (その船の乗組員)
- the car‘s engine (その車のエンジン) ← “the engine of the car” も可
これらの無生物に ‘s を使うケースは、その無生物をまるで人のように扱ったり、ある種の活動体と見なしたりするニュアンスが含まれていることが多いです。特に組織名や国名などは、’s を使うのが一般的ですね。
二重所有格とは?「a friend of mine」の謎を解明
ここで、ちょっと発展的な「二重所有格 (Double Possessive / Double Genitive)」という形を紹介します。「a friend of mine」や「a picture of my sister’s」のような形、見たことありませんか?
これは、「a/an, this/that, some, any, no, which, what など」の限定詞 + 名詞 + of + 所有代名詞 (mine, yours, hers, his, ours, theirs) または 名詞’s という形を取ります。
なぜこんなややこしい形が必要なのでしょうか?それは、”a my friend” や “this John’s book” のように、限定詞 (a, this など) と所有格 (my, John’s など) を直接名詞の前に並べて置くことができないという英語のルールがあるからです。
例:
- She is a friend of mine. (彼女は私の友人の一人です。)
× She is a my friend. (これは間違い)
「私の友人たち (my friends) の中の一人 (a friend)」というニュアンスです。 - I saw a picture of my sister’s. (私は姉/妹の写真の一枚を見ました。)
「姉/妹が持っている写真 (my sister’s pictures) の中の一枚 (a picture)」という意味。
単に「姉/妹が写っている写真」なら “a picture of my sister” となります。 - That brilliant idea of yours saved us. (君のあの素晴らしいアイデアが私たちを救ったんだ。)
- Is this a book of Ken’s? (これはケンの本の一冊ですか?)
二重所有格は、「~の中の一つ」というニュアンスを出すときによく使われます。最初は少し難しく感じるかもしれませんが、この形を知っておくと、より自然な英語表現ができるようになりますよ。
ちなみに、”a friend of John” のように of の後が所有格になっていない場合は、「ジョンという友人」といった同格の意味合いになることがあります。二重所有格の “a friend of John’s” とは意味が異なるので注意しましょう。
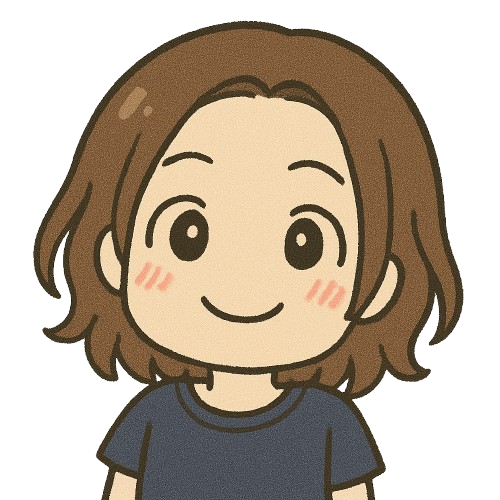
二重所有格、ちょっと難しいけど、そういう理由があったんですね!
前置詞 of を使う名詞の所有格:「モノ」や「こと」の所有・関連
さて、次はもう一つの所有格の表現方法である、前置詞 of を使う形について見ていきましょう。こちらは主に「無生物」や「抽象的なもの」の所有や関連を示すときに使われます。
of を使う所有格の基本:「the A of B」で「BのA」
前置詞 of を使った所有格は、「A of B」という語順で、「BのA」という意味を表します。’s を使う所有格 (B’s A) とは語順が逆になるのがポイントですね。
通常、A と B の両方に the や a/an などの冠詞が付いたり、他の修飾語が付いたりします。
例:
- the door of the house (その家のドア)
- the name of the street (その通りの名前)
- the beginning of the story (その物語の始まり)
- the result of the exam (その試験の結果)
このように、後ろから前に修飾する形で「~の」という意味を作ります。
「無生物」の所有を示す場合は of が基本
原則として、所有者が「無生物(生命のないもの)」である場合、その所有関係は of を使って表します。
- the leg of the table (その机の脚)
△ the table’s leg (不自然に聞こえることが多い)
- the roof of the building (その建物の屋根)
△ the building’s roof (組織名など擬人化する場合は’sも可だが、単なる建物ならofが自然)
- the cover of the book (その本の表紙)
- the bottom of the sea (海底)
- the key of the piano (ピアノの鍵盤) ← “the piano’s key” も使われることがありますが、”of” の方が一般的で硬い印象。
先ほど ‘s を使う例外として「the car’s engine」を挙げましたが、”the engine of the car” ももちろん正しい表現です。どちらを使うかは、文脈や話し手のニュアンス、あるいは慣習によって変わることがあります。一般的に、無生物の場合は of を使うのが無難でフォーマルな印象を与えることが多いです。
「抽象名詞」の関連を示す場合も of を活用
物質的な「モノ」だけでなく、「抽象名詞(目に見えない概念や性質など)」の関連を示す場合も、of がよく使われます。
- the importance of education (教育の重要性)
- the fear of failure (失敗への恐れ)
- the lack of information (情報の不足)
- the beauty of nature (自然の美しさ)
- the history of art (美術の歴史)
- a man of courage (勇気のある男) ← この場合は「~という性質を持った」という意味
このように、具体的な所有関係というよりは、「~に関する」「~という性質の」といった意味合いで of が使われることも多いです。
‘s と of、どちらも使える?迷ったときの考え方
これまで見てきたように、’s と of の使い分けには基本的なルールがありますが、例外やどちらも使えるケースも存在します。迷ったときはどう考えれば良いでしょうか?
1. まずは「生き物か無生物か」で判断する
- 所有者が「人」や「動物」なら、基本は ‘s を考えます。
(例: my sister’s bike) - 所有物が「無生物」で、その一部や属性を表すなら、基本は of を考えます。
(例: the window of the room)
2. ‘s を使う「無生物」の例外を思い出す
- 時間、距離、天体、国、組織などは ‘s を使うことが多いことを覚えておきましょう。
(例: yesterday’s meeting, the earth’s atmosphere, the government’s decision)
3. どちらも使える場合は、ニュアンスや慣習を考慮する
例えば、「the car’s engine」と「the engine of the car」はどちらも正しいですが、’s を使うと車を少し擬人化して見ているような、あるいは車全体とその一部というより密接な関係を強調するニュアンスが出ることがあります。一方、of を使うとより客観的で説明的な響きになります。
また、「the end of the world」のように、慣用的に of が使われる表現はそのまま覚えるのが良いでしょう。「the world’s end」も間違いではありませんが、前者の方が一般的です。
4. 迷ったら辞書や例文で確認する
最終的には、ネイティブスピーカーがどのように使っているかを参考にするのが一番です。辞書で用例を調べたり、信頼できる英語の文章をたくさん読んだりする中で、自然な使い分けが身についていきます。
最初は難しく感じるかもしれませんが、たくさんの英語に触れていくうちに、だんだんと「こっちは ‘s の方がしっくりくるな」「これは of を使うのが自然だな」という感覚が養われていきますよ。焦らずいきましょう!

使い分け、奥が深いですね…。でも、基本を押さえれば大丈夫そう!
まとめ:名詞の所有格をマスターして表現力アップ!
今回は、英語の名詞の所有格について、アポストロフィS (‘s) を使う場合と前置詞 of を使う場合を中心に、その作り方や使い分け、注意点などを詳しく解説してきました。これで「~の」という表現に迷うことが少しでも減ったら嬉しいです。
最後に、この記事でお伝えした重要なポイントをまとめておさらいしましょう。
- 名詞の所有格の基本:「誰の」「何の」という所有や所属の関係を「~の」という意味で表す。
- アポストロフィS (‘s) を使う場合:
- 単数名詞や-sで終わらない複数名詞には「名詞 + ‘s」。
- -sで終わる複数名詞には「名詞 + ‘ (アポストロフィのみ)」。
- -sで終わる人名は「’s」または「’」の両方があり得る(現代では’sが一般的)。
- 主に「人」や「生き物」の所有を示す。
- 例外的に、時間、距離、天体、国、組織などの無生物にも使う。
- 二重所有格「a friend of mine」の形も覚えておこう。
- 前置詞 of を使う場合:
- 「the A of B」の形で「BのA」という意味。
- 主に「無生物」の所有や部分、属性を示す。
- 「抽象名詞」の関連(~に関する、~という性質の)を示す。
- 使い分けのポイント:
- 基本は「生き物なら’s、無生物ならof」。
- ‘sを使う無生物の例外パターンを覚える。
- 迷ったら、より客観的でフォーマルなのは of。
- たくさんの英語に触れて自然な使い方を身につける。
名詞の所有格は、英語の表現を豊かにするための大切なツールの一つです。最初は少しルールが多く感じるかもしれませんが、例文と一緒に繰り返し練習することで、必ずスムーズに使いこなせるようになります。今回の内容を参考に、ぜひ日々の英語学習に活かしてみてくださいね。応援しています!

所有格、スッキリ理解できました!これから自信を持って使えそうです!

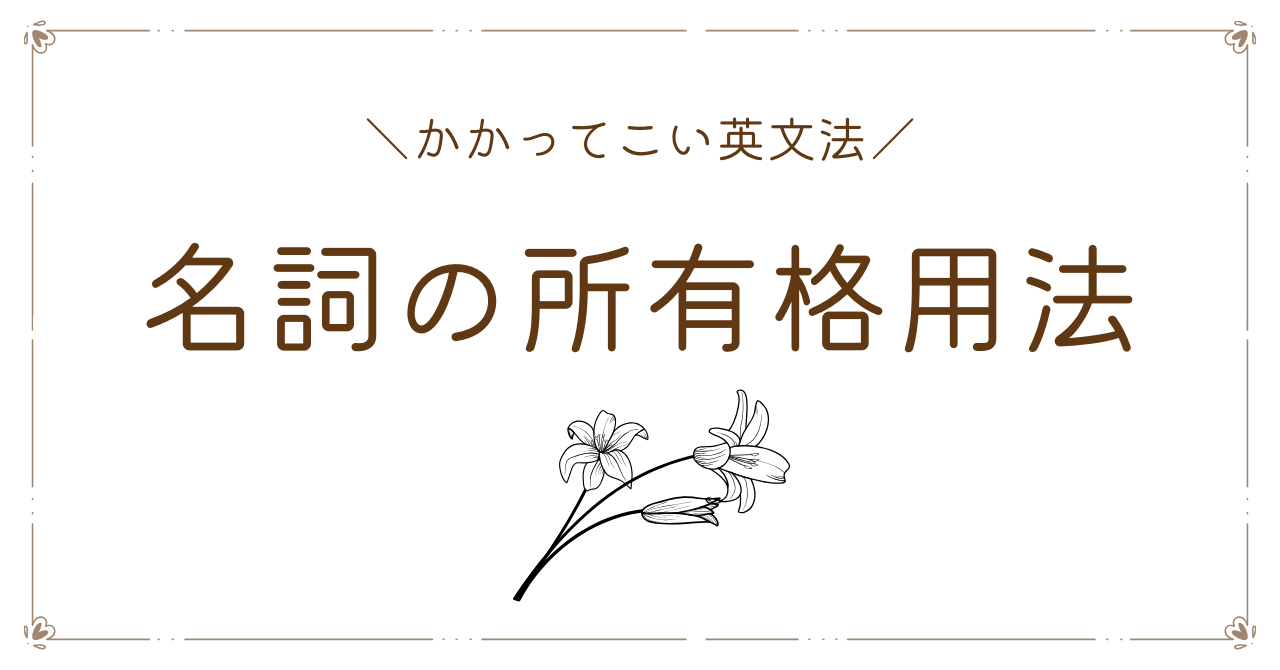
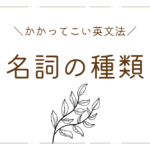

コメント