英語の文を読んでいると、”to” の後ろに動詞の元の形(原形)がくっついている形、本当によく見かけますよね! “I want to go…” とか “It’s important to study…” みたいに。でも、この “to + 動詞の原形” のかたまりって、文の中で色々な意味や働きをしていて、「結局これって何なの?」「どう訳せばいいの?」って混乱してしまうこと、ありませんか?「不定詞」っていう名前も、なんだか漠然としていて掴みどころがない感じがしますよね。
でも実は、この「不定詞」は英語の文を組み立てる上でめちゃくちゃ便利で重要な働きをしているんです!この記事では、そんな不定詞の基本中の基本、「to + 動詞の原形」という形(to不定詞)に焦点を当てて、その正体と、大きく分けて3つある使い方(名詞的用法・形容詞的用法・副詞的用法)を、初心者の方にも「なるほど!」と納得してもらえるように、基礎からじっくり解説していきます。不定詞をマスターすれば、英文の読み書きがもっとスムーズに、そして楽しくなりますよ!

不定詞って、学校で習ったけど、いまいちよく分かってないかも… 用法が3つもあるなんて…!
不定詞ってそもそも何?「to + 動詞の原形」の正体を探る
まずは、「不定詞」という言葉の意味と、それが英語の中でどんな役割を果たしているのか、基本的な概念から押さえていきましょう。ここが理解できると、3つの用法もスムーズに頭に入ってきますよ。
不定詞の定義:「形が決まっていない」= 用法が多様!
不定詞(ふていし、Infinitive)という名前、なんだか不思議ですよね。「定まっていない詞(ことば)」ってどういうことでしょう?
これは、不定詞が文の中で特定の品詞(名詞、形容詞、副詞)に役割が「限定されていない」、つまり色々な品詞の働きをすることができる、という意味合いから来ています。まさに、形を変えずに色々な役をこなせる、英語界の名俳優のような存在なんです!
英語の不定詞には、主に「to不定詞(to + 動詞の原形)」と「原形不定詞(動詞の原形 ※toが付かない)」の2種類がありますが、一般的に「不定詞」と言う場合、特に断りがなければ「to不定詞」のことを指すことが多いです。この記事でも、主にこの「to不定詞」について解説していきます。
【不定詞の正体】
- 基本の形: to + 動詞の原形 (例: to play, to eat, to study, to be)
- 特徴: 元々は動詞だが、文の中では名詞、形容詞、副詞のいずれかの働きをする。
- 意味:「~すること」「~するための」「~するために」など、用法によって様々。
動詞の「動作」や「状態」といった意味を持ちながら、文の中では別の品詞の役割を演じる、このハイブリッドな性質が不定詞の最大の特徴であり、便利さの秘密でもあるんですね。
なぜ不定詞を使うの?英語表現を豊かにする役割
では、なぜ英語ではこの不定詞という形がよく使われるのでしょうか? それは、不定詞を使うことで様々なメリットがあるからです。
- 動詞を名詞・形容詞・副詞として使いたい時に便利: 例えば、「泳ぐこと」と言いたい時に、動詞 swim を名詞化するために to swim という形を使ったり、「読むための本」と言いたい時に book を修飾するために to read を使ったりできます。新しい単語を覚えなくても、動詞を使って表現の幅を広げられるんです。
- 文を簡潔にする: 例えば、「私は彼が試験に合格することを望んでいる」を “I hope that he will pass the exam.” と言う代わりに、”I hope for him to pass the exam.” のように、that節を使わずに不定詞で表現できる場合があります。(※これは不定詞の意味上の主語という少し応用的な内容ですが)
- 複雑な意味合いを表現できる: 特に副詞的用法では、「目的」「結果」「原因」「理由」など、文脈に応じて様々なニュアンスを付け加えることができます。
不定詞は、英語の文構造を柔軟にし、表現をより豊かに、そして時にはより簡潔にするために欠かせないツールなんですね。
不定詞とよく似た働きをするものに「動名詞(~ing形)」があります。特に名詞的用法ではどちらを使うかで意味合いが変わることもあるので、それはまた別の記事で詳しく解説しますね!
不定詞の3つの用法:名詞・形容詞・副詞に変身!
さて、不定詞(to + 動詞の原形)が文の中で果たす主な働きは、大きく分けて以下の3つです。これが、不定詞学習の核となる「3つの用法」です。
- 名詞的用法 (Noun Use): 不定詞が名詞のように扱われ、文の中で主語(S)、補語(C)、目的語(O)になる。「~すること」と訳されることが多い。
- 形容詞的用法 (Adjectival Use): 不定詞が形容詞のように働き、前の名詞を修飾する。「~するための、~すべき、~するような」と訳されることが多い。
- 副詞的用法 (Adverbial Use): 不定詞が副詞のように働き、動詞、形容詞、副詞、文全体などを修飾する。「~するために(目的)、~して(原因・結果)」など、様々な意味を表す。
【3つの用法のイメージ】
<不定詞の3用法イメージ図>
+–→ 名詞の働き (S, C, O になる):「~すること」
[to + 動詞の原形] (不定詞)—-┼–→ 形容詞の働き (前の名詞を修飾):「~するための」
+–→ 副詞の働き (動詞などを修飾):「~するために」etc.
同じ「to + 動詞の原形」という形でも、文の中での役割によってこんなにも意味や働きが変わるんですね!これから、この3つの用法について、一つずつ詳しく見ていきましょう。

不定詞って、名詞にも形容詞にも副詞にもなれるんだ!すごい変身能力!だから「不定」なんですね!
不定詞の名詞的用法:「~すること」と訳す基本パターン
まずは、不定詞が名詞と同じ働きをする「名詞的用法」から見ていきましょう。これは不定詞の用法の中でも比較的理解しやすい、基本となる使い方です。
名詞的用法の意味と役割:「~すること」という名詞の塊
不定詞の名詞的用法では、「to + 動詞の原形」のかたまり全体が、まるで一つの名詞のように機能します。そして、その意味は基本的に「~すること」と訳すことができます。
名詞が文の中で主語(S)、補語(C)、目的語(O)になれるように、名詞的用法の不定詞も、文の中でこれらの役割を果たすことができるんです。
主語(S)になる場合:「~することは…だ」
不定詞が文の主語(S)になるパターンです。「~することは…だ」という意味の文になります。
【例文】
- To master English requires a lot of effort. (英語を習得することは多くの努力を必要とする。)
- [To master English] が文全体の主語(S)になっています。
- To get up early is good for your health. (早く起きることは健康によい。)
- [To get up early] が主語(S)です。
- To travel alone can be exciting. (一人で旅することはワクワクすることがありうる。)
- [To travel alone] が主語(S)です。
ただし、このように不定詞をそのまま主語にするのは、少し硬い響きがあり、特に長い場合は「頭でっかち」な印象を与えることがあります。そのため、実際の英語では、次に紹介する形式主語 “It” を使う形の方がはるかに一般的です。
形式主語 “It” を使う形:「It is ~ to do …」
不定詞が主語になる文では、形式主語(仮主語)の “It” を文頭に置き、本当の主語である不定詞句(真主語)を文の後ろに回す形が非常によく使われます。
It is [形容詞/名詞] to + 動詞の原形 … (~することは…だ)
【例文】
- 元の文: To master English is difficult.
- 形式主語構文: It is difficult to master English. (英語を習得することは難しい。)
- It = 形式主語 / to master English = 真主語
- 元の文: To get up early is good for your health.
- 形式主語構文: It is good for your health to get up early. (早く起きることは健康によい。)
- It is important to keep your promises. (約束を守ることは重要だ。)
- It was fun to play tennis with them. (彼らとテニスをすることは楽しかった。)
この「It is ~ to do …」の形は、会話でも書き言葉でも頻繁に使われるので、しっかりマスターしましょう!
「It is ~ for [人] to do …」([人]が~することは…だ)や「It is ~ of [人] to do …」(~するとは[人]は…だ)のように、不定詞の動作主(意味上の主語)を示す形もあります。これは少し応用的な内容です。
補語(C)になる場合:「~は…することだ」 (SVC)
不定詞が、第2文型(SVC)の補語(C)になるパターンです。「主語(S) = 補語(C)」の関係が成り立ち、「主語は~することだ」という意味を表します。主に be動詞の後ろに来ます。
【例文】
- My dream is to become a pilot. (私の夢はパイロットになることです。)
- S(My dream) = C(to become a pilot) の関係。
- Her hobby is to collect stamps. (彼女の趣味は切手を集めることです。)
- S(Her hobby) = C(to collect stamps) の関係。
- The most important thing is to try your best. (最も重要なことは最善を尽くすことです。)
- S(The most important thing) = C(to try your best) の関係。
- To see is to believe. (見ることは信じることだ。→百聞は一見にしかず)
- 主語も補語も不定詞の例。ことわざです。
主語が何であるか(=何することか)を説明する役割を果たしていますね。
目的語(O)になる場合:「~することを…する」 (SVO)
不定詞が、第3文型(SVO)などの目的語(O)になるパターンです。「~することを…する」という意味になります。多くの動詞が、目的語として不定詞をとることができます。
【目的語に不定詞をとる主な動詞】
- want to do (~したい)
- hope to do (~することを望む)
- wish to do (~したいと願う)
- like to do (~することが好きだ) ※動名詞(-ing)も可
- love to do (~することが大好きだ) ※動名詞(-ing)も可
- need to do (~する必要がある)
- decide to do (~することを決める)
- plan to do (~することを計画する)
- try to do (~しようと試みる) ※動名詞(-ing)だと「試しに~してみる」
- learn to do (~することを学ぶ)
- promise to do (~することを約束する)
- refuse to do (~することを拒む)
- offer to do (~することを申し出る)
- agree to do (~することに同意する)
- expect to do (~することを期待する)
- manage to do (なんとか~する)
【例文】
- I want to travel around the world. (私は世界中を旅したい。)
- want の目的語が [to travel around the world]
- She decided to change her job. (彼女は仕事を変えることを決めた。)
- decided の目的語が [to change her job]
- He promised to call me later. (彼は後で私に電話することを約束した。)
- promised の目的語が [to call me later]
- Don’t forget to lock the door. (ドアに鍵をかけることを忘れないで。)
- forget の目的語が [to lock the door] ※forget は動名詞(-ing)もとるが意味が違う
このように、動詞の後ろに「~すること」という意味の目的語として不定詞が来るパターンは非常に多いです。どの動詞が to不定詞を目的語にとるかは、少しずつ覚えていく必要がありますね。
疑問詞 + to不定詞:「何を~すべきか」などの意味の塊
これも名詞的用法の一種で、「疑問詞 (what, when, where, which, how, whether) + to不定詞」の形で、一つの名詞の塊(名詞句)として扱われます。文の中で主語(S)、補語(C)、目的語(O)になることができます。
【意味】
- what to do : 何をすべきか
- when to start : いつ始めるべきか
- where to go : どこへ行くべきか
- which to choose : どちらを選ぶべきか
- how to use : どのように使うべきか(~の仕方)
- whether to accept or not : 受け入れるべきかどうか
※ why to do という形は通常使われません。
【例文】
- I don’t know what to say. (私は何を言うべきか分からない。)
- know の目的語(O)になっています。
- Please tell me how to get to the station. (駅への行き方を教えてください。)
- tell の間接目的語 me に対する直接目的語(O)のような働き。
- The problem is when to begin the project. (問題はいつプロジェクトを始めるべきかだ。)
- be動詞 is の補語(C)になっています。
- Where to stay hasn’t been decided yet. (どこに滞在すべきかはまだ決まっていない。)
- 文全体の主語(S)になっています。
この「疑問詞 + to不定詞」の形は、非常に便利で会話でもよく使われるので、ぜひ覚えておきましょう!
「疑問詞 + to不定詞」は、「疑問詞 + 主語 + should + 動詞の原形」で書き換えられることが多いです。(例: what to say = what I should say)

名詞的用法、分かりやすい!「~すること」って覚えればいいんですね!形式主語 It や疑問詞 + to不定詞も便利そう!
不定詞の形容詞的用法:「~するための」「~すべき」名詞を修飾
次に、不定詞が形容詞と同じ働きをする「形容詞的用法」を見ていきましょう。名詞を詳しく説明する使い方です。
形容詞的用法の意味と役割:名詞を後ろから修飾
不定詞の形容詞的用法では、「to + 動詞の原形」のかたまりが、直前にある名詞(または代名詞)の意味を詳しく説明(修飾)します。ちょうど、関係代名詞の節(例: a book which I should read)が前の名詞を修飾するのと似たような働きですね。
そして、形容詞的用法の不定詞は、原則として修飾する名詞の「後ろ」に置かれます(後置修飾)。これは限定用法の形容詞が他の語句を伴って長くなる場合に後ろに置かれるのと同じルールです。
意味としては、文脈に応じて「~するための」「~すべき」「~するような」などと訳されます。
基本的な使い方:「名詞 + to不定詞」
最も基本的な形は、「名詞」のすぐ後ろに「to不定詞」が続く形です。
【例文】
- I need something to write with. (私は何か書くためのものが必要です。)
- [something] ← [to write with]。「書くための」が something を修飾。
- He has no friends to play with. (彼には一緒に遊ぶ友達がいません。)
- [no friends] ← [to play with]。「一緒に遊ぶ」が friends を修飾。
- Do you have time to talk now? (今、話す時間はありますか?)
- [time] ← [to talk]。「話すための」が time を修飾。
- She is looking for a house to live in. (彼女は住むための家を探しています。)
- [a house] ← [to live in]。「住むための」が house を修飾。
- It’s a good place to visit. (そこは訪れるのによい場所です。)
- [a good place] ← [to visit]。「訪れるための」が place を修飾。
- He was the first man to walk on the moon. (彼は月面を歩いた最初の男性でした。)
- [the first man] ← [to walk on the moon]。「歩いた」が man を修飾。※叙述的な意味合いも含む。
注意点:不定詞の後ろに前置詞が必要な場合がある!
上の例文のいくつか (write with, play with, live in, swim in) で気づいたかもしれませんが、形容詞的用法の不定詞では、不定詞の後ろに前置詞 (with, in, on, for など) が必要になる場合があります。
これは、修飾される名詞が、不定詞の動詞の「目的語」ではなく、「前置詞の目的語」になる関係の場合に起こります。
【考え方】
修飾される名詞を不定詞の動詞の後ろに置いてみて、自然な意味になるか(特に前置詞が必要ないか)を確認します。
- something to write with → write with something (何かを使って書く) → with が必要。
- friends to play with → play with friends (友達と遊ぶ) → with が必要。
- a house to live in → live in a house (家に住む) → in が必要。
- a chair to sit on → sit on a chair (椅子に座る) → on が必要。
- a pen to write with → write with a pen (ペンで書く) → with が必要。
- paper to write on → write on paper (紙に書く) → on が必要。
もし前置詞がないと意味がおかしくなります。(例: live a house ??)
一方、前置詞が不要な場合:
- homework to do → do homework (宿題をする) → 前置詞不要。
- a book to read → read a book (本を読む) → 前置詞不要。
- time to talk → talk (about time?) ではない → 前置詞不要。(この talk は自動詞)
この「前置詞が必要かどうか」は、形容詞的用法を使いこなす上での大きなポイントであり、間違いやすいところでもあります。「名詞を動詞の後ろに置いてみる」という確認方法をぜひ使ってみてください。
「be動詞 + to不定詞」の形:予定・義務・可能・運命・意図
これは少し特殊な用法で、不定詞が be動詞の補語 (C) になり、「be to do」の形で助動詞のような意味合いを表します。主に書き言葉やフォーマルな場面で使われます。
【主な意味】
- 予定:「~することになっている」 (be scheduled to)
- The President is to visit Japan next month. (大統領は来月日本を訪問する予定だ。)
- 義務・命令:「~すべきである」「~しなければならない」 (should, must)
- You are to report to the police immediately. (君は直ちに警察に報告しなければならない。)
- Students are to wear uniforms. (生徒は制服を着用すること。)
- 可能:「~できる」 (can be done ※主に受動態で否定文・疑問文)
- Not a sound was to be heard. (物音一つ聞こえなかった。[聞かれることができなかった])
- How am I to solve this problem? (私はどうやってこの問題を解くことができるだろうか?[解くべきか])
- 運命:「~する運命にある」 (be destined to)
- He was never to return to his hometown. (彼は二度と故郷に戻ることはない運命だった。)
- 意図・目的:「もし~するつもりなら」 (intend to ※主に If節の中で)
- If you are to succeed, you must work harder. (もし成功するつもりなら、もっと熱心に働かなければならない。)
この be to 不定詞は、文脈によってどの意味になるか判断する必要があります。少し難易度が高いですが、特に書き言葉では重要な表現なので、頭の片隅に置いておくと良いでしょう。
be to 不定詞は、助動詞の will, should, can などが持つ意味合いを、よりフォーマルに、あるいは客観的に表現する方法と考えることができます。
不定詞の副詞的用法:目的・結果・原因・理由・判断の根拠などを説明
最後に、不定詞が副詞と同じ働きをする「副詞的用法」を見ていきましょう。これは、不定詞の用法の中で最も意味が多く、文脈判断が重要になる用法です。
副詞的用法の意味と役割:動詞・形容詞・副詞・文を修飾
不定詞の副詞的用法では、「to + 動詞の原形」のかたまりが、動詞、形容詞、他の副詞、あるいは文全体を修飾し、様々な意味を付け加えます。「なぜ?」「何のために?」「どんな結果?」「どう判断して?」といった情報を提供してくれるんですね。
主な意味としては、目的、結果、感情の原因・理由、判断の根拠、形容詞の修飾、条件などがあります。どの意味になるかは、文脈や一緒に使われる語句から判断します。
目的:「~するために」 (in order to / so as to)
副詞的用法の中で最もよく使われるのが、この「目的」を表す意味です。「~するために」と訳し、動作の目的を示します。
【例文】
- I went to the library to borrow some books. (私は本を数冊借りるために図書館へ行った。)
- なぜ図書館へ行ったのか? → 借りるために (went を修飾)
- He is saving money to buy a new car. (彼は新しい車を買うためにお金を貯めている。)
- なぜお金を貯めているのか? → 買うために (is saving を修飾)
- We need to hurry to catch the train. (私たちは電車に乗るために急ぐ必要がある。)
- なぜ急ぐ必要があるのか? → 乗るために (hurry を修飾)
目的の意味をより明確にしたい場合は、不定詞の前に “in order to do” や “so as to do” を使うこともできます。特に書き言葉やフォーマルな場面で使われます。
- She studied hard in order to pass the exam. (彼女は試験に合格するために一生懸命勉強した。)
- Please speak clearly so as to be understood. (理解されるようにはっきりと話してください。) ※受動態の不定詞
否定形(~しないために)は “in order not to do” / “so as not to do” となります。(例: He left early in order not to be late. 彼は遅れないように早く出発した。)
結果:「(その結果)~した」「~して…になった」
動作や出来事の「結果」を表す用法です。「~して、その結果…した」という流れで訳します。この用法で使われる動詞はある程度限られています。
【主なパターン】
- 無意志動詞 (live, grow up, awake など) + to do: 「生きて~歳になった」「成長して~になった」「目が覚めると~だと気づいた」
- He lived to be ninety years old. (彼は生きて90歳になった。)
- She grew up to become a doctor. (彼女は成長して医者になった。)
- I awoke to find myself famous. (私は目が覚めると自分が有名になっていることに気づいた。)
- only to do: 「結局~しただけだった」「~したが、残念ながら…だった」という、予想外の、あるいは残念な結果を表します。
- He hurried to the station, only to miss the train. (彼は駅へ急いだが、結局電車に乗り遅れただけだった。)
- She studied hard for the test, only to fail. (彼女はテストのために一生懸命勉強したが、結局失敗しただけだった。)
- never to do: 「~して、二度と…しなかった」という結果を表します。
- He left his hometown, never to return. (彼は故郷を去り、二度と戻らなかった。)
結果の用法は、目的の用法ほど頻繁ではありませんが、特に only to do はよく使われるので覚えておきましょう。
感情の原因・理由:「~して…(感情)」
感情を表す形容詞 (glad, happy, sad, sorry, surprised, pleased, disappointed など) や一部の動詞の後ろに不定詞が置かれ、その感情が「なぜ」生じたのか、原因や理由を示す用法です。「~して(~なので)…な気持ちだ」と訳します。
【例文】
- I am happy to see you again. (あなたにまた会えて嬉しいです。)
- なぜ happy なのか? → あなたに会えたから (happy を修飾)
- She was surprised to hear the news. (彼女はその知らせを聞いて驚いた。)
- なぜ surprised なのか? → その知らせを聞いたから (surprised を修飾)
- We are sorry to cause you trouble. (ご迷惑をおかけして申し訳ありません。)
- なぜ sorry なのか? → ご迷惑をおかけしたから (sorry を修飾)
- He must be pleased to receive your gift. (彼はあなたの贈り物を受け取って喜んでいるに違いない。)
- なぜ pleased なのか? → 贈り物を受け取ったから (pleased を修飾)
感情の理由を説明する際に、非常に自然でよく使われるパターンです。
判断の根拠:「~するとは…だ」「~するなんて…だ」
文全体の内容、特に話し手の判断(~に違いない、~とは…な人だ など)の根拠を示す用法です。「~するなんて」「~するとは」と訳します。
【例文】
- He must be crazy to say such a thing. (そんなことを言うなんて、彼はおかしいに違いない。)
- なぜ crazy だと判断するのか? → そんなことを言うから (must be crazy という判断の根拠)
- She must be very kind to help a stranger like that. (あのように見知らぬ人を助けるとは、彼女はとても親切に違いない。)
- なぜ kind だと判断するのか? → 見知らぬ人を助けるから (must be very kind という判断の根拠)
- He was foolish to make the same mistake again. (同じ間違いを再び犯すなんて、彼は愚かだった。)
- なぜ foolish だったと判断するのか? → 同じ間違いを犯したから (was foolish という判断の根拠)
この用法は、人の性質に対する判断 (kind, foolish, clever, careless など) と一緒に使われることが多く、その場合、「It is ~ of 人 to do」の形(形式主語構文)になることもよくあります。
- It was kind of you to help me. (私を助けてくれるなんて、あなたは親切でした。)
- = You were kind to help me.
- It is careless of him to forget the key. (鍵を忘れるなんて、彼は不注意だ。)
- = He is careless to forget the key.
形容詞の修飾:「~するのに…だ」「~するには…だ」
形容詞の意味を限定したり、その程度を説明したりする用法です。特に、easy, difficult, hard, dangerous, safe, possible, impossible, ready, eager などの形容詞の後ろによく来ます。「~するには…だ」と訳します。
【例文】
- This book is easy to understand. (この本は理解するのが簡単だ。)
- 何が easy なのか? → 理解すること (easy を修飾)
- English is difficult to master. (英語は習得するのが難しい。)
- 何が difficult なのか? → 習得すること (difficult を修飾)
- The river is dangerous to swim in. (その川は泳ぐのが危険だ。)
- 何が dangerous なのか? → 泳ぐこと (dangerous を修飾) ※ここでも前置詞 in が必要! (swim in the river)
- Are you ready to go? (行く準備はできていますか?)
- 何の ready なのか? → 行くこと (ready を修飾)
- She is eager to learn new things. (彼女は新しいことを学びたがっている。)
- 何に eager なのか? → 学ぶこと (eager を修飾)
形容詞がどんな点でそうなのかを具体的に示すことができます。
条件:「もし~すれば」(文脈依存)
頻度は高くありませんが、文脈によっては不定詞が「もし~すれば」「~するとしたら」という条件の意味を表すことがあります。仮定法のようなニュアンスで使われることが多いです。
【例文】
- To hear him speak, you would think he was a native speaker. (彼の話を聞けば、あなたは彼がネイティブスピーカーだと思うだろう。)
- = If you heard him speak, …
- You would be surprised to see the result. (その結果を見たら、あなたは驚くだろう。)
- = If you saw the result, …
この用法は少し見抜きにくいかもしれませんが、文脈(特に would などの助動詞)から判断できることがあります。
副詞的用法の意味は多岐にわたりますが、最も多いのは「目的」です。迷ったらまず「~するために」と訳してみて、文脈に合わない場合は他の意味(結果、原因、判断の根拠など)を考えてみると良いでしょう。

副詞的用法、意味がいっぱいありすぎる…!覚えられるかなぁ。でも「目的」が一番多いんですね!
まとめ:不定詞の3つの用法を使いこなそう!
今回は、英語の基本的な表現要素である「不定詞」、特に「to不定詞」について、その正体から3つの重要な用法(名詞的・形容詞的・副詞的)まで、基礎からじっくりと解説してきました。最後に、不定詞マスターのための重要ポイントをまとめておきましょう!
- 不定詞とは: 基本形は「to + 動詞の原形」。動詞の意味を持ちつつ、文中で名詞・形容詞・副詞の働きをする変幻自在な表現。
- 3つの用法:
- ① 名詞的用法:「~すること」
- 役割: 主語(S)・補語(C)・目的語(O)になる。
- 主語の場合: 形式主語 It を使う「It is ~ to do」の形が一般的。
- 補語の場合: 「Sは~することだ」(SVC)。
- 目的語の場合: want to do, hope to do など動詞の後ろに来る。
- 疑問詞 + to不定詞 (what to do など) も名詞の塊を作る。
- ② 形容詞的用法:「~するための」「~すべき」
- 役割: 前の名詞を後ろから修飾する(後置修飾)。
- 注意点: 不定詞の後ろに前置詞が必要な場合がある (a pen to write with)。
- 特殊用法: be to不定詞(予定・義務・可能・運命・意図)。
- ③ 副詞的用法:「~するために」「~して…」など
- 役割: 動詞・形容詞・副詞・文などを修飾し、様々な意味を付け加える。
- 主な意味:
- 目的 (~するために ※最頻出)
- 結果 (~して…した、only to do)
- 感情の原因・理由 (~して嬉しい/悲しい など)
- 判断の根拠 (~するとは…だ)
- 形容詞の修飾 (~するのに簡単/難しい など)
- 条件 (もし~すれば ※稀)
- 見分け方: 文脈判断が重要。
- ① 名詞的用法:「~すること」
- ポイント:同じ「to + 動詞の原形」でも、文の中でどんな「働き」をしているか(名詞?形容詞?副詞?)を見抜くことが、不定詞理解の鍵!
不定詞は、その使い道の多さから、英語学習の初期段階では少し複雑に感じるかもしれません。しかし、この3つの用法をしっかり理解し、区別できるようになれば、英文の構造がよりクリアに見えるようになり、読解力も表現力も格段に向上します。
まずは、それぞれの用法が持つ基本的な意味と役割を覚え、たくさんの例文に触れて「これはどの用法かな?」と考える練習をしてみてください。不定詞は英語の表現を豊かにするための強力な武器です。ぜひマスターして、あなたの英語をさらにステップアップさせましょう!

不定詞の3つの用法、やっと整理できた気がします!それぞれの役割を意識して、これから英文を読んでみます!

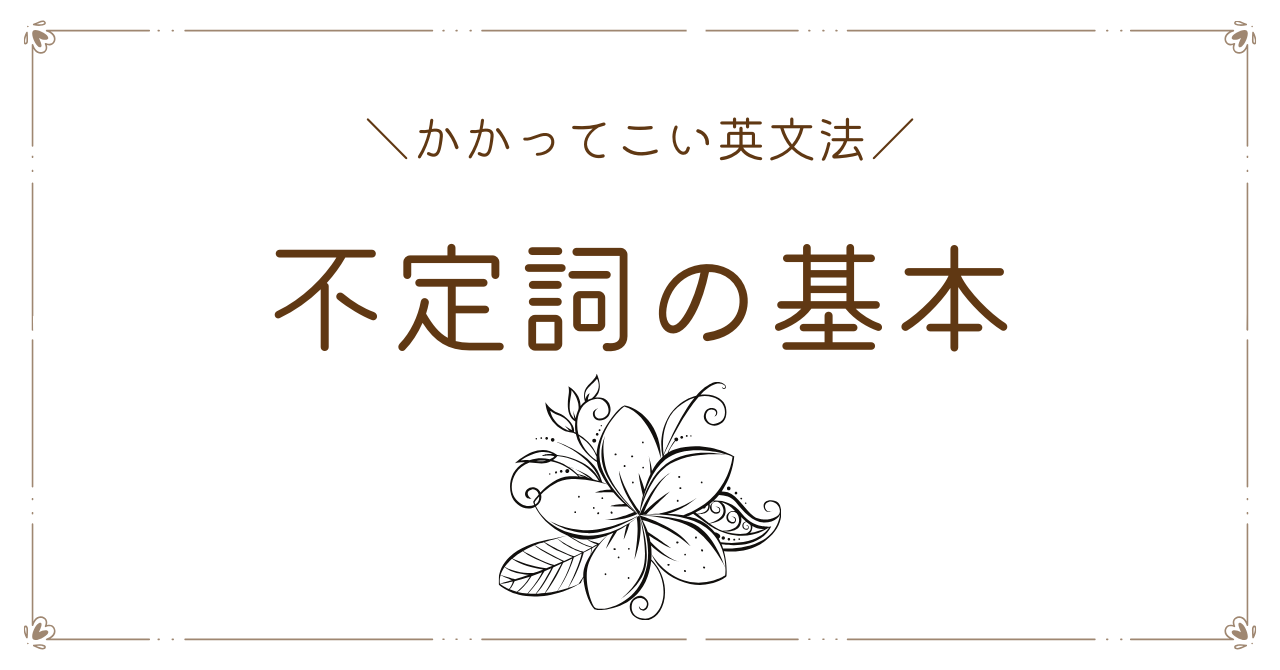
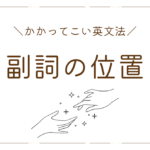
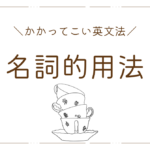
コメント