英語の長文を読んでいると、文の途中で突然カンマ(,)が出てきて、その後に “-ing” や “-ed” で始まるかたまりが出てくること、ありませんか?「あれ?これって文法的にどうなってるの?」「どういう意味で訳せばいいんだろう?」って、手が止まってしまった経験、きっとありますよね。それが、多くの英語学習者さんを悩ませる「分詞構文」かもしれません。
分詞構文って、名前からしてちょっと難しそうな雰囲気が漂っていますよね…。でも、実はこれ、英語の文をグッと短く、そしてスマートにするための便利なテクニックなんです!この記事では、そんな分詞構文の「そもそも何なのか?」という基本から、具体的な作り方、そして「時・理由・条件・譲歩・付帯状況」といった様々な意味と、その見分け方まで、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説していきます。分詞構文をマスターすれば、英文読解がスムーズになるだけでなく、英作文での表現力も格段にアップしますよ!
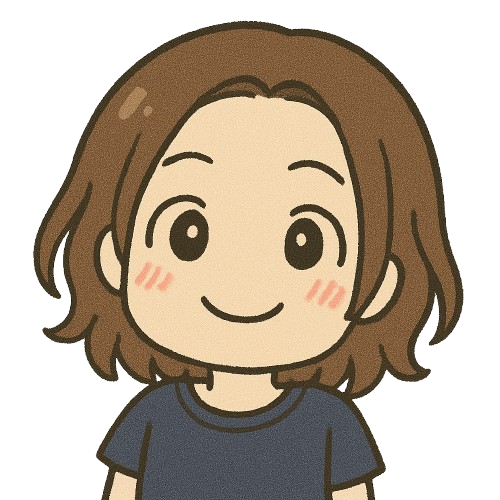
分詞構文…聞いたことはあるけど、やっぱり苦手意識があります…!
分詞構文の基本:そもそも何?なぜ使うの?
まずは、「分詞構文」というものが一体どんなものなのか、そして英語ではなぜこのような形が使われるのか、基本的な考え方をしっかり押さえていきましょう。ここが分かれば、分詞構文への苦手意識もきっと薄れていきますよ。
分詞構文とは「接続詞+主語」を省略したシンプルな形
分詞構文(ぶんしこうぶん)とは、ものすごく簡単に言うと、接続詞(when, because, if, though など)が導く文(副詞節)から、「接続詞」と「主語」を省略し、動詞を「分詞(現在分詞 -ing / 過去分詞 -ed, -en)」に変えて、文全体を短くシンプルにした表現方法のことです。
例えば、こんな2つの文があったとします。
- When I walked along the street, I saw an old friend. (通りを歩いていたとき、私は旧友を見かけた。)
この文の “When I walked along the street” の部分は、「いつ〜したか」という時を表す副詞節ですよね。接続詞 “When” が文を導いています。そして、この副詞節の主語 “I” は、後ろの主節 “I saw an old friend.” の主語 “I” と同じです。
こういう場合に、英語では接続詞 “When” と主語 “I” を省略して、動詞 “walked” を現在分詞 “walking” に変えることで、もっと短い形にすることができるんです。
- Walking along the street, I saw an old friend. (通りを歩いていて、私は旧友を見かけた。)
これが分詞構文です!元の文と比べて、かなりスッキリしましたよね? 分詞構文は、このように副詞節の情報を、分詞を使ってより簡潔に表現するためのテクニックなんです。
分詞構文を使うメリット:文を簡潔に、スマートにする
では、なぜわざわざ分詞構文なんていう形を使うのでしょうか?それには、いくつかのメリットがあるからです。
- 文が簡潔になる: 接続詞と主語(場合によってはbe動詞も)が省略されるので、文全体の語数が減り、スッキリと短くなります。
- 文と文のつながりがスムーズになる: 接続詞を使わずに情報を補足できるため、文の流れが滑らかになり、より洗練された印象を与えます。
- 英語らしいリズム感が出る: 特に書き言葉において、分詞構文を効果的に使うことで、単調さを避け、表現にリズムや変化を持たせることができます。
特に、少し長めの文章や、論理的な文章を書く際には、分詞構文を上手に使えると、より「こなれた」英語に見えることが多いんですよ。
ただし、分詞構文はどちらかというと書き言葉で使われることが多く、日常会話では、特に複雑なものはあまり頻繁には使われない傾向があります。
分詞構文の基本的な作り方:「接続詞削除 → 主語削除 → 動詞を分詞化」
分詞構文の作り方は、基本的には3つのステップで理解できます。元の文(接続詞 + S + V … , S’ + V’ …)から分詞構文を作る手順を見ていきましょう。
【ステップ1】 接続詞を削除する
まず、副詞節を導いている接続詞(when, while, as, because, since, if, though, although など)を取り除きます。
【ステップ2】 副詞節の主語を削除する(主節の主語と同じ場合)
次に、副詞節の主語(S)が、主節の主語(S’)と同じ人物やモノであれば、副詞節の主語(S)を削除します。
※もし主語が違う場合は、主語を残します。これが「独立分詞構文」と呼ばれるもので、後で詳しく説明しますね。
【ステップ3】 副詞節の動詞を分詞に変える
最後に、副詞節の動詞(V)を分詞の形に変えます。ここでのポイントは、元の副詞節が能動態か受動態か、ということです。
- 元の文が能動態の場合 → 現在分詞 (-ing) にする
- 例:walked → walking / studies → studying
- 元の文が受動態 (be動詞 + 過去分詞) の場合 → 過去分詞 (-ed/en) にする (※Being は通常省略される)
- 例:was broken → (Being) broken / is loved → (Being) loved
- Being + 形容詞/名詞 の場合も、Being は通常省略されます。例:was tired → (Being) tired
具体例で見てみましょう!
元の文: Because she felt tired, she went to bed early. (彼女は疲れていたので、早く寝た。)
- 副詞節:Because she felt tired / 主節:she went to bed early
- ステップ1(接続詞削除): She felt tired, she went to bed early.
- ステップ2(主語削除): 副詞節の主語 “She” と主節の主語 “she” は同じ → “She” を削除。
Felt tired, she went to bed early. - ステップ3(動詞を分詞化): 動詞 “felt” は能動態 → 現在分詞 “feeling” にする。
Feeling tired, she went to bed early. (疲れていたので、彼女は早く寝た。) ← これで分詞構文の完成!
もう一つ、受動態の例も見てみましょう。
元の文: As the book was written in easy English, I could read it. (その本は易しい英語で書かれていたので、私はそれを読むことができた。)
- 副詞節:As the book was written in easy English / 主節:I could read it
- おっと、これは主語が違いますね (the book と I)。これだと普通の分詞構文にはできません。独立分詞構文の例として後でまた出てきます。
- ステップ1(接続詞削除): He was defeated, he did not give up.
- ステップ2(主語削除): 副詞節の主語 “He” と主節の主語 “he” は同じ → “He” を削除。
Was defeated, he did not give up. - ステップ3(動詞を分詞化): 動詞 “was defeated” は受動態 → Being defeated にする。そして、受動態の分詞構文では Being は通常省略されるので…
Defeated, he did not give up. (負かされたけれども、彼は諦めなかった。) ← 完成!
この3ステップが分詞構文の基本的な作り方です。能動態なら -ing、受動態なら (Being) + 過去分詞、というルールをしっかり覚えましょう!

なるほど!接続詞と主語を取って、動詞を-ingか過去分詞にするだけなんですね!意外とシンプルかも!
分詞構文の5つの意味と見分け方:時・理由・条件・譲歩・付帯状況
分詞構文は文をシンプルにしてくれる便利なものですが、一つやっかいな点があります。それは、接続詞が省略されてしまうため、元の文が持っていた接続詞の意味(時、理由、条件、譲歩など)を、文脈から判断しなければならないということです。分詞構文がどんな意味を表す可能性があるのか、主な5つのパターンと、その見分け方のヒントを見ていきましょう。
① 時:「~とき」「~しながら」 (when, while, as)
最もよく見られる意味の一つが「時」を表す用法です。主節の動作が行われた時や、同時に行われている状況を示します。元の接続詞としては when (~とき), while (~する間), as (~とき、~しながら) などが考えられます。
- Walking along the street, I met an old friend.
- 意味: 通りを歩いていたとき、私は旧友に会った。
- 元の接続詞: When / While I was walking…
- 見分け方のヒント: 主節の出来事 (met) が起こったタイミングや、それと同時に行われていた状況 (walking) を表しています。
- Opening the window, he let in some fresh air.
- 意味: 窓を開けて、彼は新鮮な空気を入れた。
- 元の接続詞: When he opened…
- 見分け方のヒント: 窓を開ける動作と空気を入れる動作が連続して起こっています。
- Turning the corner, she saw a beautiful park.
- 意味: 角を曲がったとき、彼女は美しい公園を見た。
- 元の接続詞: When she turned…
- 見分け方のヒント: 角を曲がるという動作の直後に、公園を見るという出来事が起こっています。
② 理由・原因:「~なので」「~だから」 (because, as, since)
分詞構文は、主節の出来事の理由や原因を示すこともよくあります。元の接続詞としては because, as, since (~なので) などが考えられます。
- Feeling tired, I went to bed early.
- 意味: 疲れていたので、私は早く寝た。
- 元の接続詞: Because / As I felt tired…
- 見分け方のヒント: 早く寝た理由が「疲れていたこと」である、という因果関係が文脈から読み取れます。
- Not knowing what to say, I remained silent.
- 意味: 何と言っていいかわからなかったので、私は黙っていた。
- 元の接続詞: Because / As I did not know…
- 見分け方のヒント: 黙っていた理由が「何と言っていいかわからなかったこと」だと推測できます。(これは否定形の分詞構文ですね。後で説明します。)
- Written in simple language, this book is easy for beginners.
- 意味: 簡単な言葉で書かれているので、この本は初心者にとって易しい。
- 元の接続詞: Because / As it is written…
- 見分け方のヒント: 本が易しい理由が「簡単な言葉で書かれていること」だと考えられます。(これは受動態の分詞構文です。)
③ 条件:「もし~ならば」 (if)
頻度はそれほど高くありませんが、分詞構文が条件「もし~ならば」を表すこともあります。元の接続詞としては if が考えられます。
- Turning to the left, you will find the station.
- 意味: もし左に曲がれば、あなたは駅を見つけるでしょう。
- 元の接続詞: If you turn to the left…
- 見分け方のヒント: 「左に曲がる」という条件を満たせば、「駅を見つける」という結果になる、という関係が読み取れます。道案内の場面などで使われます。
- Used properly, this tool can be very helpful.
- 意味: もし適切に使われれば、この道具はとても役に立つだろう。
- 元の接続詞: If it is used properly…
- 見分け方のヒント: 「適切に使われる」という条件の下で、「役に立つ」という結果になることを示唆しています。
- Admitting what he says, I still cannot trust him.
- 意味: 仮に彼の言うことを認めるとしても、私はまだ彼を信用できない。
- 元の接続詞: Even if I admit what he says… (譲歩とも取れます)
- 見分け方のヒント: 分詞構文の慣用表現(後述)の中には、条件や譲歩の意味を持つものがあります。
④ 譲歩:「~だけれども」「~にもかかわらず」 (though, although, even though)
条件と同様に、頻度は高くありませんが、「~だけれども」「~にもかかわらず」という譲歩の意味を表すこともあります。元の接続詞としては though, although, even though などが考えられます。
- Admitting he is young, he is very capable.
- 意味: 彼は若いけれども、とても有能だ。
- 元の接続詞: Although / Though I admit he is young…
- 見分け方のヒント: 「若い」ことと「有能だ」という、一見相反するような内容が結びついており、逆接(譲歩)の関係が推測されます。
- Living next door, I rarely see him.
- 意味: 隣に住んでいるけれども、私はめったに彼に会わない。
- 元の接続詞: Though / Although I live next door…
- 見分け方のヒント: 隣に住んでいれば普通はよく会いそうなのに、「めったに会わない」という予想外の結果になっており、譲歩の関係と考えられます。
- Defeated, he did not give up.
- 意味: 負かされたけれども、彼は諦めなかった。
- 元の接続詞: Though / Although he was defeated…
- 見分け方のヒント: 負かされた状況にもかかわらず、「諦めなかった」という逆の内容が続いています。
譲歩の意味を明確にしたい場合は、分詞構文の前に Though や Although を残すこともあります。(例: Though living next door, I rarely see him.)
⑤ 付帯状況:「~しながら」「そして~した」 (and)
これは、他の4つとは少し性質が異なり、主節の動作と同時に行われる状況や、主節の動作に引き続いて起こる状況を補足的に説明する用法です。「~しながら」や「そして~した」と訳せることが多いです。
1. 同時進行の動作:「~しながら」
主節の動作が行われている間、同時に別の動作や状態が進行していることを示します。特に文末にカンマ(,)とともに置かれることが多いです。
- He walked along the river, singing a song.
- 意味: 彼は歌を歌いながら、川沿いを歩いた。
- 訳し方のヒント: 「そして歌を歌った」と訳すことも可能ですが、「~しながら」の方が自然な場合が多いです。主語の He が「歩く」と「歌う」を同時に行っています。
- She told me the story, tears filling her eyes.
- 意味: 彼女は目に涙を浮かべながら、私にその話をした。
- 訳し方のヒント: これは独立分詞構文の付帯状況です。”tears” (涙) が “filling” (満たす) の意味上の主語になっています。「彼女が話す」のと「涙が目を満たす」のが同時に起こっています。
- He sat on the bench, surrounded by pigeons.
- 意味: 彼はハトに囲まれながら、ベンチに座っていた。
- 訳し方のヒント: 「彼が座る」のと「ハトに囲まれる」状態が同時に存在しています。主語 He が囲まれる側なので過去分詞 surrounded が使われています。
2. 連続する動作:「そして~した」
主節の動作に引き続いて、すぐに別の動作が行われたことを示します。「そして~した」と訳すと自然です。
- He opened the door, revealing a messy room.
- 意味: 彼はドアを開けた、そして散らかった部屋が現れた。(ドアを開けると散らかった部屋が見えた)
- 訳し方のヒント: ドアを開ける動作 (opened) の結果として、部屋が見える (revealing) という状況が続いています。
- The train left the station at noon, arriving in Osaka at 3 PM.
- 意味: その電車は正午に駅を出発し、そして午後3時に大阪に到着した。
- 訳し方のヒント: 出発 (left) という動作に続いて、到着 (arriving) という動作が起こっています。
付帯状況は、文脈によって「同時」なのか「連続」なのかを判断する必要がありますが、どちらも主節の情報を補足する役割を果たしています。
意味の見分け方のコツ:文脈判断が最重要!接続詞を補ってみる
さて、5つの意味を見てきましたが、「じゃあ、実際に出てきた分詞構文がどの意味なのか、どうやって見分ければいいの?」と思いますよね。
残念ながら、「これがあれば絶対にこの意味!」という明確なルールはありません。分詞構文の意味は、文脈全体から判断するのが基本です。
ただし、見分けるためのヒントや練習方法はあります。
- 前後の文脈を読む: 分詞構文だけで意味を決めつけず、主節の内容や、その文が含まれる段落全体の流れを見て、最も自然な意味(時、理由、条件、譲歩、付帯状況)を考えます。
- 接続詞を補ってみる: どの意味か迷ったときは、元の文にあったであろう接続詞 (when, because, if, though など) や “and” を補ってみて、文意が通るか、しっくりくるかを確認する、という練習が非常に有効です。「この接続詞を入れるのが一番自然だな」と感じるものが、その分詞構文の主な意味である可能性が高いです。
例えば、”Walking along the street, I met Ken.” という文なら、「もし通りを歩けば… (If)」や「通りを歩いたけれども… (Though)」と考えるよりは、「通りを歩いていたとき… (When)」と考えるのが一番自然ですよね。
慣れるまでは少し時間がかかるかもしれませんが、たくさんの英文に触れて、文脈から意味を推測する練習を繰り返すことが、分詞構文マスターへの一番の近道です!
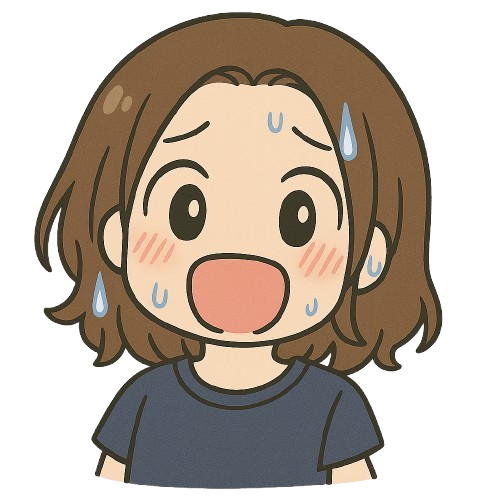
意味が5つもあるなんて…!文脈判断が大事って言われても、自信ないなぁ。接続詞を補う練習、やってみます!
分詞構文の応用:否定形・完了形・独立分詞構文と注意点
分詞構文の基本的な形と意味が分かったところで、もう少し応用的な形や、使う上での注意点も見ていきましょう。これらを理解すると、さらに複雑な英文にも対応できるようになりますよ。
分詞構文の否定形:「not / never + 分詞」
分詞構文を否定の意味(~しないで、~ではないので、など)にしたい場合は、分詞の直前に “not” または “never” を置きます。
- Not knowing his phone number, I couldn’t call him.
- 意味: 彼の電話番号を知らなかったので、私は彼に電話できなかった。
- 元の文のイメージ: Because I did not know his phone number…
- Not feeling well, she decided to stay home.
- 意味: 気分が良くなかったので、彼女は家にいることに決めた。
- 元の文のイメージ: As she did not feel well…
- He walked past me, not saying a word.
- 意味: 彼は一言も言わずに、私のそばを通り過ぎた。(付帯状況)
- 元の文のイメージ: …and he did not say a word.
- Never having seen snow before, the child was very excited.
- 意味: それまで一度も雪を見たことがなかったので、その子供はとても興奮していた。(完了形の否定)
- 元の文のイメージ: Because the child had never seen snow before…
否定語を分詞の前に置く、というルールさえ覚えておけば、難しくはありませんね。
完了形の分詞構文:「having + 過去分詞」
普通の分詞構文 (例: -ing) は、主節の時制と「同じ時」または「それより後」の出来事を表すことが多いですが、主節の時制よりも「前のこと」を表したい場合があります。そんなときに使うのが完了形の分詞構文「having + 過去分詞」です。
これは、元の副詞節の動詞が、主節の動詞よりも過去(あるいは過去完了など、より古い時制)だった場合に用いられます。
- Having finished my homework, I went to bed.
- 意味: 宿題を終えた後で、私は寝た。
- 時制の関係: 「寝た (went: 過去)」よりも「宿題を終えた」方が前。
- 元の文のイメージ: After / Because I had finished my homework…
- Having lived in London for years, he knows the city well.
- 意味: ロンドンに長年住んでいたので、彼はその街をよく知っている。
- 時制の関係: 「よく知っている (knows: 現在)」よりも「住んでいた」方が前(過去から現在までの経験・継続が背景にある)。
- 元の文のイメージ: As he has lived / lived in London for years…
完了形の分詞構文も、時・理由・条件・譲歩などの意味を表します。
また、元の副詞節が受動態で、かつ主節より前のことを表す場合は、「Having been + 過去分詞」という形になります。ただし、この “Having been” も省略されることが非常に多いです。
- Having been written in haste, the report has many mistakes.
→ (Having been を省略して) Written in haste, the report has many mistakes.- 意味: 急いで書かれたので、そのレポートには多くの間違いがある。
- 時制の関係: 「間違いがある (has: 現在)」よりも「書かれた」方が前。かつ受動態。
- 元の文のイメージ: Because it was written / has been written in haste…
- Having been defeated twice, the team lost confidence.
→ (Having been を省略して) Defeated twice, the team lost confidence.- 意味: 2度負かされたので、そのチームは自信を失った。
- 時制の関係: 「自信を失った (lost: 過去)」よりも「負かされた」方が前。かつ受動態。
- 元の文のイメージ: Because the team had been defeated twice…
完了形の分詞構文は少し難しく感じるかもしれませんが、「主節より前のこと」を表すという点を押さえておきましょう。
完了形の分詞構文の “Having been” が省略されると、形の上では普通の過去分詞の分詞構文と同じになってしまいますね (例: Written…, Defeated…)。そのため、主節より前のことなのか、それとも同じ時制の受動態なのかは、やはり文脈から判断する必要があります。
独立分詞構文:主語が違う場合は主語を残す
分詞構文の作り方のステップ2で、「副詞節の主語と主節の主語が同じなら、副詞節の主語を削除する」と説明しました。では、主語が違う場合はどうなるのでしょうか?
その答えが独立分詞構文(どくりつぶんしこうぶん)です。主語が違う場合は、分詞の前に、その意味上の主語を省略せずに残しておく、というルールになっています。
- It being fine, we went for a picnic.
- 意味: 天気が良かったので、私たちはピクニックに行った。
- 主語の関係: 副詞節の主語は “It” (天気)、主節の主語は “we”。違うので It を残す。
- 元の文のイメージ: As it was fine…
- The sun having set, we started for home.
- 意味: 日が沈んだので、私たちは家路についた。
- 主語の関係: 副詞節の主語は “The sun”、主節の主語は “we”。違うので The sun を残す。
- 時制: 「家路についた (started: 過去)」よりも「日が沈んだ」方が前なので、完了形の分詞構文 (having set) が使われている。
- 元の文のイメージ: After / Because the sun had set…
- There being no bus service, we had to walk.
- 意味: バス便がなかったので、私たちは歩かなければならなかった。
- 主語の関係: 元の文が “There was no bus service…” (There is/are 構文) の場合、意味上の主語として There を残す。
- 元の文のイメージ: As there was no bus service…
- She told me the story, tears filling her eyes. (付帯状況)
- 意味: 彼女は目に涙を浮かべながら、私にその話をした。
- 主語の関係: 主節の主語は “She”、分詞 “filling” の意味上の主語は “tears”。違うので tears を残す。
独立分詞構文は、形が少し特殊に見えますが、「主語が違うから残したんだな」と分かれば理解しやすくなります。前回学んだ慣用表現 (weather permitting など) の多くも、この独立分詞構文から派生したものでしたね。
分詞構文を使う上での注意点
最後に、分詞構文を使う上で少し気をつけておきたい点を2つほど挙げておきます。
- 意味が曖昧になる可能性: 接続詞を省略するため、文脈によっては複数の意味に解釈できてしまう可能性があります。例えば、”Living in the countryside, he is healthy.” は「田舎に住んでいるので健康的だ(理由)」とも「田舎に住んでいるけれども健康的だ(譲歩)」とも取れるかもしれません(普通は理由でしょうが)。誤解を避けたい場合や、意味を明確に伝えたい場合は、無理に分詞構文を使わず、接続詞を使った方が良い場合もあります。
- 主に書き言葉で使われる: 先にも述べましたが、分詞構文、特に複雑なものや独立分詞構文などは、主に書き言葉(小説、論文、ニュース記事など)で使われる傾向があります。日常会話では、接続詞を使った方が自然で分かりやすいことが多いです。
分詞構文は便利な表現ですが、使う場面や相手、伝えたい内容の明確さなどを考慮して、適切に使うことが大切ですね。

否定形や完了形、独立分詞構文…ちょっと難しいけど、ルールが分かれば読解の時に役立ちそう!注意点も知れてよかったです!
まとめ:分詞構文を理解して使いこなそう!
今回は、英語学習者を悩ませがちな「分詞構文」について、その基本から応用、注意点まで、かなり詳しく掘り下げてきました。最後に、今回の内容をしっかり頭に入れるために、重要なポイントをまとめておきましょう。
- 分詞構文とは: 接続詞が導く副詞節を、分詞を使って簡潔に表現する方法。文をスマートにする。
- 作り方の基本:
- 接続詞を削除。
- 主節と同じ主語なら削除。(違うなら残す → 独立分詞構文)
- 動詞を分詞化:能動態なら現在分詞(-ing)、受動態なら (Being) 過去分詞(-ed/en)。
- 主な5つの意味: 文脈から判断することが最も重要!
- 時: ~とき、~しながら (when, while, as)
- 理由・原因: ~なので、~だから (because, as, since)
- 条件: もし~ならば (if)
- 譲歩: ~だけれども (though, although)
- 付帯状況: ~しながら、そして~した (and)
- 応用的な形:
- 否定形: not / never + 分詞
- 完了形: 主節より前のことを表す → having + 過去分詞 (受動態なら Having been + 過去分詞 → Having been は省略可)
- 独立分詞構文: 主節と主語が違う場合 → 意味上の主語 + 分詞
- 注意点: 意味が曖昧になる可能性、主に書き言葉で使われる。
分詞構文は、接続詞の意味を自分で補って考えなければならないため、慣れるまでは少し難しく感じるかもしれません。しかし、文脈を読む力や、文の構造を把握する力を養う上で、非常に良いトレーニングになります。
まずは、たくさんの英文を読む中で分詞構文に意識的に注目し、「これはどの意味かな?」「元の接続詞は何だろう?」と考えてみることから始めましょう。そして、理解が深まってきたら、簡単なものから英作文でも使ってみるのがおすすめです。分詞構文を使いこなせるようになれば、あなたの英語力は確実にレベルアップしますよ!

分詞構文、手ごわいけど、仕組みが分かると面白いかも!たくさん練習して、使いこなせるようになりたいです!

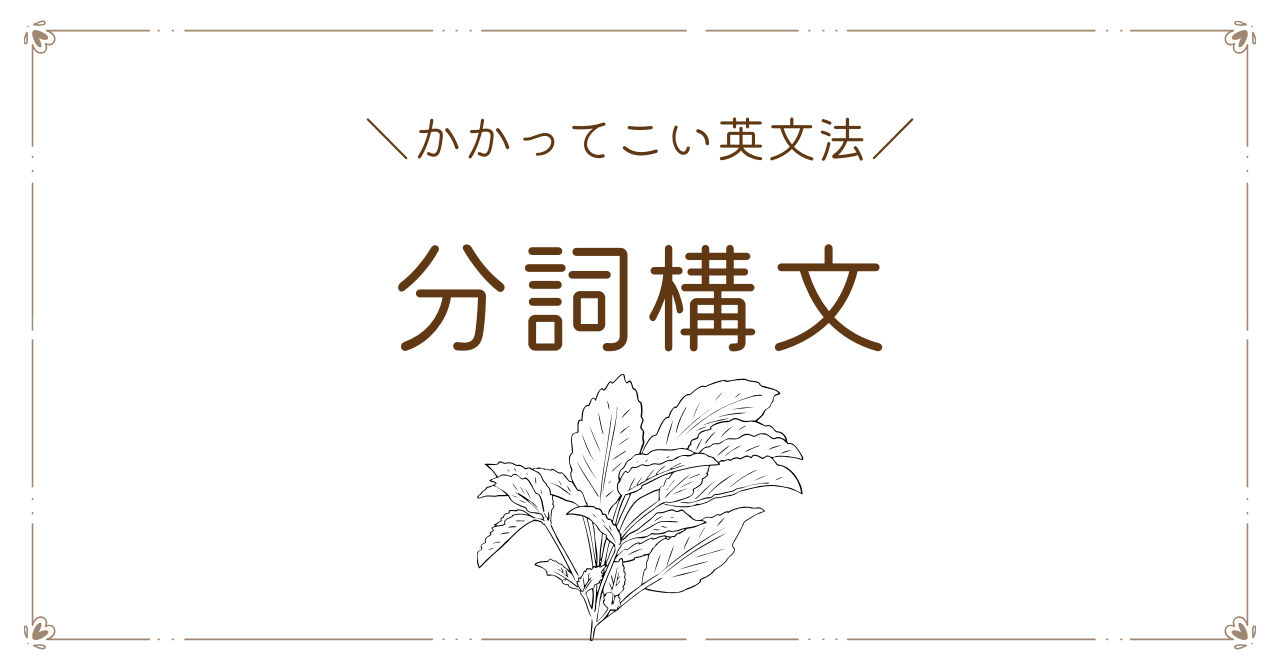
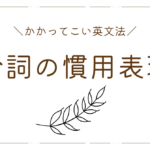
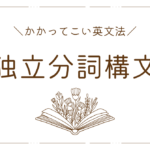
コメント